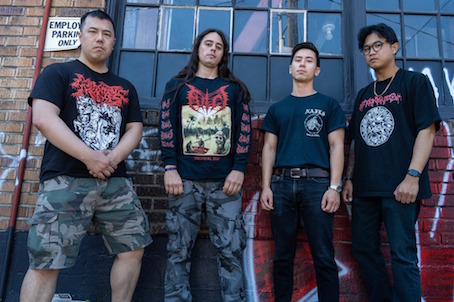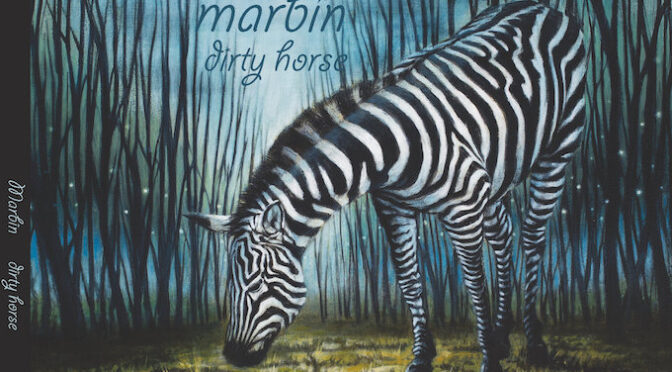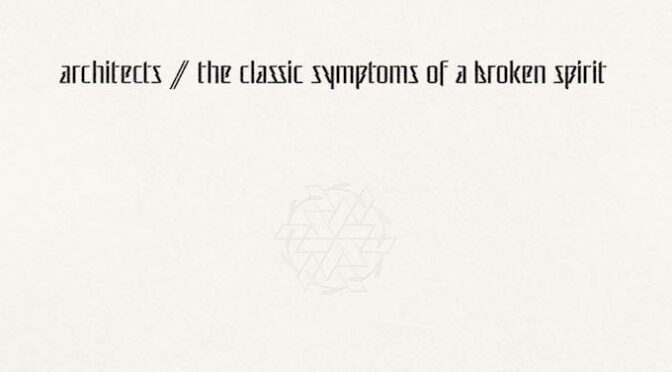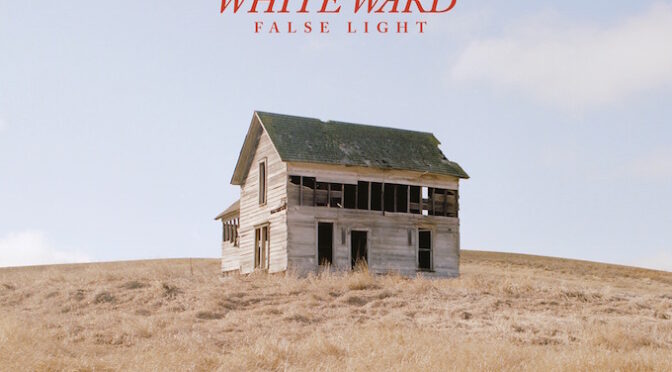COVER STORY : BLIND GUARDIAN “THE GOD MACHINE”
“I think What We Did Now Is How Speed Metal Has To Sound Right Now And This Is How It Can Be Interesting For The New Generation Of Metal Fans.”
THE GOD MACHINE
1984年、ギタリストの André Olbrich は、高校の同級生だった Hansi Kürsch をロックバンドのリハーサル室に誘います。そこから、BLIND GUARDIAN の歴史は始まりました。
「Hansi と僕は修学旅行で酒を飲んでいたんだ。すると突然、彼は King Diamond のように高音で歌い始め、完全におかしくなった。でも僕は同時に、”なんて声なんだ! 信じられない!圧倒されるし、こんなに高い音も出せるんだ!”と思ったんだ」
André はすぐに Hansi を自分のバンドで歌わないかと誘いましたが、Hansi は自分はシンガーではなくギタリストであると主張して断りました。 André のバンドにはすでに2人のギタリストがいて、3人目を加える計画はありませんでした。しかし、2人の間ですぐに妥協が成立します。Hansi のベース/ボーカルとしての参加です。さらに André は最終的に希望をかなえ、1997年、Hansi はベースを置いてボーカルだけに専念することになります。ここに、BLIND GUARDIAN の前身である LUCIFER’S HERITAGE が誕生したのです。
「Hansi が参加した瞬間から、ロックっぽいバンドからメタル・バンドになったんだ」
Hansi が付け加えます。
「André と一緒にバンドを組もうと決めたときから、とても真剣に取り組んでいた。僕ら二人は、夢を生きられない人たちにうんざりしていたんだ。誰もが有名になることについて話していたけど、話すことと実行することは別なんだから」
リハーサル室での地味な活動から抜け出し、新たに LUCIFER’S HERITAGE と改名した彼らは、2本のデモテープをリリースし、ドイツの小さなメタルレーベル、No Remorse Records の目にとまることになります。1988年、彼らはレーベルとレコード契約を結び、その記念として新しい名前を手に入れます。BLIND GUARDIAN。まもなくメタル世界で最も神聖なバンドのひとつとなる名前です。こうして彼らのオデッセイは幕を開けました。
BLIND GUARDIAN の名で最初にリリースされたのは1988年の “Battalions of Fear” で、この作品はより壮大なものに目を向けたスピード・メタルだったと言えます。 André, Hansi, ギタリストの Marcus Siepen、ドラマーの Thomen Stauch は、1987年10月にプロデューサー Kalle Trapp とレコーディング・スタジオに入り、世界の頂点に立ったような気分になっていたと André は明かします。
「スタジオに入ったとき、僕たちはとても高揚していたんだ。ヘヴィ・メタルのシーンの一部になって、自分たちのアルバムを持つことになるとね。録音するのは僕らのデモの曲で、僕らが大好きな曲だったから、最高のアルバムになると確信していたんだ」
“Battalions” のセッションは、この若いバンドにとってスタジオ・レコーディングの猛特訓となりました。クレーフェルトのリハーサル・ルームでデモを作っていた彼らのやり方は、あらゆるミスが目につく無菌状態のスタジオでは通用しなかったのです。”Battalions” は初期のバンドの奔放な野心を、特に “指輪物語” のアラルゴンに感化された中心曲の “Majesty” で見せつけますが、彼らにはまだ学ぶべきことがたくさんありました。特に André にとって、”ギターソロを作曲するべき” という気づきは、今後の BLIND GUARDIAN にとって重要な指針となっていきます。
「もっと時間があれば、もっと良くなっていたかもしれない」と André は振り返ります。「例えばソロの場合、あの時は一発勝負で、運が良ければ2発で録れた記憶がある。2回で録音できなかったものは?自分の問題だ。このままではいけないと思った。次のアルバムでは、通常のバンド・リハーサルだけでなく、一人でリハーサルをして、ギターソロを作曲する必要があるとね。スタジオで自分が何を演奏したいのか、どの音が必要なのかを考えるのではなく、その前に準備する必要があるとわかったんだよ」
“Battalions” がスタジオ・レコーディングの厳しさに対してバンドが準備不足だったとすれば、1989年の “Follow the Blind” は全く別の問題があったと André は言います。
「”Battalions of Fear” では、曲作りに時間的なプレッシャーはなかった。曲は全部できていたからね。デモテープにあった曲で、あと1、2曲書いて、アルバムは完成したんだ。そしたら突然、レーベル・マネージャーが “OK、次のアルバムは1年以内に出してくれ” って言ったんだ。それで僕たちは、まったくナイーブに、”ああ、問題ない!” と言ってしまった。だって、1年なんて結構長いと思ったから」
しかし、その1年はあっという間でした。André は公務員になり、Hansi も見習いとして働いていました。バンドはまだ BLIND GUARDIAN をフルタイムの仕事にすると決めていなかったので、曲作りとリハーサルは仕事の後の深夜に詰め込まれることになっていました。
「要求に応じて音楽を作るというのは、そんなに簡単なことではないとを初めて知った。だから多くのことが急いで行われ、リハーサル室で数回だけアイデアをまとめて曲をリハーサルしたんだ」
とはいえ、”エルリック・サーガ” に感化された “Fast To Madness” などファンタジックなメタルはより存在感を増しました。”Follow the Blind” のために彼らが最後に書いた曲は “Valhalla” で、André はこの曲を単なる “繋ぎ” だと考え、トラックリストから危うくカットするところでした。André の予想に反して今日、この曲は BLIND GUARDIAN の曲の中で最も人気のある曲の一つとなり、ライブの定番曲として観客のシンガロング欲を常に刺激しています。
「僕たちは素晴らしい曲を書くことができた。”Valhalla” は、あまり考えすぎない方が良いという素晴らしい例だ。自分の中から出てくるものをすべて、最初に受け止めてしまえばいい。最初のアイデアを採用する。2つ目のアイデアを待つという選択肢はなく、ただそこにあるものをつかむんだ。それがとても純粋で、とても本質的なことだと思うし、それこそが “Valhalla” なんだ。そして、これこそが純粋な BLIND GUARDIAN なんだ」
“Tales from the Twilight World” は、BLIND GUARDIAN がすべてをまとめ始めたレコードです。エピカルでありながら、比較的ストレートなスピード・メタルを2枚お見舞いした後、”Tales” でバンドは曲がりくねった曲の構成と綿密に重ねられたアレンジを導入し、以降それが彼らの特徴になることを宣言したのです。公務員と労働はすでにバックミラーの彼方にありました。バンドは André と Hansi の仕事になっていたのです。
「最初の2枚のアルバムで稼いだお金を全部つぎ込んで、自分たちの小さなスタジオを買ったんだ。スタジオと同じプロセスが必要だった。学ぶべきだとね。曲を事前にプロデュースする必要があったけど、これは小さなスタジオでしかできない。だから、スタジオ機材を購入したんだ。そして、この技術的な機材を手に入れた瞬間から、Hansi と僕はリハーサルルームで生活するようになった。機械を使って、一分一秒でも早く曲に取りかかろうとしたんだ」
Hansi も変革の時であったことを認めます。
「僕たちはいつもいろいろなことを試すのが好きなんだ。実験に対する情熱は、僕たちのソング・ライティングには欠かせないからね。”Follow The Blind” の後、自分たちで初めてスタジオ機材を手にしたとき、僕たちの選択肢は無限に広がり始めた。これがあの頃感じていたことだ」
“Tales” のハイライトである “Traveler in Time”, “Lost in the Twilight Hall”, “The Last Candle” といった楽曲は、複雑で重く、しかしメロディックでキャッチーな要素を一度に味わうことができました。”Lord of The Ring” では素直に自らの素性を告白。振り返ってみると、これはパワー・メタルの発明、そしてその体系化の始まりようにも感じられますが、2人は会話の中で、意図的にこの用語を避けていました。どのように呼ぶにせよ、”Tales” は明らかにバンドが自分たちの “声” を発見した瞬間でした。
「僕たちは、ミュージシャンとしての自分たちについて考えていた」 と André は言います。「どうすれば自分の個性を生かせるか?リード・ギタリストとしての音色はどうすればいいのか?そして、Hansi はもちろん、ボーカリストとしての自分の個性を見つけ、初めて、僕たちが知っている Hansi のような、カリスマ的なサウンドを奏でたと思う。”Follow the Blind” では、彼はもう少しスラッシーなサウンドを出そうとしていて、どこに行けばいいのかよくわからなかったんだと思う。でも、”Tales” ではわかっていた。そして僕らも分かっていた。みんな、自分たちがどこにいて、どんな音を出したいのかわかっていたんだ」
そして、”Tales” でメインストリームでの成功がもたらされたと Hansi は言います。
「もはや、誰もが BLIND GUARDIAN が何であるかを知っていた。最初の2枚のアルバムよりも当然優れていることは別として、違いを生んだのは人々の意識だった。次のアルバムに対する人々の期待を実感したことで、”Somewhere Far Beyond” の制作は最も重要で困難な曲作りの期間となったんだ」
期待はソングライターとしての自分たちに大きなプレッシャーを与えたと André も同意します。
「だって、”なんてこった、こんなに成功したアルバムがあるのに、どうやったらこれを超えることができるんだ?”って思ったんだから」
今年30周年を迎え記念のツアーも行われた “Somewhere Far Beyond” で BLIND GUARDIAN は、”Tales” のメロディックなアイデアを発展させると同時に、より多くのサウンド要素を導入しました。バグパイプを使った “The Piper’s Calling” とタイトル曲、シンセサイザーによる “Theater of Pain”、さらに “ホビットの冒険” を踏まえた “The Bard’s Song(In the Forest)” では悲しげなアコースティック・ギターを、続編 “The Bard’s Song(The Hobbit)” ではそれを発展させた中世的なサウンドを披露して、バンドは “Tales” における自己発見を倍加させながら、さらに外界へと拡大していったのです。ちなみに、”The Quest For Tanelorn” は、ムアコックのエターナル・チャンピオンシリーズが元ネタ。
「”Tales” から “Somewhere” へ進む中で、明らかな進化があった」と André は言います。「だから、ギターの音をもっとリッチにして、”Tales” でやったことにすべて上乗せしようとしたんだ」
“Somewhere Far Beyond” は同時に、BLIND GUARDIAN がリハーサル・ルーム時代にお世話になったプロデューサー、Kalle Trappe との関係を終了させる作品ともなりました。「彼はプロデューサーとして非常に保守的で、僕がサウンドやプロダクションに関して革新的なアイデアを思いついても、いつもブロックされた」と André は嘆きます。だからこそ、1995年の “Imaginations from the Other Side” でバンドは、METALLICA の80年代を支えた伝説のエンジニア、Flemming Rasmussen を起用することにしたのです。
「彼はミュージシャンの尻を叩く方法を知っている。前任者は、パフォーマンスとグルーヴとキャラクターにしか興味がなかったんだ。でも Flemming は、僕たちをミュージシャンとして押し上げることを望んでいた。だから、最初は指から血が出るほど演奏していたよ。”もう100%やってるよ!”って言っても彼は、”そんなのは認めないぞ!もっと頑張れ!” と言うんだよ」
Flemming がミキシング・ボードの後ろにいることで、BLIND GUARDIAN はこれまでで最もタイトで、プログレッシブかつ最もダイヤルの合ったアルバムを完成させます。ファンタジー全般を礼賛するタイトルトラックにアーサー王伝説を引用した “Mordred’s Song” まで、”想像のアザー・サイド” を祝賀する “Imaginations” は大ヒットし、バンドにとって待望の国際的なブレイクを成し遂げました。世界のメタル・シーンは、ドイツと日本のオーディエンスがすでに気づいてたことにやっと気づいたのです。また、このアルバムはメロディック・メタルが低迷していた時期に発表された、豊かなレイヤーを持つバロック的なパワー・メタルでした。95年と言えばグランジがまだ優勢で、Nu-metal が徐々に台頭し、アンダーグラウンドの世界はますます過激になるデス・メタルやブラック・メタルに固執していました。それでも、André は気にしませんでした。ロンドンから来た彼のヒーローが、道を示してくれたから。
「僕たちは QUEEN を尊敬していたんだ。彼らは常に、何があろうと自分たち自身のことをやっていた。彼らは個性的で、シーンから完全に独立していた。僕たちも同じようになりたかった。他のバンドを見すぎて、成功したトレンドに自分を合わせようとすると、常に先を行くバンドより少し遅れてしまうから下降する一方なんだ。僕たちは何かを発明するバンドになりたかったんだ」
現在では誰もが認める名盤となっているため、当時 “Nightfall in Middle Earth” がいかに大きな賭けであったかを想像するのは困難かもしれません。BLIND GUARDIAN は常にオタク的な性癖を持っていて、お気に入りの SF やファンタジーの本を基にした歌詞を書いていました。
「僕はオタク的だと思ったことはないし、自分がオタクだとも思っていなかった」と Hansi は抗議しますが。「オタクだったのは、 André と Marcus だ。彼らはコンピュータのロールプレイングに夢中だったからね。でも僕はクールな男だった。彼らがそうしてる間に本を読んでいたんだよ」
“Nightfall” では、トールキンの “シルマリルの物語” をベースにした22曲入りのメタル・オペラを制作し、これまで以上にファンタジーの道を突き進むことになります。
「このアルバムは、トールキンのファンや、僕たちのようなファンタジーが好きな人にとって素晴らしいものになると思ったんだ」と André は回想します。「だから、自分たちのためでもあった。商業的な考えは排除したんだ。レーベルがこの作品をあまり好まないだろうことは、もうわかっていた。このアルバムには、ヒット曲やラジオのシングル曲、MTVのビデオクリップ的なものは入っていないからね。それは分かっていた。でも、”だからどうした?自分たちがやりたいことなんだから” って思っていたよ」
“Nightfall” の構成は、バンドにとって新たな挑戦となりました。”Imaginations” のように単独で成立する曲を作るのではなく、全体の物語とどのように相互作用するかを考えなければならなかったから。 André が回想します。
「Hansi は “メランコリックなものが必要だ”, “戦いが必要だ”, “あれもこれも必要だ” と言っていたよ。ファンタジー世界に深く入り込んで、トールキン的な感覚に合うようなアイデアを出そうとしたんだ。今までとは違う作業工程だったけど、とても興味深く、違う道を歩んだその時から多くのことを学んだんだろうな」
「この作品は新たな BLIND GUARDIAN のソングライティングの出発点だったのかもしれない」 と Hansi は言います。「当時はそう感じなかったけど、今思えばここがポイントだったのかもしれない。曲作り全体が常に進行しているんだ。だから、”Imaginations” から新しいものに向かって自然で有機的な進化を遂げることになったんだ」
“Nightfall” は、 André がクラシック音楽とオーケストラ・アレンジメントに興味を持ち始めたきっかけとしても重要な作品であった。このこだわりは、”Nightfall” の次の作品である2002年の “A Night at the Opera” でさらに実を結ぶことになります。「キーボードでクラシックの楽器を演奏して、それをレコーディングできるなんて、本当に驚いたよ」と André は言います。
「僕たちは、壮大でクラシック志向の曲を作り、実験していたバンドのひとつだったんだ。そして、これらのサウンドの融合は素晴らしいものだと今でも思っている。メタル・ミュージックにとてもよく合うんだ。曲のストーリーやメロディーで作り上げるエモーションは、オーケストラが入ればさらに強くすることができるんだよ」
“A Night at the Opera” で最も大胆な試みは、ホメロスの長編叙事詩 “イーリアス” を14分に渡ってシンフォニック・メタルに翻案した “And Then There Was Silence” でしょう。この曲は、オーケストラの楽器をふんだんに使い、コーラスだけが繰り返されるという、ほとんど圧倒的な音楽的アイデアの洪水を実現しています。”Opera” のレコーディングを開始する頃、2人はクラシック音楽のアルバム “Legacy of the Dark Lands” の制作を始めていました。 André は”Legacy” で採用した作曲スタイルに解放感を覚え、それをメタルの文脈で適用しようとしたのです。
「ルールはない。僕はただ音楽で物語を語りるだけ。もちろん、ドラムとギターを加えなければならなかったけど、とてもうまくいった。ヴァース/コーラス/ヴァース/コーラス/ソロ/コーラス/コーラスみたいな普通の曲の流れから抜け出したかったんだ。それに縛られたくなかったんだ。それに、ヘヴィ・メタルには物語をどこかに導いてくれる自由があると感じている。左の道を通って、またまっすぐな道に戻って、別のところに行くこともできるってね。森の中を歩いていて、木が来たらルートを変えるようなもの。ずっとまっすぐな道である必要はないんだよ」
“Opera” をリリースした後、多くのバンドがレトロなアルバムを制作した時期があったと André は嘆息します。
「彼らは80年代のような音を出そうとしたんだ。僕にとっては、それはひどいことで、そうしたアルバムはすべてひどいと感じた。後ろ向きに歩いているような気がしたんだ。彼らは80年代をもう一度再現したかったんだろうけど、何をバカなことを! 時間は一方向にしか流れていないんだ」
BLIND GUARDIAN のカタログの中で見過ごされてきた逸品、”A Twist in the Myth” がそうしたレトロに回帰するバンドに対する André の答えでした。長年のドラマー Thomas “Thomen” Stauch が脱退し Frederik Ehmke が新たに加入。その厳しい制作スタイル、短くしかし密にミックスされた楽曲、奇妙なシンセ音の多用は、そうしたレトロの風やバンド自身の “A Night at the Opera” からも可能な限り距離を置いていました。 André は、”Twist” について今でも、その最高の曲 -“This Will Never End”, “Otherland”, “Fly” は、トップレベルの BLIND GUARDIAN であると信じています。そして彼は、それらをさらに良くするために手を加え続けたいと思っています。
「今聴くと、もっとこうしたらいいのにと思うことがたくさんある。でも、当時、僕たちはこうした音楽の作り方をこのやり方しか知らなかったし、心の中ではベストだったんだ。でも、いつかこのアルバムの曲のいくつかを作り直したいと思っているんだ。素晴らしいアイデアなんだけど、曲はもっといい方法でアレンジできるし、もっとキャッチーになるはずだからね。このアルバムは、初めて聴く人にとって、とてもとても入り込みにくいものだったということが、今になってよくわかる。情報過多になってしまうし、カッコ悪い。今ならこのアルバムをどうプロデュースするかがわかるんだ」
“Twist” の成果に失望した André は、”And Then There Was Silence” の壮大でシンフォニックな実験に立ち返り、そこから前に進むためのインスピレーションを得ようとしました。そしてその頃、 “Legacy of the Dark Lands” のリリースに向けたセッションに没頭していた André は、本物の人間によるオーケストラを BLIND GUARDIAN のアルバムに使用したくてたまらなくなっていました。
「本物のオーケストラを録音して多くを学んだからこそ、壮大なものを書いてみよう、より良いものを作ろうと言って “And Then There Was Silence” をプログラミングしたからね」
プラハ交響楽団は、”A Night at the Opera” の最大級の衝動をより有機的に感じさせる “At the Edge of Time” で重要な脇役となっています。ゲームの主題歌ともなった “Sacred Worlds” と”時の車輪” がモチーフの “Wheel of Time” はアルバムの中枢として機能し、”And Then There Was Silence” の圧倒的なスケールをややコンパクトにまとめて提供しています。一方で、”Ride Into Obsession” は André の “作曲された” リードギターがメロディアスなフレーズを奏でなければスラッシュと見紛うばかりのアグレッションを纏います。結局、”At the Edge of Time” は原点回帰という名の一時後退で、 André とバンドの他のメンバーが “Twist” の “失敗” を克服するために必要なリセットであったのです。
2015年の “Beyond the Red Mirror” は、”At the Edge of Time” の自然な伴侶となるべき作品でしょう。この2枚のアルバムはほぼ同じシークエンスとペースで構成されていて、この作品では9分の “The Ninth Wave” と “Grand Parade” を、”Edge” における “Sacred Worlds” と “Wheel of Time” と同じスロットに配置しています。 André は当時、エピックモードで作業し、BLIND GUARDIAN のサウンドを盛り上げるオーケストラの使用に満足していました。
「この2枚のアルバムの間で抜本的な改革はしていないんだ。よし、”Tales” と “Somewhere” の間でやったように、さらに良い音にして、このスタイルをさらに進歩させようという感じだったね。”Beyond the Red Mirror” でピーク・ポイントを設定したかった。ソングライティングはそうできたと思うけど、プロダクションはそうじゃなかったんだ」
確かに、”Mirror” のオーケストラの要素は、”Edge” の力強さに比べて妙に弱々しく感じられ、その結果、アルバムは少しスケールダウンしています。それでも、”Prophecies” のようにいくつかの素晴らしい曲が含まれていますが、 André は “壮大なオーケストラの BLIND GUARDIAN 路線” に行き詰まりを感じていたようにも思えます。
「僕にとっては、その時、この壮大なスタイルを続ける必要はないと思ったんだ。しばらくはこれをやっていたが、今は他のことをやる時だ。もう一度激変が必要なんだとね」
その変化はすぐにやってきますが、その前に André と Hansi は20年以上も温めていた愛の結晶をリリースする必要がありました。BLIND GUARDIAN TWILIGHT ORCHESTRA とクレジットされ、エレクトリック・ギターがゼロである “Legacy of the Dark Land” は、2019年に発売されました。”Legcy” に収録されている最も古い曲は、”Nightfall” 時代までさかのぼります。
「純粋な体験について言えば、常に学び続けるプロセスだった」 と、Hansi は説明します。「音楽家としての能力はもちろん、機能的な曲作りや音楽における物理学について、膨大な知識を得ることができた。それは、実際よりも理論的にね。音楽の魂にとって、その知識は効率的なんだよ」
メタルではないアルバムをリリースし、その理由をファンに理解してもらうことができたのは BLIND GUARDIAN が数十年に渡って築き上げてきた実験の証といえるでしょう。バンドは常にAndré と Hansi の実験室であり、”Legacy” は彼らの最も壮大な実験であったと言えます。だからこそ、二人はこの作品をとても大切にしているのです。
「20年という時間の中で、このような学習プロセスがあったのだから、本当に素晴らしいことだ。こうした時間があったからこそ、このアルバムを作ることができた。何も変えたくないんだ。僕にとってあれは完璧なアルバムで、今までで最高の作品だ」
「長い間、僕らの思考を支配してきたオーケストラ・アルバムの後に、僕らが何か声明を出したかったのは確かだ」と Hansi は言います。「今、僕たちはやりたいことを何でも自由にできるようになったんだ。”The God Machine” は、解き放たれたブラインド・ガーディアンなんだ」
“解き放たれた” という言葉は、”The God Machine” にとって完璧な言葉でしょう。少なくとも “A Twist in the Myth” 以来、あるいはそれ以前から、BLIND GUARDIAN のアルバムの中で最もヘヴィな作品なのですから。このアルバムは、”Deliver Us from Evil”, “Damnation” という2曲の強烈なスピード・メタルで幕を開けます。その後に続く “Secrets of the American Gods” は7分間の音の迷宮で、”The God Machine” の中で最も叙事詩に近いもの。この曲は、Marcus のリズムギターを軸に、アレンジが螺旋状の回廊を下っていくようなうねりを伴っています。Marcus、ドラマーの Frederik Ehmke、ベーシストの Barend Courbois は André や Hansi と同様にアルバムのサウンドにとって重要な存在であることは言うまでもないでしょう。
「久々にバンドとしてリハーサルを再開したんだ。そして、”Legacy of the Dark Lands” に取り組んでいる間、ずっと見逃していたバンドのエネルギーとヘヴィネスを感じたんだ。それは僕らが再び速く、よりハードになった理由のひとつだ」
“The God Machine” はコロナ時代の BLIND GUARDIAN 最初のアルバムですが、彼らの曲は世界的な大災害よりもエルフや魔法使いについての曲の方が未だに多いのはたしかです。ただし、このアルバムは André が今の世界の “世相” と呼ぶものを捉えているようです。
「世界全体が厳しくなったように感じた。人々がお互いにどのように話しているのかがわかった。10代の頃のイライラした気持ちに近いものがあった。そして、それが “The God Machine ” の感覚だった。フラストレーションを全部吐き出して、エネルギーを全部込めたんだ。もっとスピード・メタルなんだ。もっとハードでファストな感じ。僕にとって、それは今の時代を反映しているもので、常に重要なこと。そしておそらく、僕がこの時代に抱いた感情を解消するのに役立つのであれば、それは他の人々にも役立つかもしれない」
今回、BLIND GUARDIAN の挑戦は “スピード・メタル 2022” です。
「もう2017年末のツアーの直後から曲作りを始めていたね。ただアイデアを集めて、すべてをオープンにしておいたんだ、なぜなら、最初のうちは、自分たちを特定の方向に限定したくないから、どんなアイデアがあるか見て、そこから作業するんだ。だから、最初は “American Gods” と “Architects of Doom” に取り組んでいて、その後、”Legacy of the Dark Lands” に集中しなければならない、あるいは集中したいので、曲作りは一旦中断したと思うんだ。それが終わると、オーケストラやアレンジメントと一緒に仕事をするのはとても強烈で、僕にとっては何か別のことをするのが自然だと感じたし、メタル・バンドを再び感じ、残忍さとスピードを感じることができた。だから自然に、最初の1、2曲はスピード感のある曲になった。Wacken Worldwide で演奏して “Violent Shadows” をプレイしたとき、この曲に対して素晴らしいフィードバックを受けた。そして、この直後に、いや、この直後ではなく、すでにこの前に、パンデミックがスタートしたんだ。その瞬間、僕の周りや世界が一変した。よりタフになり、ある種のサバイバルモードに切り替わったような感じ。だから僕もよりタフに、よりハードにならざるを得なかった。すべてが少し混沌としているように見え、その瞬間、よりハードで残忍な音楽を書くことが本物だと感じたんだ。だから、このアルバムは、僕らが今感じている “タイム・スピリット” 世相や瞬間を捉えたものだと思うし、それは僕らの音楽の中に常にあるもので、古いアルバムからずっと、音楽における感覚の大きな部分を占めていたんだ。
このスピード感のあるアルバムは、僕らにとっては自然なことなんだ。レトロなアルバムを作ろうとか、昔を真似しようとは思っていなかった。僕らにとってこの作品は、メタル・バンドとしてスタートしたときの純粋なに、今の知識を加え、バンドとして、作曲家として成長を加えたものなんだ。スピード・メタルを2021年、2022年の時代に移したかった。だから、よりモダンなサウンドにする必要があったし、アレンジに関しても少しトリッキーにする必要があって、それを実行した。振り返ってみて、通用しないような曲は嫌なんだ。そうだね、今回僕らの挑戦は、スピード・メタルが今どう聞こえるべきかということであり、新しい世代のメタル・ファンにとってどう興味深いものになり得るかということだと思う。もし今、16歳や20歳の若者が聴いたら、80年代のオリジナル曲よりもずっと彼らの関心を引くことができると思う」
ある意味、”The God Machine” は BLIND GUARDIAN の新章、その幕開けと言えるのかもしれません。
「どこか別の場所に行きたかった、それは確かだ。いわば、新しい BLIND GUARDIAN のサウンドを定義したかったんだ。”At the Edge of Time” と “Beyond the Red Mirror” はかなり近かったから、あれを1つの章として見ている。そのあと時折、章を閉じ、別の章を開く必要があるんだよ。今がそのタイミングだと思ったんだ。プロデューサーのチャーリーと、どうやったら新しいアルバムをまったく違うサウンドにできるかについて何度も話し合ったんだけど、結論は最初からすべてを変えること。ドラムの録り方も変えたし、ギターの音も完全に変えた。ミキシングも新しい人にやってもらったし、そういうことを全部ひっくるめて、新しい章が始まるんだということがわかるような、今までとは違う作品になったと思う。アートワークについてもね。ファンタジーであることに変わりはないけど、より現代的であることを示すようなアートワークのカットが必要だと」
ただし、BLIND GUARDIAN にとっての “現代化” とは、断捨離で、ミニマライズで、スペースを作ることでした。
「同じダイナミックさ、同じアグレッションを持ちながら、たくさんのスペースが欲しかった…今回の音楽はもっとオープンで、もっとスペースがあるんだ。80の楽器が同時にトリックを繰り広げるような超壮大なものではなく、もっと…僕は70年代のものが好きでね。DEEP PURPLE から LED ZEPPELIN まで、僕の好きなバンドの多くは70年代のロックバンドで、彼らのギターサウンドが本当に大好きなんだ。だから今の僕の基本的なサウンドは70年代のアンプをベースにしていて、それによってよりスペースができて、ある意味ボーカリストがより輝いている。
実際、”The God Machine” はかなり70年代の影響を受けている。今でもライブではこのコンセプトにこだわっていて、うまくいっている。その方がみんなにとってずっといいんだ。僕たちは、基本的なロックっぽいバンドに少し戻っているからね。例えば、ギターから見たアメリカ流のメタル・サウンド、SLIPKNOT, KORN, DISTURBED は、典型的な歪み過ぎ。僕のヒーローは Eddie Van Halen なんだけど、彼のサウンドをいつもチェックしていて、何が好きで何が嫌いなのかっていうのを考えていたんだ。たぶん、それが僕らにとっての進むべき道なんだと思うし、スピード・メタル系の音楽でも、こういうサウンドは気持ちいいと感じるんだ」
“Life Beyond the Spheres” にはたしかに、70年代の音もかなりはっきりと入っています。
「この曲は特殊な奏法で演奏されているんだけど、この奏法を実現するために何度もリハーサルを重ねたんだ。僕は音楽ジャンル全体を何か別のものに前進させる、イノベーションの大ファンなんだ。もしかしたら、今までなかった新しい何かを見つけられるかもしれない。”Life Beyond the Spheres” では、サウンドトラックの方向へ行きたいと思ったんだ。当時は “サイバーパンク 2077″ をやっていたから、ちょっとそこからインスピレーションがあった。サイバーパンクの方向性で、今までよりもスペイシーなメタル・サウンドを持ち込もうとしたんだ。その感覚を Hansi も掴んでくれて、今までやったことのない、このジャンルに近くない曲ができたと思う。いいよね、これはとても革新的な曲で、誇りに思っているよ」
多くのバンドが左に進むと、右に行くのが BLIND GUARDIAN のやり方。
「”Twist in a Myth” のように、遠くへ行ったアルバムもあるし、エレクトロニック・サウンドの実験もたくさんやった。当時はもっとシンセティックなサウンドにしたかったし、シーケンサーで遊んでみたかった。禁止されていることは何もない。自分の頭の中に素晴らしいコンセプトがあれば、何があってもそれを実現させたい。僕らにとってはただ、アルバム全体が調和していることが重要なんだ。曲作りの段階でたくさんの曲を考えたけど、その中には絶対に合わない曲もある。それを入れるのは休憩とか場違いみたいになってしまうから嫌なんだ。だから、曲順を工夫すれば、ストーリーが生まれるような曲ばかりを選んでいった。全く違う方向性の曲もあったよ。ジャズ的な要素も試したし、本当にクールなアイデアもある。ある時点で、リリースする予定だけど、すべては正しく行われなければならない。それでも、オリジナルの BLIND GUARDIAN サウンドにこだわる必要はない。僕の考えでは、BLIND GUARDIAN の本当の最初の定義となったのは “Tales of the Twilight World” だった。だから僕たちはどこへでも行けるんだ」
André は未だに長年連れ添った Hansi と意見が合わないこともあると認めています。”Blood of the Elves” はまさにそんな2人の違いとケミストリーが生んだ曲。
「キャッチーでフックなメロディーを聴く耳は、僕の方が上だと思う。Hansi はそういう意味では、もっと複雑で、プログレッシブな思考を持ちすぎている人。僕は楽器の演奏ではそうなんだけど、壮大でクラシックな曲になると複雑になりすぎてしまうのは嫌なんだ。僕は心に残るようなサビが好きなんだよ。Hansi はこれを壊したがっていたんだけど、僕は絶対にダメだと言ったんだ。彼にとっては、歌詞のセンスを入れることがとても重要なんだよね…全体がコーラス部分に収まる必要があるんだよ。でも僕はリズムもメロディも完璧なんだから、そのままでいいじゃないかと。だから、たまにはそういうこともあるけど、たいていの場合は同意する。僕たちはそんなに離れているわけでもないし、2つの世界が衝突するようなことはない。
結局、BLIND GUARDIAN の成功は、僕と Hansi のケミストリーのおかげだから。それは、愛憎半ばするケミストリー。僕たちは、本当に何でも話し合えるコミュニケーション方法を持っているから。たとえ意見が合わないときでも、すべてを持ち寄る。でも、最終的には一歩引いて、 “やっぱり、君が正しかった” と言えるんだ。それができるのが大事なんだよ。Hansi が思い通りになることもあれば、僕が思い通りになることもあり、時には妥協点を見出すこともできる。でも、僕は妥協があまり好きじゃなくて、妥協すると何かを失うと思ってしまう。だから、100%彼のやり方で行くか、100%僕のやり方で行くか、その方がいいんだ。何かに合意したら、何かを決めたらそれを100%追求する。それが僕らのいいところで、例えば Hansi が何かに反対していたとして、じゃあ君のやり方でやろうと言った瞬間から、そのアイディアに100%賛成することになるし、その反対もある。それが結果的にいい音楽につながっている」
ただ、歌詞のアイデアは、この曲での “Witcher” のように “オタク” である彼と Marcus が Hansi に押し付けることもあります。ただし、正解を出すのはいつも Hansi です。
「Hansi は歌詞について素晴らしい才能を持っているよ。だから彼に任せるよ。彼はボーカリストだから、正しい言葉に対する正しい感覚を持っているし、サビの部分の言葉ひとつで大きく変わるからね。もし、シンガーが嫌がる言葉を入れたら、曲が台無しになることもある。だから、最終的にボーカリストが気に入ったものを演奏することが本当に大事だと思う。Hansi の歌詞は、行間を読ませるような書き方をしていて、大好きだ。彼はいつも、解釈のためのスペースをたくさん残しているんだ。彼がヒントを与えることで、人々は何が起こっているのか、どういう意味なのかを考え始め、より深く、より深く掘り下げていくことができる。そうすることで、BLIND GUARDIAN の音楽は最終的にもっと強烈なものになるんだ。時には、歌詞がきっかけで本を見つけて、本を読んでくれるなんてこともあるくらいでね。
曲作りの時に彼はダミーの歌詞を使うから、時々議論が起こる。そのダミーの歌詞の中で、彼はとても良さそうな言葉を選んでいて、でも最終的に彼はその素敵な言葉を交換しようとするから、いつもまた喧嘩になる。ただ、Hansi は本当にセンスがよくて、曲のフィーリングや音楽に合うトピックを見抜く力があるんだよね。逆に、僕が音楽を作るとき、例えば “Destiny” は、僕が大のRPG好きで、あれは僕にとって、”World of Warcraft” という氷の世界の何かを題材にしたゲームにインスパイアされたものなんだ。そのことを彼に話し、僕のイメージするリッチキングのことを話した。すると彼は、”僕はそのストーリーに興味がないから、これについては書かないけど、同じ感情をキャッチできるようなものを考えてみるよ” と言ったんだ。彼はそれが本当に上手だから、心配する必要はないし、干渉する必要もないんだよね」
パンデミックで文化としての音楽、文化としてのメタルも危機に瀕しました。
「若い人がいきなり2年間も趣味を追求できなくなる。いきなり家に閉じこもってしまう。もちろん、フラストレーションは溜まる。僕が思うに、一番の捌け口は “音楽” だよ。音楽は良い治療法だ。ハードなバンドをいくつか聴いて、それを捌け口にするんだ。若い世代の人たちは昔よりオープンだからね。そんな若いファンにとって、スピード・メタルに親しむことは間違いなく面白いことだと思うんだ。”The God Machine” はスピード・メタルだけど、ただ、非常にモダンなスピード・メタルだから埃をかぶってはいない。そうやってスピード・メタルのエッセンス、エネルギーを今の時代に伝え、若い世代の足元に投げかけて、”ここにいい音楽があるよ” と言うことが大切だと思うんだ。パンデミックで、音楽シーンは社会の中で何のステータスもなく、真っ先にキャンセルされ、サポートされないことが明らかになった。この生じた穴を再び埋めることができればと願っているよ。多くのオーガナイザーやバンドが潰れてしまわないように。文化は重要だし、音楽は政治家が考えている以上に重要だよ。音楽という文化がこのまま、2023年以降も、僕たちが築き上げることのできる確かなものであってほしいと願っているんだ」
参考文献: TUONELA MAG:Interview with Blind Guardian — “We wanted to define a new Blind Guardian sound.”
BANDCAMP :An Introduction to Blind Guardian’s Mighty Power Metal