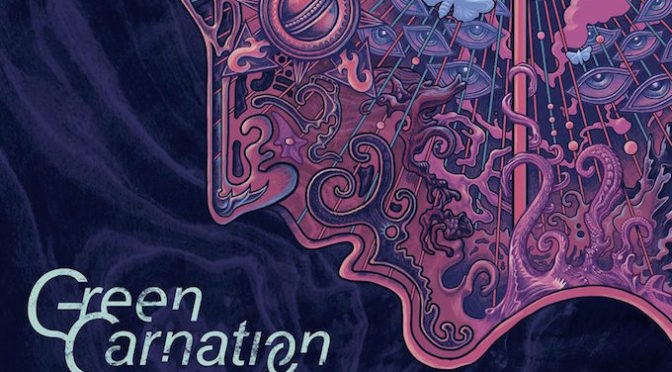EXCLUSIVE: INTERVIEW WITH ANDY LAROCQUE OF KING DIAMOND !!
“I Think The Difference Between King Diamond And Mercyful Fate Is, Mercyful Fate Gotta Little More Maybe 70’s, Roots In It’s Music Style. In My Opinion, While Kind Diamond Has Always Been Little More Murderer.”
MASQUERADE OF MADNESS
GHOST が存在する遥か以前から KING DIAMOND の劇場的オカルトはメタル世界を侵食していました。コペンハーゲン郊外に生を受けた Kim Bendix Petersen は、サタニックメタルの始祖 MERCYFUL FATE で King Diamond への羽化を完全に果たします。
MERCYFUL FATE が80年代初期に残した二枚のアルバム “Melissa”, “Don’t Break the Oath” は実際、メタルの歴史を変えました。コープスペイントで頭蓋骨を仰ぎ、足の骨でマイクスタンドを拵える真性の異端児。地獄の底から絞り出すような唸り声から、悪魔が囁くファルセットまで、奇々怪界を紡ぐため死の世界から舞い戻った幽鬼。そんな King のオカルティックな詩篇とシアトリカルな美学は METALLICA, SLAYER から後の北欧ブラックメタルシーンにも多大な影響を及ぼしたのです。
では、King の特徴的なファルセットやシアトリカルな仮装はどこから来ているのでしょうか?
「あのファルセットは、BLACK ROSE 時代にファンからもっとファルセットを使えと言われたのが始まりなんだ。おかげで歌唱のテクニックや空気のコントロールなど多くのアイデアを得ることができたんだ。シアトリカルな仮装は Peter Gabriel と Alice Cooper だね。GENESIS のライブを見て、音楽に合わせた “演劇” の重要性を悟ったんだ。」
象徴的な “Melissa” の頭蓋骨はどこで手に入れたのでしょう?
「兄から貰ったんだ。マイクスタンドにしていたクロスボーンもね。彼の友人の父が医者をしていて、提供された死体を使って学生に授業をしていたんだ。授業が終わると、皮膚を剥ぎ取って骨を樽に入れていた。それで手に入れることができたんだ。だけど彼女はショウで盗まれてしまったんだよ。」
METALLICA との邂逅は印象的でした。
「84年に MOTORHEAD が USツアーに連れていってくれたんだ。その時誰かが METALLICA を教えてくれたんだけど、ドラマーがデンマーク人だという。よくよく調べると Lars の父親は有名なテニスプレイヤーだったんだ。だからアンコールでステージに上げたんだよ。そうして、”Ride the Lightning” をコペンハーゲンで録音することになったのさ。あの時彼らが泊まっていた私のアパートはお化け屋敷だったんだけど (笑)」
MERCYFUL FATE が “音楽的方向性の違い” により分裂した後、Kind は自らの名を冠した新たな魑魅魍魎 KING DIAMOND を結成し、これまで以上にエピカルでシアトリカルな道を辿ります。1987年にリリースした “Abigail”は、霊と家族の暗い秘密をコンセプトに認めて今でもメタルのオールタイムクラッシックとして名を馳せ続けています。
「ファーストアルバム “Fatal Portrait” には、MERCYFUL FATE のために書かれた楽曲もあったけど、5曲のミニストーリーも存在したんだ。それがとてもしっくりきて、ホラーコンセプトアルバムを作りたいと思ったわけだよ。音楽もそれに伴い進化して、より演劇的になっていったね。BLACK SABBATH はたしかにダークサイドを音にし掘り下げていたけど、私たちはフェンスの向こう側に立って別の視点から見ていたんだよ。」
長年の相棒、ギタリストの Andy LaRocque は弊誌独占インタビューで MERCYFUL FATE と KING DIAMOND の違いについてこう語ります。
「MERCYFUL FATE はより70年代的で、ルーツを探るような音楽スタイルだよ。一方で、KING DIAMOND は僕の考えではいつだってより猟奇的なんだ。」
後のブラックメタルサークルが起こした一連の事件に対して King はどのような感情を抱いていたのでしょうか?
「ちょっと大げさだったよね。だって暴力や放火に関わっていたのはほんの一部でしょ。ほとんどのバンドは関わっていなかった。もちろん、殺人や暴力を肯定しているわけじゃないよ。私は蜘蛛も殺せないんだ。捕まえて逃すだけさ。」
以後、King は時に復活した MERCYFUL FATE と二足のわらじを履きながらその怪奇譚、悪夢の物語を綴り続けました。創作が暗礁に乗り上げたのは、2010年。心臓発作に苛まれた King は、3度の心臓バイパス手術を受け、死の淵を彷徨います。回復の過程で、長く音源のリリースから遠ざかりましたが遂に今年、KING DIAMOND として完璧な新曲 “Masquerade of Madness” を発表。MERCYFUL FATE も再度の復活を宣言し、古の悪魔の不死を証明しています。
「あれ以来、タバコも一本も吸っていない。健康的な食事と運動も欠かさないよ。全てが良い方向に向かっている。2度目のチャンスを得たんだからね。」
間違いなく復活のマスカレード “Masquerade of Madness” には失った時を取り戻す魔法がかけられています。Andy はこう力強く語りました。
「80年代の僕たちと “Masquerade of Madness” にはたしかに多くの共通点があるね。
実は、僕たちはファーストアルバムを振り返って、最初の最初に実際何をやっていたのかチェックしてみたんだ。この曲のライティングやレコーディングを行なっている時、これはあの曲のあの部分ぽくしようなんて思ったわけじゃないんだけど、それでもあの振り返りのおかげで間違いなくこの曲にはオールドアルバムのヴァイブがあるよね。」
NIGHTMARE
2014年、KING DIAMOND のキャリアを総括するコンピレーションとしてリリースされた “Dreams of Horror”。そのタイトルはまさにバンドと King の全てを体現していました。
デンマークから現れた怪異は、黒のトップハットにコープスペイントを施し、悲鳴のようなファルセットで瞬く間にメタル世界の台風の目へと躍り出ました。その KING DIAMOND が抱える不気味と不吉の元凶は、King が長い間悩まされてきた夜の恐怖に端を発しているのです。
「散々悪夢を見てきたよ。目が覚めたら誰かを殺してしまったと思うこともあった。それから15分くらい、どうやってその殺人を隠蔽しようか考えていたりね。」
とはいえ、King Diamond ほどの知名度で捜査の手から逃れることは難しいでしょう。オカルトメタルのパイオニア MERCYFUL FATE のフロントマンにして、Church of Satan のメンバー、”Abigail” や “Them” といったコンセプチュアルホラーの創立者は、メタル史において最も認知されている “声” の1人に違いありませんから。
事実、METALLICA の秀逸なカバーは語るまでもありませんし、Phil Anselmo からの敬愛、さらに Kerry King は SLAYER の “Hell Awaits” が MERCYFUL FATE の子供であることを認めています。
King を突き動かすのは彼の鮮明な悪夢。「目が覚めた時はホッとしていることが多いね。人が死ぬ、ペットが死ぬ、奇妙なことが起こる、車が粉砕されたり、争いに巻き込まれたり。大抵は非現実的な夢だよ。飛び立ったあと急に落下して、地面に墜落する直前に目が覚めたりね。起きた時に叫んだり、汗びっしょりだったりするよ。片腕は痺れていて、今のは何だったんだ?って思うんだ。」
それでも、自らの地獄のような夢の世界を探求することは、King にとって生涯の使命であり、創造性の源とも言えます。
「悪夢を見るとその原因を考える。時には同じシナリオの悪夢を連続してみることもあるよ。それで本当にその悪夢が現実になるんじゃないかとか思ったりしてね。眠りに落ちて、また同じ夢に吸い込まれ、あんな悲しい思いはしたくないって思うよ。だけどたまには、あの場所に戻って解決できるかみてみたいと思うこともあるんだ。」
昨年、およそ20年ぶりの再結集を発表した MERCYFUL FATE。バンドの金字塔である1984年の “Don’t Break The Oath” に収録された “Nightmare” も King の悪夢に根ざしていました。
「子供のころの夢さ。兄が隣のベッドで寝ていてね。そしたらフードを着た男が突然部屋に入ってきて、オマエの運命は尽きかけている!と私を指さすんだ。私は恐ろしくて兄を起こそうと叫ぶんだけど、声は出なかった。」
King は現在、2007年 “Give Me Your Soul…Please” 以来となる新作の制作に熱を上げています。2010年、生死の境を彷徨った心臓のバイパス手術から蘇る不死の王。
「とても特別な方法で書かれたアルバムになるよ。1枚で全てを語ることはできないから、2枚組になるだろうな。これまでで最悪の悪夢だよ。あの心臓手術から目覚めて、私は窒息しそうな気がしてパニックになった。口から人工呼吸器のチューブを抜こうとしたんだよ。妻リヴィアがすぐに走ってきて、ようやく私は医師たちが命を助けようとしていると悟ったんだけど、ベットに縛り付けられていた。まるで METALLICA の “One” の世界観だよ。」
故に、人工呼吸器の音を新譜のイントロやライブのエフェクトに使用しても不思議ではありません。
「地獄がどんなものかはわからないけど、あのゆっくりとしかし確実にいつも首を絞められているような感覚よりはマシだろうな。私はあの人工呼吸器の音を聞くだけで悪夢を見てしまうだろうな。」
ただし、そのライブに纏わる悪夢も King を悩ませてきました。
「私はショウの前に衣装やメイクで長い時間が必要なんだが、目覚ましが鳴らなくてスッピンで出る羽目になるってシナリオもあったな。ギタリストの Andy が普通のロックンロールをプレイし始めて、シアトリカルなメタルを期待しているファンから物を投げられたりする悪夢もあったよ。私はステージ裏に身を潜めていたが、コープスペイントの女性に見つかりマイクスタンドで応戦したりね。フルメイクで逃げ惑って一線を超えたファンを振り払いながらバスに乗り込んだんだ。」
定期的に見るのは戦争の夢。1987年に亡くなった父が、第二次世界大戦中、デンマークのレジスタンスに参加していた時の話を King はよく聞かされていました。
「ナチスに追われる夢を見るんだ。ドイツ軍に占領されていた5年間、ここでも多くの粛正が行われた。父は連合軍のコペンハーゲン奪還を手伝ったんだよ。子供のころは、父に誰かを殺したことがある?ってよく尋ねていた。彼は決して答えなかったけどね。」
夢が現実になることもあります。20年以上前に King は “From the Other Side” という楽曲を仕上げ、”The Spider’s Lullabye” のオープニングに収録しました。
「あの曲を聴くとまるで手術台の上にいるような気分になる。そして突然体から離脱して、自分のために戦っている医師たちを天井から見下ろすんだ。自分はセカンドチャンスを得られるのか、得られないのか。後に心臓の手術を受けた時、下を見下ろすと悪魔が魂を奪い去ろうとしていた。だから悪魔と戦わなければならなかったのさ。最初は夢だったんだが、私は後にそのシナリオを経験したのさ。」
いつか正夢になって欲しい夢もあるのでしょうか?
「宝くじに当たるとか?時々はそんな夢も見るよ(笑)」
参考文献: REVOLVER:KING DIAMOND: THE DARK VISION, BAD DREAMS AND NEAR-DEATH OF AN OCCULT-METAL ICON
KERRANG!: KING DIAMOND: “IF THERE IS A HELL AND I GO THERE WHO CARES? I’VE ALREADY FACED IT”
続きを読む COVER STORY + INTERVIEW 【KING DIAMOND : MASQUERADE OF MADNESS】