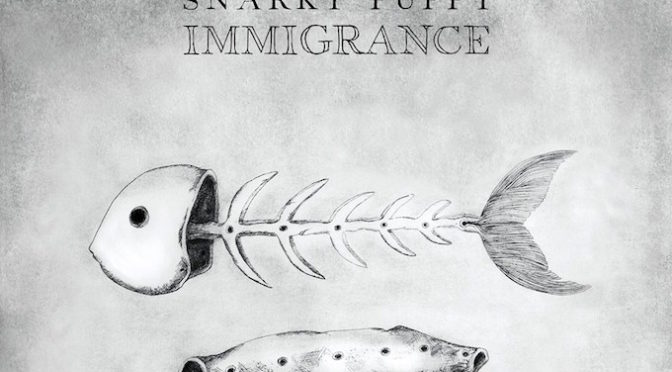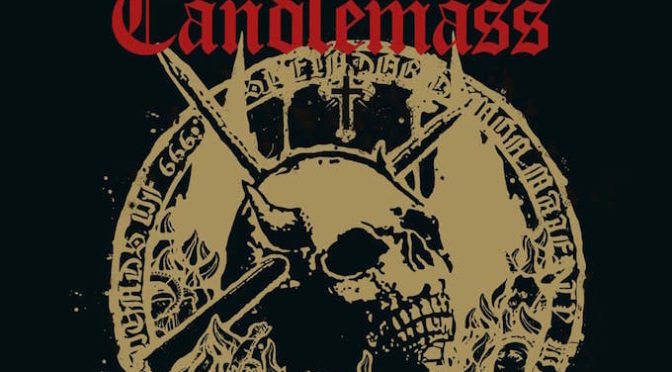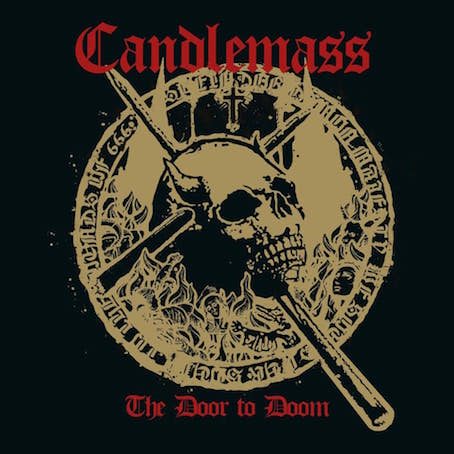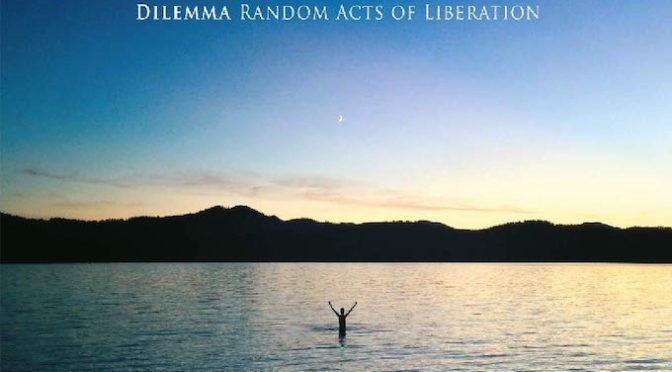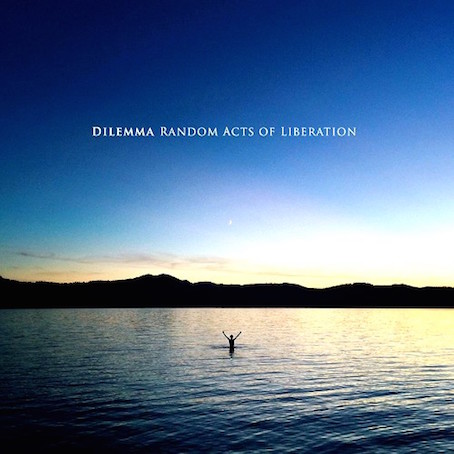EXCLUSIVE: INTERVIEW WITH MICHAEL LEAGUE OF SNARKY PUPPY !!
“Traveling So Much Really Reminds You How We Are All Immigrants In a Certain Kind Of Way, Whether It’s About Our History, Our Ancestry, Or The Customs And Cultural Elements We’ve Borrowed From Other Parts Of The World.”
DISC REVIEW “IMMIGRANCE”
「一つのジャンルに向けてのみ演奏をしたくないんだ。全てのジャンルのオーディエンスに訴求したいよ。だから本当に様々な音楽ジャンルのファンが僕たちの音楽を楽しんでくれているという事実は、進化を続け異なる方向を打ち出す僕たちを強く勇気づけてくれるんだ。」
耽溺のジャジストはもちろん、THE MAHAVISHNU ORCHESTRA, RETURN TO FOREVER を崇拝するフュージョンマニアックス、SLAYER, Biggie, さらにはフォークミュージックの粋人まで、多種多様な音の眷属が集結する SNARKY PUPPY のライブはさながら “Immigrance” のサウンドキャラバンです。
「世界中で僕たちのオーディエンスの中に多様性を見つけることは実に美しいね。こうやって僕らのように旅を重ねていると、自分たち全員がある種の “移民” であることを思い起こすんだよ。」
グラミー賞を3度獲得したグルーヴオーケストラ SNARKY PUPPY。その多様でボーダレスな “移民” の創造性は、ベーシストでマスターマインド Michael League の数奇なる旅路に起因しています。
ハイスクール時代、ギタープレイヤーとして LED ZEPPELIN, CREAM, PEARL JAM, SOUNDGARDEN のカバーに勤しみグルーヴの鼓動を刻んだ Michael は、STEELY DAN の “Alive in America” によってロックとファンク、そしてジャズの悪魔合体に開眼することとなりました。
ノーステキサス大学でベースに持ち替えジャズを学びつつ SNARKY PUPPY を結成した Michael は、Erykah Badu に見出されヒップホップ、R&B、さらにはゴスペルをも咀嚼し、遂にはその興味の矛先を世界の伝統音楽にまで向けながら、その全てを自らのグルーヴコレクティブへと注ぎ込んでいるのです。
グラミーを獲得した前作 “Culcha Vulcha” で頂点に達したポリリズムとエスニックの複雑な探求。”Immigrance” では Michael が鼓動のベースとするロックとファンクにも再び焦点を当てて、流動する “移民” の羈旅をよりエクレクティックに噛み砕いて体現することとなりました。
例えばオープナー “Chonks” ではシンプルなヘヴィーグルーヴをベースに圧倒的なアンサンブルでファンカデリックな空間を演出し、よりメカニカルな “Bad Kids to the Back” では TRIBAL TECH にも似た骨太なジャズロックのインテンスを見せつけます。
そうして、全面参加を果たした2人のギターマエストロ Bob Lanzetti, Chris McQueen が一層輝きを増しながら、ジャズ領域の外側へと大胆な移住を促進したのは David Crosby との出会いも大きく作用したはずです。事実、Michael は自身が歌ってギターも奏でるソロ作品のリリースを予定しているのですから。
「確かに “Immigrance” ではいくつかの異なる伝統音楽から影響を受けているね。そうして時を経るごとに、その影響はレコード毎に大きくなっていっているよ。」
一方で、モロッコのグナワを基盤としたエスノビートとポリリズムが鮮やかに溶け合う “Xavi’ では SNARKY PUPPY の先鋭性を遺憾無く味わうことが出来るでしょう。西アフリカのトライバルミュージックとブルースを融合させた BOKANTE の立ち上げが示すように Michael の特に中東~アフリカ地域に対する音の探究心は並々ならぬものがありますね。
3人のドラマーと3人のパーカッション奏者を抱える SNARKY PUPPY にとって根幹はやはりグルーヴです。そして、”Even Us” にも言えますが、日本人パーカッショニスト 小川慶太氏の美技を伴ったトライバルビートは、SNARKY PUPPY が有する移民の多様性と華麗に調和しながら瑞々しいジャンルのポリフォニーを実現していきます。
“Immigrance” に伴うワールドツアーはここ日本から始まります。作品の多くがライブレコーディングである SNARKY PUPPY にとって当然ライブこそが本領発揮の場です。ただし、”Immigrance” はスタジオで録音されたレコード。故に、バンド本来の躍動感に、思索や計画性が伴って実に奥深い多次元のリスニング体験をもたらすこととなりました。
今回弊誌では、Michael League に2度目のインタビューを行うことが出来ました。「歴史がどうであれ、祖先がどうであれ、習慣や文化がどうであれ、僕たちは世界のほかの場所から何かしらを “借りて” 生きているんだからね。」鍵盤奏者 Bill Laurance が奏でる虹の音色にも注目。どうぞ!!
SNARKY PUPPY “IMMIGRANCE” : 10/10
続きを読む NEW DISC REVIEW + INTERVIEW 【SNARKY PUPPY : IMMIGRANCE】JAPAN TOUR 2019 SPECIAL !!