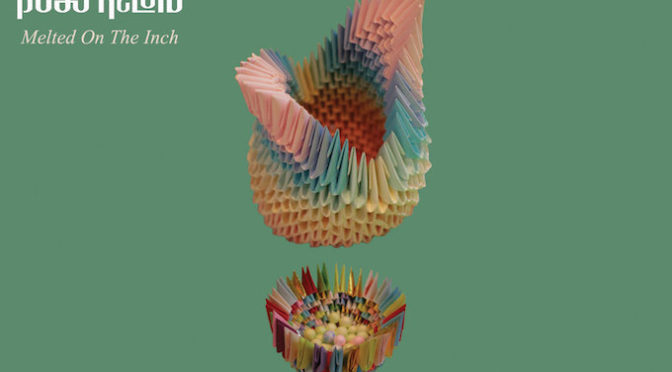EXCLUSIVE: INTERVIEW WITH JOE VAN HOUTEN OF JOURNAL !!
“I Have Always Been Fascinated By Emotional And Memorable Music That I Would Hear In Certain Video Games – Particularly JRPGs Like Final Fantasy And Chrono Trigger, As Well As High-Fantasy Action Adventure Games Like The Legend of Zelda Series.”
DISC REVIEW “CHRYSALIS ORDALIAS”
サクラメントに居を置く JOURNAL が “Unlorja” で2010年に奏でたテクニックとカオスのエクストリームな二重奏は、ゲーム音楽のエピカルな薫りも纏いながらプログメタル/マスコアの “日誌” に確かな足跡を刻みました。
8年の後、遂に帰還を遂げた JOURNAL が掲げたのは、幼少期から馴れ親しみ愛し続ける “JRPG” 日本のロールプレイングゲームを彷彿とさせる世界観の更なる拡大でした。
「僕のフェイバリットコンポーザーは、ファイナルファンタジーの植松伸夫さんとゼルダの近藤浩治さんなんだ。疑いようもなく、僕が聴いて来たどのメタルバンドよりも強く影響を受けているね。」ゲームの話となると明らかに饒舌さを増すコンポーザー Joe。彼のゲームに対する強い愛情は、そのまま JRPG とそのサウンドトラックのスペクタクル、壮大な世界観、ストーリー展開の妙、そして溢れる感情を最新作 “Chrysalis Ordalias” へと投影することになりました。
もちろん、そこには Joe が養ってきた THE DILLINGER ESCAPE PLAN, TRAINING FOR UTOPIA, CANDIRIA, PROTEST THE HERO, CAR BOMB といったカオティックなメタル/ハードコアの素養が基盤して存在しています。さらに160ページに渡るストーリーを反映する歌詞の深みは COHEED AND CAMBRIA 譲りでしょうか。
そうして、Joe が言うところの 「複雑なタイムシグニチャーと突拍子もないテンポをユニークにブレンドし、同時に様々な感情や景色を運ぶ作曲の妙を得ることが出来たんだ。僕たちの音楽を RPG のボス戦みたいだって言う人もいるくらいでね!」 という独創性極まるユニークブレンドのコンセプトアルバムは完成を見たのです。
JOURNAL の音楽に一際個性を生んでいるのが、ファストで難解なチップチューンサウンドの楽器による完全再現でしょう。確かに8bitサウンドをメタルワールドへと取り込んだバンドは少なからず存在していますが、人の手で半ば強引に勇敢に導入する JOURNAL の姿はまさに開拓者。
実際 Joe も、「8-bit のビデオゲームサウンドを取り入れているバンドも素晴らしいんだけど、僕は人が楽器をプレイしたサウンドの方が好きなんだ。」 と語っていますし、その試みがより生々しいサウンドスケープと、複雑でアグレッシブな迫真のインテンスを共存させているのは明らかです。
事実、”Calamity Smile” はバンドのエクストリームな実験が未曾有のダイナミズムを創造するマイルストーン。FFシリーズのバトルを想起させるスリリングな音符の連鎖、リズムの荒波を、全て演奏で具現化する狂気のハイテクニックは圧倒的な混沌と緊迫感を放ち、一方で中盤のファンキーなパートではチョコボに乗って旅をしているかのような優しい錯覚を抱かせます。
もしかすると、SikTh がゲーム音楽を制作すれば同様の景色に到達するのかもしれませんね。音の先にイメージが宿る無上のサウンドスケープ。
さらに、Joe 自身、ex-CONDUCTING FROM THE GRAVE の Drew Winter 等4人を起用したマルチボーカルシステムも完璧に機能しています。ロールプレイングゲームのキャラクターのように生き生きと適材適所で語りかける彼らの声はグロウル、スクリーム、クリーンに分厚いハーモニーまで自由自在。
特にゼルダのカラフルで牧歌的世界観が表出するタイトルトラック “Chrysalis Ordalias” では、ワイドなボーカルレンジが鮮やかに楽曲の多様性、コントラストを引き立てていますね。
ゲームとエクストリームミュージックの魅力が収束した日誌の1ページ。今回弊誌では、ギタリスト、コンポーザー、そしてボーカルも務める Joe Van Houten にインタビューを行うことが出来ました。
「例えば “FF10” の悲哀極まるシーンで、実に悲しいピアノの調べが流れ出すようにね。そうして僕たちは、ティーダとユウナがいつか結ばれることをただひたすらに願うんだ!大好きなストーリーだよ。」 どうぞ!!
JOURNAL “CHRYSALIS ORDALIAS” : 9.9/10
続きを読む NEW DISC REVIEW + INTERVIEW 【JOURNAL : CHRYSALIS ORDALIAS】