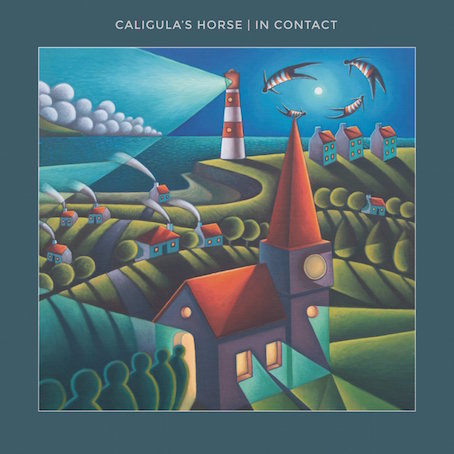EXCLUSIVE: INTERVIEW WITH TSUKSA & KAPO FROM SWARRRM !!
After More Than 20 years Activity, Japanese Grindcore Titan Swarrrm Breaks The Genres And Hardcore Rules With Their Newest Record “Beginning to break” !!
DISC REVIEW “こわれはじめる – Beginning to break”
“Chaos & Grind” を御旗に掲げる気概と熱情のグラインドコア烈士 SWARRRM が、激しさに豊かな感情を宿す愛と破壊の狼煙 “こわれはじめる” をリリースします!!スタンダードなハードコア的ルールに別れを告げ、アレンジや表現の幅を止めどなく拡大した作品は、ジャンルの垣根を意に介さない強靭で普遍的な魅力に満ちています。
「ハードコアルール的なものにはもうあまり興味ありません。それよりも刺激を欲しています。」 とインタビューで KAPO 氏が語るように、”こわれはじめる” は怒りや絶望、憤りといったオールドスクールなハードコアに根差すネガティブなアティテュードや類型的なスタイルが文字通り壊れ始めるレコードだと言えるのかも知れません。
刺激という意味では、例えば CONVERGE が新作でその多様なサウンドデザインによって語らずしてハードコア本来の刺激を更新したように、混沌の先を見据え変化を渇望する SWARRRM が保守的な地下室から這い出し少なからず陽の光を欲することは必然にも思えます。
アルバムオープナー “ここは悩む場所じゃない” は変化の象徴。「前作 ”FLOWER” 収録の ”幸あれ” ”あがれ” といった曲に可能性を感じていたのは間違いない」 「より普遍的なロックテイストに辿り着くべくして辿り着いた」と KAPO 氏が語る通り、この楽曲が指し示すレコードのイメージはキャッチーで歌心を携えた前代未聞の歌謡グラインド。伝説 HELLCHILD 時代から、原川 司氏がこれほど “歌った” ことは勿論ないでしょう。
司氏が発する歌心、エモーションが、J-Pop ではなく70年代の歌謡曲を想起させる事実は重要です。ここに存在するのはロマンではなく浪漫、ラブではなく愛、儚さと寂寞そして感謝。
大人になれば世界のほとんどが綺麗事や純愛ではなく、どこか歪な愛や歪んだ感情で成り立っていることに気づきます。それでも今がある奇跡。モダンなポップスが纏う煌びやかな飾りを寄せ付けない、司氏の貫く “歌” は日本的な侘び寂びを孕んでどこまでも正直です。
そうした司氏の新境地とバンドのルーツが見事に融解した楽曲こそ “愛のうた” であり、”絆” であると感じます。「あなたの思うグラインドコアと、私たちのグラインドコアは違うという事でしょうか。」 と KAPO 氏が語るように、ブラストのアレンジメントにこそグラインドの美学を貫く SWARRRM。
美しさと儚さはメロディーに、混沌と破綻はブラストへと帰依し、そこから生まれるボーカルと演奏の鬩ぎ合い、美醜のコントラストは唯一無二の尊き激音を創出するのです。楽曲の前半と後半でガラリと情景が変化し衝撃をもたらす詩の魔法も見事。
そうして辿り着く “血が叫ぶ” は、実際ブラストが装飾程度にしか使用されない異端の極地。ファンキーなカッティングが映えるポップとも形容可能な楽曲にはノイズが大胆に散りばめられています。
インタビューにもあるように、勿論偶然で意図も離れていますが、とは言えエクストリーム最前線の ENDON, FULL OF HELL, THE BODY との偶発的シンクロニシティーはシーンの向かう先を朧気に映し出しているようにも思えますね。
そうしてアルバムは、幕開けと同様にアコースティックの静謐な音色でその幕を閉じるのです。
今回弊誌では、司氏と KAPO 氏にインタビューを行う事が出来ました。「激しい音楽に長く触れてこられた方にこそ聞いていただきたいです。何か感じていただけるのではと思います。」 変わらないことへの恐怖と、変わることへの恐怖。SWARRRM です。どうぞ!!
SWARRRM “こわれはじめる – Beginning to break” : 9.9/10
続きを読む NEW DISC REVIEW + INTERVIEW 【SWARRRM : こわれはじめる – Beginning to break】