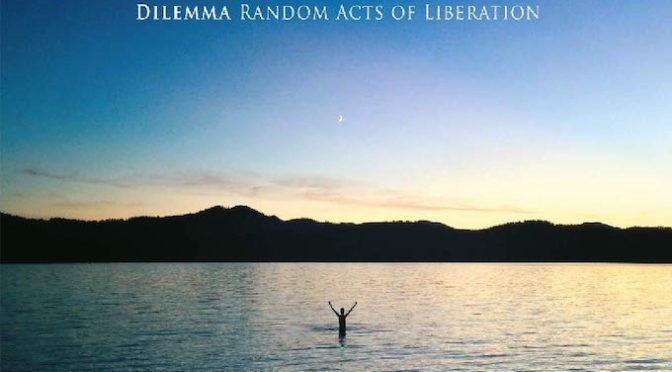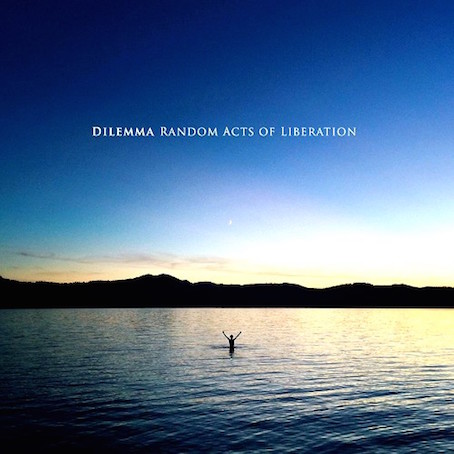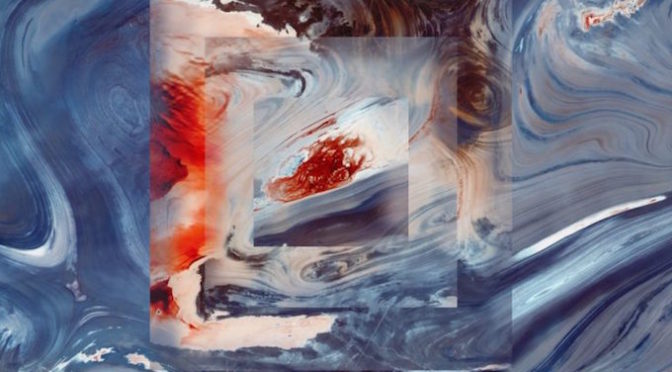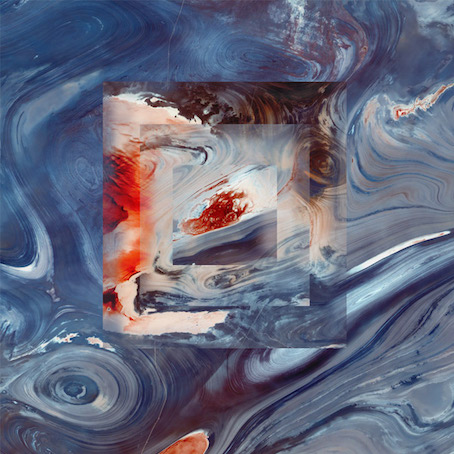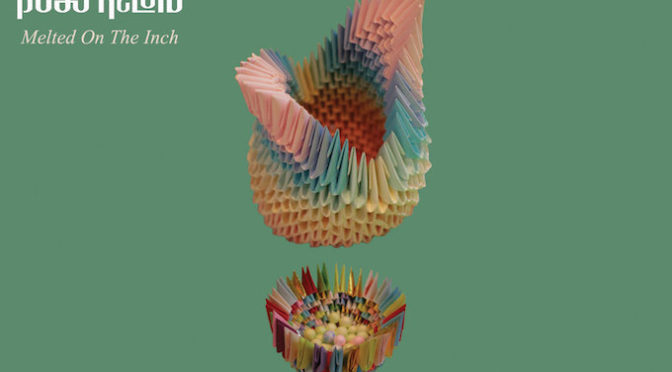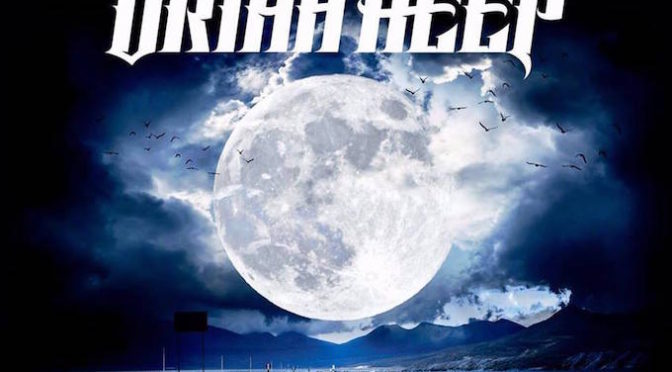EXCLUSIVE: INTERVIEW WITH COLLIN LEIJENAAR OF DILEMMA !!
“I Believe That Prog Music Should Not Only Be Clever And Virtuoso, But Also Moves Your Emotions And Your Heart. And It Should Surprise You, Taking You On a Musical Journey.”
DISC REVIEW “RANDOM ACTS OF LIBERATION”
「オランダ人はいつも交易と開拓を掲げてきたよ。この精神は、音楽にも反映されているんだ。なにせオランダのプログシーンは小さいから、成功を収めたいなら手を広げなければならないんだ。だからこそ、オランダのプログロックバンドはよく世界的な注目を集めるんだろうね。」
オランダに根づく交易と開拓の精神は、文化、芸術の歩みをも伴うこととなりました。そしてそのスピリットは、”交易” と “開拓” を音で体現するプログレッシブロックの海原と無謬にシンクロしているのです。
FOCUS, EARTH & FIRE, TRACE, KAYAK, AYREON, TEXTURES, VUUR。潮風の交差点で脈々と重なるダッチプログの渦潮は、DILEMMA を呑み込み、23年の長い間仄暗き水の底へと沈めました。しかし、90年代に素晴らしき “Imbroccata” でプログシーンに深々と爪痕を残した船乗りたちは甦り、遅れて来た大航海時代 “Random Acts Of Liberation” で文字通り自由を謳歌するのです。
ただし、乗組員は船長の鍵盤奏者 Robin Z を除いて大きく変化を遂げています。特筆すべきは、Neal Morse, KAYAK との仕事でも知られる百戦錬磨のドラマー Collin Leijenaar と、ex-FROST*, DARWIN’S RADIO の Dec Bruke を加えたことでしょう。オランダでプログ雑誌のライターも務める Collin の理想と、FROST* の血脈に繋がる Dec の個性は、バンドを一際カラフルでアクセシブルなプログレッシブポップの海域へと誘うこととなりました。
「プログロックはただクレバーでバーチュオーソ的だけであるべきではないと信じているんだ。同時に感情や心を動かすべきだってね。そうしてそこには驚きや音楽的な旅への誘いがあるべきだってね。人は心の底から音楽と繋がる必要があるんだよ。」
実際、Collin のこの言葉は、”Random Acts Of Liberation” が強固に裏付けています。
DREAM THEATER の “Pull Me Under” を彷彿とさせる緊張感とキャッチーなメロディーラインのコントラストが鮮やかなオープナー “The Space Between The Waves” が、より”自由”なプログロックの風波としてアルバムの趨勢を占えば、14曲72分の DILEMMA シアターの幕開けです。
“Amsterdam (This City)” を聴けば、一番の理解者 Mike Portnoy が 「SPOCK’S BEARED, FROST*, FLYING COLORS, HAKEN, Steven Wilson と並ぶとても味わい深いモダンプログ」 と DILEMMA を評した理由が伝わるはずです。デジタルサウンドとストリングスを効果的に抱擁する多様で甘やかなホームタウンのサウンドスケープは、Steven Wilson や FROST* が提示するプログレッシブポップのイメージと確かにシンクロしているのです。
“Aether” では PINK FLOYD と、”All That Matters” では ELO とのチャネリングでさらにプログポップの海域を探求したバンドは、しかし12分のエピック “The Inner Darkness” でスリリング&メタリックなルーツを再び提示し対比の魔術で魅了します。
“Spiral Ⅱ” からのシアトリカルに、コンセプチュアルに畳み掛ける大円団は、まさに Neal Morse と Mike Portnoy の申し子を証明する津波。中でも、”Intervals”, “Play With Sand” の激しく胸を打つ叙情、音景、エモーションはあまりに尊く、リスナーの心を “音楽” へと繋げるはずです。
今回弊誌では、Collin Leijenaar にインタビューを行うことが出来ました。時にトライバル、時にジャズ、時に Portnoy の影響を組み込んだドラミングの妙は、アルバムのデザインを華麗に彩ります。「このアルバムでは、プログロックをよりオープンで直接的な表現とすることに成功したと思うよ。プログをプログたらしめている興味深い要素を失うことなく、ポップな感覚を加えているね。」 どうぞ!!
DILEMMA “RANDOM ACTS OF LIBERATION” : 9.9/10
続きを読む NEW DISC REVIEW + INTERVIEW 【DILEMMA : RANDOM ACTS OF LIBERATION】