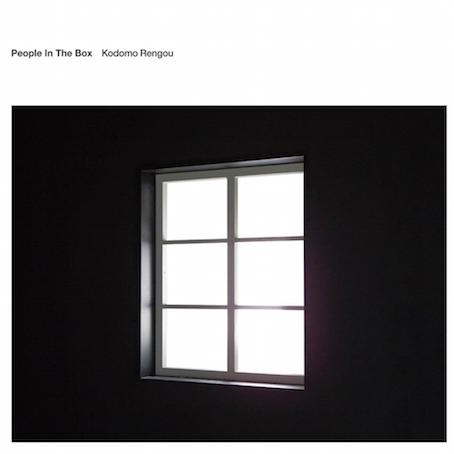EXCLUSIVE: INTERVIEW WITH JONAS REINGOLD OF THE SEA WITHIN !!
New Art Rock Collective, The Sea Within Goes To Fantastic Maiden Voyage, With Flexible And Diverse Debut Record “The Sea Within” !!
DISC REVIEW “THE SEA WITHIN”
キャプテン Roine Stolt のプログレッシブな航海はスーパーグループ THE SEA WITHIN と共に新たなアドベンチャーを創成します。荒波や暴風にも屈しない最上級の乗組員を揃えたフラッグシップは、フレキシブルな風を受け未踏の音景へと舵を切るのです。
実際、伝説のプログ船長 Roine のもとへと集結したのはマスタークラスの名だたる船乗りばかり。THE FLOWER KINGS で補佐官を務めるシーンきってのベースヒーロー Jonas Reingold。その TFK にもかつて在籍したプログメタルの至宝、PAIN OF SALVATION のマスターマインド Daniel Gildenlöw。RENAISSANCE, YES の寵児、キーボーディスト Tom Brislin。さらに Steven Wilson, THE ARISTOCRATS などで知られるトップドラマー Marco Minnemann を招聘したキャプテンは、盤石の布陣にもかかわらずゲストのスカウトにも余念がありませんでした。
Jonas のインタビューにもある通り、 レコーディングのみの参加となる Daniel の影武者には FLYING COLORS の Casey McPherson を配置。加えて YES の Jon Anderson、DREAM THEATER の Jordan Rudess、Steve Hackett Band の Rob Townsend までをも乗船させた まさに “All-Aboard” なラインナップは、出航と同時に世界中のプログファンからヨーソローな期待と注目を集めたのです。
ボーナストラックまで含めると77分にも及ぶ長駆の処女航海 “The Sea Within” はそしてその遥かなる熱量に充分応えた雄飛なる冒険となりました。一つキーワードとして挙げるべきは “フレキシブル” というアイデアなのかも知れませんね。
事実、この豪華な母船の船員に選ばれたのは全てがユーティリティーなプレイヤーだったのですから。「このバンドのメンバーは全員が歌えるし、複数の楽器をこなすことが出来るんだ。」インタビューで語ってくれた通り、ボーカル、ギター、キーボードをこなす船長 Roine を筆頭にフレキシブルな才能を誇るバンドの航路は、全員がコンポーザーという奇跡まで備えながら鮮やかな多様性に満ちています。中でもドラマー Marco Minnemann のパーカッションはもちろん、ギター、ボーカルまでこなすマルチな才能はこの偉大な航海の大きな推進力となっていますね。
THE FLOWER KINGS とは異なる進路を目指すというキャプテン Stolt の野望は、オープナー “Ashes of Dawn” を聴けば伝わるでしょう。アルバムで最もダーク&ヘヴィー、Roine と Daniel の歌声導く苦悩とアグレッションが印象的な楽曲は、世界経済のカオスをテーマに据えています。
故に、Roine と Jonas が TFK のファンタジックな殻を破り、深海のアビスをリアルに映し出すかのようなサウンドを選択したことも驚きではないでしょう。KING CRIMSON の “Red” にもシンクロするこのインテリジェントな音の幽暗は、Tom のサクスフォンを得てより深部までその混沌を浸透させるのです。
その Tom がイニシアチブを取った物憂げでコーラスも鮮やかなクラッシックアート “They Know My Name”、KARMAKANIC を想起させる Jonas の幻想的でシネマティックな作曲術が Daniel の PAIN OF SALVATION とは一味違うオーガニックな声色を引き出した “The Void”。そして辿り着く “An Eye for an Eye for an Eye” はアルバムのハイライトと言えるかも知れませんね。
ラインナップの中で最もロッカーの佇まいを備えた Marco が作曲を手がけたことにも頷ける、ファストでアグレッシブな楽曲は THIN LIZZY とプログがモダンな風を受けてハイブリッドを果たしたようなユニークでしかしフックに満ちたキラーチューン。潮目の変化はフォービートとジャズロックの海風を運び華麗なソロワークが美しく華を添える中、楽曲は再びメロディックなブリッジへと回帰しロックのエナジーを胸いっぱいに吸い込みながら大円団を迎えるのです。
そうしてその多様性の濁流は、5人の主要メンバーが共作した “Goodbye” へと流れ込んでいきます。そこはポップとエモーションが乱れ咲く桃源郷。アルバムには確かにキャッチーという名の子午線が貫かれていますが、7/8拍子のファンキーなリズムを起点に光の放射を放つ素晴らしくリリカルな楽曲は飛び抜けてプログポップの期待感に満ち溢れているのです。
Jon Anderson も参加してオールスターキャストで贈る14分のプログ劇場 “Broken Cord”。キャプテン Stolt は “Sgt. Pepper” から YES までプログロックのイデアを体現したエピックを THE FLOWER KINGS のファンへとしっかり捧げてその旅路を終えるのです。
今回弊誌では、ベースヒーロー Jonas Reingold にインタビューを行うことが出来ました。プログ、ポップ、ジャズ、アートロック、クラッシックロック、そしてシネマティックな離島を繋ぐフレキシブルで魅惑的な航海。エースを揃えた SONS OF APOLLO が正統的なスーパーグループなら、ユーティリティーの極み THE SEA WITHIN もまた異なるスーパーグループのあり方でしょう。どうぞ!!
THE SEA WITHIN “THE SEA WITHIN” : 9.8/10
続きを読む NEW DISC REVIEW + INTERVIEW 【THE SEA WITHIN : THE SEA WITHIN】