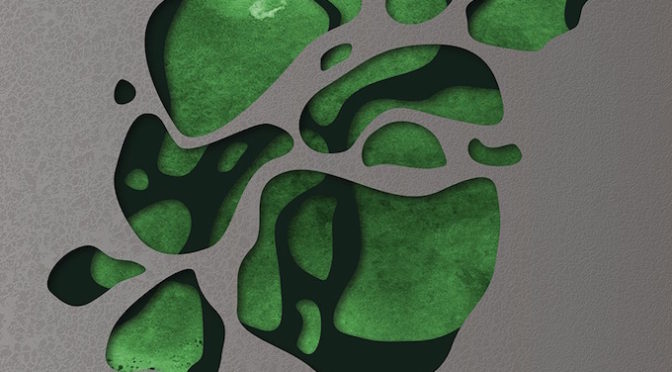EXCLUSIVE: INTERVIEW WITH BASTIAN THUSGAARD OF SOILWORK !!
“What Can Be Tricky At Soilwork Shows Is That The Majority Of The Songs Are In a Decent Mid-Tempo And Then The Few Fast Songs Are Like Super Fast. It Happens That We Play 5-6 Songs In a Row That Are Very Easy Tempo-wise And Then One Super Fast Song After. It Feels Like Going From 0-100 In a Second And Sometimes That Can Be Tough.”
DISC REVIEW “VERKLIGHETEN”
昨年デビュー20周年を迎えたスウェーデンの巨人 SOILWORK は、絶対の信頼が置けるバンドです。
その真価は、幾度ものメンバーチェンジを乗り越える約20年間で11枚というその旺盛な制作意欲はもちろん、衝動と叙情の “Steelbath Suicide” から、Rob Halford をしてメタルの未来と言わしめた “A Predator’s Portrait”、洗練極まる “Stabbing the Drama”、そして2枚組のエピック “The Living Infinite” まで、エクストリームな精神とメロディーを常に共存させながら、リスナーの好奇心を刺激するフックと新機軸を織り込み続けている点にあります。冒険と安定感の絶妙なバランスとも言えるでしょうか。
3年半振りに届けられた最新作は、スウェーデン語で “現実” を意味する “Verkligheten” をタイトルに冠していました。スウェーデン遠郊のメランコリー、彼の地の悲哀を帯びた旋律は、苦悩に満ちた日常からの逃避を誘います。もしかすると、長年大黒柱として存在した名手 Dirk Verbeuren を MEGADETH に引き抜かれたトラウマも、バンドが現実からの逃避を題材とした理由の一つだったのかも知れませんね。
ただし SOILWORK は新たなドラムマイスター Bastian Thusgaard と共に再び歩み始めます。ダークで思慮深く、リピートを促すレコードにおいて、高揚感を伴う煌めきのメロディーが運ぶ絶佳のコントラストこそ作品の妙。その風情は、ロマンチシズムと言い換えても良いでしょう。さらに Bastian は、そのロマンを現実逃避に対するセラピーとまで表現し、バンドの新たな旅路を飾るポジティブな意思表明へと繋げているのです。
「”The Living Infinite” というダブルアルバムを書くことで、SOILWORK は遂に自分らしい場所を見つけたと思うんだ。」 そう Bastian が語るように、音楽的には確かにあの壮大なエピックこそがバンドにとっての転換点でした。
実際、Bjorn “Speed” Strid も最新のインタビューで、”The Living Infinite” こそが SOILWORK にとって新たな時代の幕開けだったと認めています。同時に、”Verkligheten” ではそのドラマ性に、クラッシックなメタルや80年代の雰囲気をより多分に封入したことも。
インタビューで Bastian も認めているように、Bjorn & David が牽引するノスタルジックな別バンド THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA の活発化が SOILWORK の方向性に影響を与えたことは確かです。
そしてこのノスタルジー溢れるロマンチックなセラピーに最も貢献したのは Bjorn の驚異的にワイドなボーカルレンジでしょう。”Full Moon Shoals” “Witan” で爽快壮美なハーモニーを披露する一方で、”When The Universe Spoke” では研ぎ澄まされたスクリームを投げかけます。過去のどの作品より自然に、シームレスに繋がる適材適所な歌唱の美学は、そうして AMORPHIS の Tomi Joutsen をフィーチャーした “Needles and Kin” のメタル劇場へと完璧に結実していくのです。
もちろん、David Andersson と Sylvain Coudret のギターチームもさらに充実を遂げています。もはや定型化したメロデススタイルを封印し、スウェーデンのメランコリーを封じた創造的なパッセージと、”The Nurturing Glance” が象徴するデュエルのスリルでカタルシスを喚起していきます。
そうして、スーパーファストなブラストビートから、トライバルなリズムまで変幻自在な新加入 Bastian のスティックワークを最後のピースとして、プログレッシブとさえ言える夢幻のメタルワールドは完成を迎えたのです。あの YES を彷彿とさせるアートワークも偶然ではないでしょう。
今回弊誌では、新加入 Bastian Thusgaard に自己紹介も兼ねたインタビューを行うことが出来ました。日本の THOUSAND EYES にも共鳴するような、より広義の血湧き肉躍る浪漫メタルレコード。「いくつかの楽曲はメタルらしい音数の多さから離れて、よりアクセシブルに仕上がったね。僕の考えでは良いことだと思うよ。」どうぞ!!
SOILWORK “VERKLIGHETEN” : 10/10
続きを読む NEW DISC REVIEW + INTERVIEW 【SOILWORK : VERKLIGHETEN】JAPAN TOUR 2019 SPECIAL !!