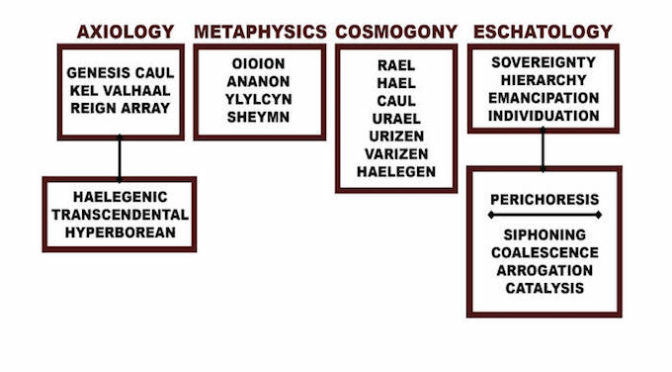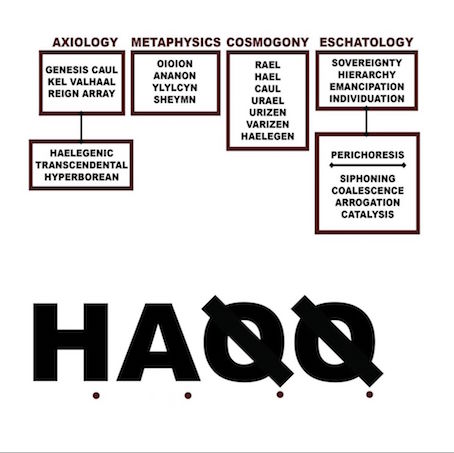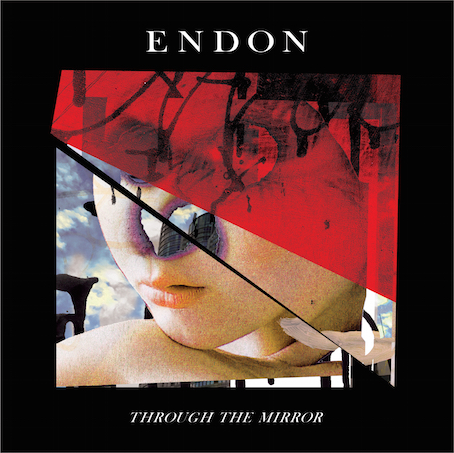COVER STORY : GHOSTEMANE “ANTI-ICON”
“Is There a Lack Of Danger In Modern Rock, Compared To Rap? Sometimes. But The Feeling Of Inauthenticity Is More About The Lack of Intent.”
ANTI-ICON
GHOSTEMANE の這い出る混沌、”Anti-Icon” は彼の人生において最も激動の時の産物です。それは歪んだビジョンによる究極のカタルシス。
“トラップメタル” の先駆者、多作の Eric Whitney は8枚のスタジオアルバム、10枚の EP、さらに4つの異なるペルソナのもと無数のコラボレーションまでを踏破し、ヒップホップ、ブラックメタル、ハードコア、ノイズに跨り新種のエクストリームミュージック傾倒者の想像力をかき立ててきました。古代から伝わる神秘主義、オカルトのイメージを織り込みながら。
遺体安置所での乱行パーティー、砂漠で燃やす霊柩車のプロローグを経て、”Anti-Icon” は10/21にリリースされました。淡い肌、黒い口紅に乳白色のコンタクトレンズ。さながら吸血鬼か死体のような彼の写真は、GHOSTEMANE のサウンドと美学の進化を象徴していました。
「Soundcloud にいたラッパーたちはストリートウェアに夢中だった。Supreme のような憧れのブランドは、信頼性の証でもあったんだ。だけど僕にとってそれは、皮肉で偽善的なものだったんだよ。だってそれを持っていないとからかわれるんだからね。僕にロゴはつけないよ。他の誰にも似せたくないから。」
それがアルバムタイトル “Anti-Icon” の源流なのでしょうか?
「アイコンというのは、インターネット時代を象徴する言葉の一つだと感じている。僕にとってアイコンとは、アリス・クーパーやマリリン・マンソンのような人のことだよ。10マイル離れていても誰だかわかる。外見も、声も、アクションフィギュアだって作ることができるほどに特徴的なんだ。でも最近じゃ、YouTuber や TikToker、ネット上のパーソナリティーにレッテルを貼るため。それがアイコンだとしたら、少なくとも僕がなりたいものじゃないね。」
ゴーストの物語は、フロリダ州レイクワースから始まりました。パームビーチから南に8マイル、サンシャインステートの郊外に広がる小さな町。ただし、Eric の記憶は父親の影によって暗く沈んでいます。
Eric が生まれる直前、ニューヨークからこの地に転勤した血液技師の父親は、Eric が4歳の時に交通事故で負傷し、それ以来ソファーと杖に拘束されていました。そうしておそらくはその苦境、その結果としてのオピオイド依存症が父親による Eric への支配を引き起こしたのです。Eric はその “暴君のような、ヘリコプターのような親” の複雑な記憶を歌詞の中で 「巨大な手を持った大きな怖い男たちが、僕の胸に指を突っ込み、何をすべきか命令した」と鮮明に振り返ります。
町の下層中流階級で育った Eric の青春は目立たないものでした。アメフトの男らしさも、オシャレへの努力も、行動的になることも、喉の奥で抑圧されていたからです。
「僕はとても内向的だった。友達も全然いなかったしね。学校じゃ、クールなブランドなんて身につけない子供さ。自分以外の何かになりたい、学校以外の何かをやりたい、ここ以外のどこかに行きたい、彼ら以外の誰かといたい、そんな圧倒的な衝動に駆られた10代だったな。いつも本当の自分との折り合いをつけようとしてるんだ。」
17歳の時に父親を亡くしたことが、Eric の感情的地滑りの引き金となりました。「ソーダのボトルを振ってキャップを開けたようなものさ。」
高校卒業後についた営業職で高額な年俸を得ていた Eric ですが、結局、閉所恐怖症のオフィスは彼が夢見ていた人生ではありませんでした。最初の逃避先はハードコアパンクでした。
「NEMESIS でギターを弾き、スラッジメタル SEVEN SERPENT ではドラムを叩いた。それで楽器のマルチな技術と友情が培われたんだ。今でも僕のキャリアには欠かせないものだ。家のようなものだったんだ。」
スピリチュアリティと仏教も Eric の閉ざした心を開かせました。ハーメティシズムと20世紀初頭の書物キバリオンの発見が彼を突き動かしたのです。
「それは宗教だけど、本当に科学に基づいている。僕にとって宇宙物理学は究極のスピリチュアリティなんだ。何より、僕たちが宇宙の中心じゃなく、もっと大きな存在の証を証明してくれるからね。僕にとって、別の領域への逃避でもあったんだよ。間違いなく今、世界は燃えている。ただ、世界には3つのタイプの人がいてね。僕は世界を売った人でも、世界を燃やした人でもない、ただそれを報告するためにここにいるだけなんだ。」
父親からもらった Dr.Dre の傑作 “The Chronic” を除いて、Eric のヒップホップな要素はこの時点まで皆無でした。しかし、NEMESIS のフロントマン Sam のレコードコレクションがその領域への道を開いたのです。DE LA SOUL, OUTKAST, HIEROGLYPHICS のようなアーティストの軽妙な創造性はまず Eric を魅了しました。それからメンフィスの大御所 THREE 6 MAFIA, マイアミの RAIDER KLAN のダークなライムを発見し、遂に Eric はヒップホップと真に心を通わせます。
「夢中になったよ。理解するべきは、僕が感じる闇や重苦しさは必ずしもヘヴィネスやラウドネスと同義ではないってことだった。それはね、ムードなんだよ。」
たしかに、メタルやハードコアは Eric の渇望するエネルギーとカタルシスを提供していましたが、無限の創造的可能性をもたらしていたのはラップだったのです。
「バンドだと他のメンバーと衝突しながら、自分のアイデアを伝えなきゃならない。ラップだとすべてが自分のアイデアなんだ。自分のやることは自分のやりたいこと。僕は完全にコントロールできるようになった。ただ、ラップ、メタル、インダストリアル、テクノ、アンビエント、アコースティック。それが今までに僕が持っていた全ての音とアイデアだ。胸の奥底にあるオカルト的なディストピアの悪夢を、血まみれになって届けるためのね。僕は何もためらっていない。ジャンルは絵の具のようなものだと思っていて、異なる考えや感情を表現するために異なる色相を使っている。だから、何かを感じたら、それに従う。その感情に合った音を見つけて、たとえそれが不完全なものであっても、たとえそれが “悪い” 音であったとしても、たとえそれに耐えられなくても、自分の外に押し出していくんだ。それが自分の真実に響くものであれば-自分の気持ちに響くものであれば-それはレコードに収録される。それだけさ。」
2014年に GHOSTEMANE が誕生し、カリフォルニアのより寛容なシーンを求めて移住したことが真のターニングポイントとなりました。
「”Ghostmane” ってトラックは音楽的な化学実験だった。これが本当の自分の姿だと気づいたんだ。」
インダストリアルな暗闇とメタリックなエッジ、それに NINE INCH NAILS の不気味さはもちろん当初から明らかに存在していました。ただし、”Anti-Icon” には新たな地平へ向かいつつ自らの精神を掘り下げる、縦と横同時進行のベクトルにおける深遠な変貌が見て取れます。2年というこれまでにない長い制作期間はその証明でもありました。
「多くのことを経験してきたよ。人生で最も変革的な時期だった。僕は自分の中にあるクソを全部取り出して作品に投影したんだ。みんな僕を羨んでいるけど、正直正気を保って自分が何者か忘れないようにすることに苦労してるから。」
“Anti-Icon” へのヒントは Eric の多種多様なサイドプロジェクトにありました。
“アンチ・ミュージック” と呼ばれるノイズプロジェクト GASM は、拷問のような不安感に苛まれていましたし、SWEARR の叩きつけるようなエレクトロは束縛なき陶酔感の中で脈動していました。BAADER-MEINHOF の生々しいブラックメタルは刃をつきつけ、GHOSTEMANE ブランドでリリースした 2019年ハードコアEP “Fear Network” は闘争、そのダークなアコースティックカウンターパート “Opium” は絶対的な虚無感を捉えており、そのすべては “Anti-Icon” への布石とも取れるのですから。
もちろん、2020年において “Anti-Icon” というタイトルはそのまま、”AI” というワードに直結します。人工知能。近未来のディストピア的イメージは、心を開いた Eric と親の威圧感からくる強迫観念、妄想被害の狭間で揺れ動いているのです。
「オピオイドなんて自分には関係ないと思ってた。中毒者のものだってね。だけど困難な時を経験した人なら誰だってそうなり得るんだ。僕はハイになったとさえ感じなくなった。気分が悪くならないように、ただそのために必要だったんだ。」
偽りの愛を繰り返し嘆く “Fed Up”, 「I DON’T LOVE YOU ANYMORE!」のマントラを打ち鳴らす “Hydrochloride”。疑心暗鬼は怒りに変わり、中毒で盲目となった Eric にとってこれはオピオイドへの別れの手紙でもあるのです。どん底へと落ちた Eric を引き止めたのは、まず父親と同様の行動を取った自身への嫌悪感だったのです。つまり、Eric は大の NIN ファンでありながら、ダウンワードのスパイラルではなく、ダウンワードからの帰還を作品へと刻んだと言えるでしょう。古い自分を終わらせ、新たな自分を生み出す。MVで示した燃える霊柩車は過去の灰。”N/O/I/S/E” からの解放。
「不死鳥は灰の中から蘇るだろ?古い自分を壊し、殺し、そこから新たな人間になるんだよ。」
前作はただ痛みと苦悩を記し続けた作品だったのかも知れません。
「”N/O/I/S/E”をレコーディングした時、僕は自由で真実味のある音楽を作りたかった。言葉は不器用で解釈を誤ることがあって、芸術の無形の資質を損なうものだと思っているからね。僕は自分の脳と骨の中を深く掘り下げて、これまで感じてきたあらゆる苦悩や、自分を含め多くの人に襲いかかるあらゆる惨劇を扱ったアルバムを作ったんだ。”N/O/I/S/E” は独自の言語であり、痛みと哀れみの出血する舌であり、恐怖の遠吠えであり、光や地上の音をすべて見失うほど深いところにある。世界が内側から自分自身を引き裂く音だった。」
毒を持って毒を制す。Eric の闇に光をもたらしたのは、奇しくも彼と同様ジャンルを渡り歩く賛否両論の “アイコン” Poppy でした。レディング&リーズのフェスで出会った二人は、7月に婚約を発表し、お揃いの漆黒に髪を染めた Poppy は “Lazaretto” の MV まで監修しています。
「彼女は素晴らしいよ。ビジュアルアーティストとして、彼女は他の追従を許さない。それは僕のキャリアの中で、自分自身を十分発揮できていなかった分野の一つだからね。だから彼女に自分の一部を託すのは、奇妙だけど楽しみなアイデアだよね。」
エクストリームミュージックの未来を担う新種として、そのパワー、可能性、そして自らの責任についてはどう考えているのでしょうか?
「ラップにくらべてロックが危険じゃない?時にはね。けど本物じゃない感じはたしかにあるよね。意図が失われたよ。メインストリームでモダンロックは大きく後退している。本当に悲しい曲や怒っている曲はもうラジオじゃ流れていないんだ。壊れた、失われた、悲しい、怒っている、病んでいる、実在の人々と実際につながるための意図がもっとあるべきだと思うんだ。僕にとっては、それが昔との最大の違いなんだ。」
とはいえ、ラップが GHOSTEMANE にとって根幹であることに変わりはありません。高音の叫び声から喉を掻き毟る嗚咽に密やかな囁きのが交互に繰り返されるさまは、さながら体に複数の悪魔が閉じ込められているよう。その悪魔はそうしてリアルを失ったロック世界を侵食していきます。
“Lazaretto” のクイックなリズムとダウンチューンギターの組み合わせには Nu-metal の亡霊が宿り、一方で”Sacrilege” ではハードコア、圧迫的なエレクトロニクス、そして幽玄なムードがダイナミックにブレンドされていて、現代のメタルアイコン CODE ORANGE とのシンクロニシティーを窺わせます。そして、”ASMR (Anti-Social Masochistic Rage) “の突き刺すようなビートは、Eric のアイコン、マリリン・マンソンと同様のダーティーな秘め事を思い起こさせるのです。
Eric にとってこうした多様で変幻自在な音の葉は、やはり暗闇への下降より自らの成長を象徴しています。”Anti-Icon” で最も荒涼とした瞬間 “Melanchoholic” でさえ希望のノートで締めくくられるように。
「僕の中にあったクソみたいなものを全部取り込んで、それを外に投影しているような感じ。今はとても気分がいい。自分の中に溜め込まずにね。」
エリックはどんな種類の伝道活動も嫌いで、「キリスト教と同じくらいラヴェイ派サタニズムを嫌っている」と宣言していますが、それは TikTok などで何が一番ポップになるかを気にするのではなく、他のアーティストが限界に挑戦するように願う気持ちにも通じます。
AUTHOR & PUNISHER, FULL OF HELL, 3TEETH。彼が真の同種と考えるアーティストは、箱の外に踏み出したパフォーマーなのですから。ボストンの VEIN もそのうちの一つ。
「彼らは実験を始めて、自分たちのシーンの人々がどう背を向けるかを経験しているんだ。僕もそれがどんなものか知っている。だから彼らが実験やり続けていること、常に努力していることは、僕にとっては驚くべきことなんだ。」
GHOSTEMANE の目的もより鮮明となりました。
「君が本当に自由であれば、作りたいものを作り、やりたいことをやり、自分の心を語り、制限なく生きることができる。だけど自分自身を傷つけてはならないよ。それがこのプロジェクトの目的だ。GHOSTEMANE は自由な精神を投影したものだから。
僕は自分とそして君たちのために音楽を作り続けるつもりだよ。別の生き方を探している人たちのために、道を切り開いていくんだ。僕は好きな時に好きなように動き、好きなものを作る。選択と独立性は僕たちが受け取った最もユニークな贈り物でだから。それは君だけがコントロールできるもの。痛みや苦悩を通してさえもね。君に治療法を与えることはできないし、どう生きるべきかを伝えることもできないけど、アイデアを与えることはできるから。僕見たこの世界を反映して、君が自由で真の人生への道を辿ることを願っているよ。僕は自分の音楽に種を蒔いてきたからね。解読するのには何年もかかるかもしれない。だけどそれが自由の仕事であり、独立の重荷だ。」
望むのは永遠不滅の音の遺産。
「自分を超えて生きているものを作りたい。この世で何が起こるかは、僕にとってそれほど重要なことじゃない。その先の世代に何が起こるのか、僕が死んだ後に何が起こるのか。全てが塵となり、荒廃した地球上に轟く風が、堕落した都市の記憶を蹴散らした時、僕は自分の音楽のかすかな叫び声を無限に響かせたい。」
最終的には、彼の最優先事項は常にファンでした。「批評家のことなど気にするな、彼らは本当に理解していないんだ。批評家のことなど気にするな、彼らは本当に理解していないんだ」と、熱を帯びて繰り返すリードシングル “AI” が宣言しているように。
「孤独や喪失感を感じたことのある人、この世界には何も残っていないと感じている人、何も持っていないと感じている人のための音楽さ。ただ音だけが聞こえるようになるまで、レコードを大音量で聴いて、落ち込んだことを忘れてほしい。ショーに来て、自分のことを知ってほしいんだ。」
300ドルの Supreme のパーカーを欲しがった15歳の若者は、結局自分で作った服が “ハイアートでプライスレス” あることに気づきました。鬱、中毒、自滅のサイクルから逃れるための教訓は結局のところ希望なのです。
「”Anti-Icon” は暗くて憂鬱で虚無的に聞こえるけど、実はとても希望的なものなんだ。人は常に変化し拡大し続けるものだから。かつての自分がが死ぬわけじゃない。君を押しつぶしているように感じるような人生だって、君がより良い何かとして自分自身を再創造するための新しい材料を作り出しているんだよ。超新星が爆発すると、新しい星が生まれる。エネルギーは永遠に続くんだ。」
参考文献:KERRANG! :How Ghostemane is changing the fabric of heavy music
REVOLVER:GHOSTEMANE: THROUGH THE FRAME