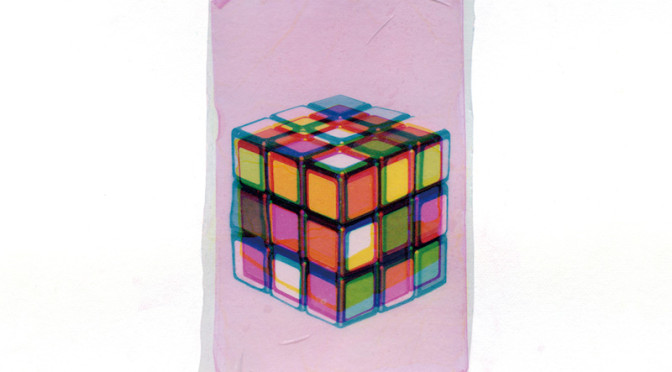EXCLUSIVE: INTERVIEW WITH NOBUYUKI TAKEDA OF LITE !!
Japanese Math / Post Rock Hero Returns! Lite Goes Back To Their Roots And Opens Up A New Chapter With Accessible And Emotive Record “Cubic” !!
DISC REVIEW “CUBIC”
日本が生んだ Math-Rock / Post-Rock ヒーロー LITE が待望の新作 “Cubic” をリリースしました!!バンドの原点である、タイトで躍動感溢れる生の音像へと回帰した作品は、国内外でインストゥルメンタルミュージックを志すアーティストへの新たな道標となるでしょう。
LITE の近作はその理知的な一面が作風を支配していました。ジグソーパズルのピースを一つ一つ組み合わせるように綿密に、デリケートに構成された彼らのストラテジーは “For All the Innocence” で一つの完成形を提示したと言えます。シンセサイザーを多用し、ギターを何本も重ね、精巧でカラフルな絵画のようにレイヤーされた音世界は、極限までこだわり抜いた足し算の美学であったとも言えるでしょう。
“For All the Innocence” の流れを汲みつつ、やや人間味も戻ってきた前作 “Installation” リリース後、LITE は国内、海外でツアーを重ねます。インタビューにもあるように、そこで彼らはオーディエンスとの温度差に直面したのです。もっとダイレクトに伝わる方法を模索し、たどり着いた一つの結論が “原点回帰” でした。
3年半のインターバルを経て、リスナーの元へと届けられた最新作 “Cubic” にはそうした葛藤を乗り越え、さらにステージアップを果たした魅力的な LITE の現在が詰まっています。
アルバムオープナー “Else” を聴けばバンドの進化が伝わるでしょう。アグレッションと躍動感を前面に押し出し、生々しくフィジカルな感覚を宿す楽曲は、ストレートにロックの真価を表現し、引き算の美学を提示しています。有機物のように形を変えていくトラックには、ワウを使用したヘンドリックスを想起させる激しい熱量のギターソロすらハマっていますね。
勿論、リズムやリフにはマスマティカルなイデオロギーが貫かれていますが、オーガニックで力強いギターサウンドと、抜けの良いダイナミックなドラムスによって、リスナーはまるで4人のメンバーのみが目前に現れ生のライブを見ているかのような錯覚に陥ることでしょう。
アーテュキレーション、ゴーストノート、そしてギターのピッキング音までクリアに感じられる立体感。あの BATTLES を手がける Keith Souza をマスタリングで、THE MARS VOLTA との仕事で知られる Heba Kadry をミキシングで起用したことも、新たなサウンドに寄与していることは明らかですね。
ジャケットのルービックキューブとリンクするように、カラフルでチャレンジングな点も “Cubic” の特徴です。SOIL&”PIMP”SESSIONS のタブゾンビがトランペットで参加した “D” はアルバムを象徴する楽曲かも知れません。自由な雰囲気でジャムセッションからそのまま進化した楽曲は、良い意味でのルーズさ、即興の魅力、ロックの原衝動を合わせ持ち、クリエイティブなエナジーが溢れて出ています。後半の転調を繰り返すアイデアも実にスリリングですね。
以前にも挑戦したとは言え、インストゥルメンタルバンドとして知られる LITE が2曲にボーカルを導入したこともサプライズだと言えますね。アヴァンギャルドなアルバムクローサー “Zero” での根本潤氏の歌唱はエキセントリックで実に効果的ですし、何よりギタリスト武田氏自らが日本語で歌う “Warp” からは、海外で認められる LITE がクールな日本語の美しさ、リズムを伝えるという意味からも重要な1曲だと感じます。
実際、フロム JAPAN のアイデンティティーは、LITE を海外のバンドから際立たせている隠し味では無いでしょうか?”Square” が象徴するような、エモとはまた違った日本的な侘び寂び、哀愁はレコードの要所で現れ作品をさらに魅力的に彩っていますね。
今回弊誌では、バンドのギタリストでコンポーザー、武田信幸さんにインタビューを行うことが出来ました。海外では、toe や ENEMIES も所属する要注目の Topshelf Records からのリリース。どうぞ!!
LITE “CUBIC” : 9.8/10
【INTERVIEW WITH NOBUYUKI TAKEDA】
Q1: 10月に行われた “SPECTRUM Vol.8” は TTNG, Mylets, Skillkills と素晴らしいラインナップが揃った魅力的なイベントでしたね。勿論、TTNGとはUSでも共にツアーを行うほどの間柄ですが、まずは今回この3組をブッキングした理由を教えていただけますか?
【TAKEDA】: TTNGとは今まで渋谷で彼らのライブに参加したり、イギリスのアークタンジェントというフェスでも一緒だったし、8月のアメリカツアーに誘ってくれたり、と実は国境を超えて色々なところで対バンをしています。
同じ世代がボーダー気にせずに切磋琢磨し合える環境はいいなと思っていました。そのボーダーレス感を特に感じるのがイギリスのアークタンジェントでした。各国からポストロックという名の下で集まり、狭いジャンル故に集まれば初めて会ったのになんだか昔から知っているような気さえするという不思議なフェスです。
そんな環境を日本でも作れたらいいなと、日本でそれをやっていけるのは僕らだけだろうという気持ちから開催する運びになりました。
日本からは世界に誇れるバンドとしてSkillkillsを呼びました。
Q2: 9月には Mouse on the Keys との Split EP もリリースされました。新曲を1曲づつと、お互いの楽曲を1曲づつカバーし合うという形の作品でしたね。マウスとのコラボレートのアイデアはどこから生まれたのでしょう?
【TAKEDA】: マウスはアメリカツアーに当時行ったことがない状態でしたが、徐々にアメリカのファンもネット上で増えて来ていて注目が集まっている状態でした。
そこでマウスから何かアメリカツアーをするきっかけがないかという話になった時に、僕らは新作が11月に出ることになっていたのでそのプロモーションという意味もあり、お互いのプロモーションを兼ねてツアーを一緒に回っては?という話になりました。
せっかく日本人の2バンドでツアーを回るのでインパクトを残したいということで、2バンドでスプリットを出そうということになりました。そこで一曲お互いのカバーを入れてみようとなり、リリースに至りました。
Q3: そして遂に11/16に LITE の新作 “CUBIC”がリリースされました。前作 “Installation” からは約3年半のインターバルがありましたが、なぜ今回はリリースに比較的長い時間を必要としたのでしょうか?
【TAKEDA】: 前作をリリースした後、リリースツアーを行いました。それが日本、中国、アジア、ヨーロッパ、アメリカと続いたので必然的に時間がかかってしまったという経緯があります。
実は前作リリース直後、すぐにバンド合宿に入り、 ”Balloon”や”D”という曲の原型は出来ていました。制作は3年半継続してやっていましたが、今回のテーマでもある原点回帰はどこまで帰るべきなのかというバランスを取ることに時間がかかったと思います。
Q4: アルバムタイトルを “CUBIC” に決めた理由を教えて下さい。濱田祐史さんの手によるアートワークには未完成のルービックキューブが配されていますが?
【TAKEDA】: Installation ツアーで海外でのライブを重ねる毎に、上手く行かないことが出てきて、LITEの本当に得意なこと、オーディエンスに伝わりやすいことを考える機会がありました。
次のステップにはある種の攻撃性や無駄の無いタイトな音像が必要だと思いました。それは思えば僕らが結成当初からやってきたことだったのですが、最近はその客観的なイメージを暗に変えようとしていたのかも知れないですね。
ただそれが確実にオーディエンス・リスナーには求められているなと気が付きました。そうした意味で僕らの原点的なイメージである「幾何学的」「直線的」 を押し出した曲を作っていこうというのが今回のテーマでした。
浜田さんの作品を見た時に、キューブが「幾何学的」「直線的」であるに加えて、CMYという3色をフィルムから剥がしてそれぞれを作品にしてしまう手法は、僕らが楽器を敢えて単音で弾いてそれを重ねることで一つのフレーズになるという構築のアイデアそのものだと思いました。
実は最後の最後までアルバムのタイトルが決まっていなかったのですが、浜田さんの作品を見て色々な面でシンクロしたことで、これだ!となりそのままアルバムのモチーフにさせてもらいました。
Q5: “原点回帰”という言葉が出ましたが、”CUBIC” は、非常に緻密でデリケートとも言える “Installation” に比べて、ロックの原衝動、躍動感、生々しさ、英語で表現すれば”Raw”をイメージするようなレコードに仕上がっていますね!
同時に、欧米のマスロック勢にはあまり見られない、日本的なキャッチーさ、哀愁のようなものも感じられました。今回 “CUBIC” で目指したものについて話していただけますか?
【TAKEDA】: まさにそのとおりだと思います。
Installationのプロダクションは、バンドの音の可能性を広げるためにシンセを多用し、音を重ねてあるものから削っていく作業でした。そこで生じたのは、特に海外においてライブでの生感がスピーカーなどの音環境に左右され思ったように伝わらないジレンマでした。
併せて、ラップトップで完結していた曲も多く、メンバーそれぞれのプレイヤーとしてのキャラクターを出し切るところまで落とし込めなかった事もありました。
今回は、最小から音を重ねていく作業に切り替えて作ることにしました。そこから原点回帰というテーマになっていったという経緯があります。従って最小の音数で構成されているという意味でのタイトさが表現されていると思います。
Q6: アルバムは、BATTLES を手がける Keith Souza がマスタリングを、THE MARS VOLTA との仕事で知られる Heba Kadry がミキシングを担当しています。彼らの起用も “CUBIC” の方向性と強く関係しているように感じたのですが。
【TAKEDA】: 音を最小限にしていくのであれば音自体が太く立体的である必要があると思いました。特にドラムの音に迫力が欲しかったので、好きな迫力を出しているバンドといえば Battles ということで、今までやったことのないことをやろうといモチベーションもあり思い切ってお願いすることになりました。
メールでの打ち合わせ時に彼いわく、”2Dの音を3Dに変える” とのことでしたが上がってきたプリミックスが本当に3Dに感じられたので驚きました。
Q7: 管楽器とのジャムセッションなど様々な表情を見せる “CUBIC” ですが、武田さんのボーカルには驚かされました。さらに LITE ならボーカルを導入するにしても英詞だろうという、ファンのフワッとした概念を裏切る日本語の歌詞。今回こういった形で武田さんのボーカルを解禁したのはなぜですか?
【TAKEDA】: たまたまかもしれませんが、僕が海外でのコミュニケーションを取った母国語が英語のかなりの数の人たちは、英語ネイティブではないバンドが母国語ではなく第二外国語や外来語である英語を使って歌を歌っていることに違和感を感じていました。
日本にいながらも、それを少なからず違和感として感じていたこともありましたし、海外で普通に活動しているバンドが英語でなく日本語で歌ってきたらどう受け止められるだろうという単純な興味とワクワク感もあり、敢えて日本語で歌うことにしました。
Q8: 最初にお話にも出ましたが、UK の ArcTanGent は、ポストロック/マスロックの先端に存在するバンドを集めた素晴らしいフェスだと思います。昨年、LITE がヘッドライナーを務めたのはまさに快挙でしたね!日本からはさらに今年、 MONO や toe も出演しました。
日本のバンドとして、あのフェスを経験されて思うところ、海外と日本のシーンやバンドの違いについて感じたことを教えてください。
【TAKEDA】: 日本のバンドがかなりリスペクトされてきているということを肌で感じました。
第一人者である MONO は当然のことですが、toe や LITE だけでなく、日本でしか活動していないバンドのことも知っているお客さんが多かったし、遠い国という印象もあるのでしょうが、ライブ中のオーディエンスの反応からも待っていた感が伝わってきました。
このシーンは特に狭いこともあり、バンドを集めると勝手にボーダーレスになるし、国とかではくシーンで盛り上げようという試みが伝わってくる面白いフェスだと思います。
Q9: 武田さんは、2014年に行政書士として開業されています。LITE の活動と合わせて、所謂ダブルキャリアの状態と言えるわけですが、音楽産業の現在を考慮すればバンドマンにとってそういった生き方がスタンダードになっていくようにも思えます。
武田さんが二足のワラジを履いていこうと決めたのはなぜですか?
【TAKEDA】: 僕らのようなインストバンドは、これをメインとしていくためには、仕事や生活の大部分を犠牲にする必要があると感じた時期がありました。生活を犠牲にして残念ながら続かなくなるバンドも見てきました。
日本や海外でありがたくも求められる環境にいるなかで、なんとか続けて行きたいと思いました。続けるためには生活と時間とお金が必要だと。バンドマンはその2つがあれば好きなバンドを続けていけるはずだと。
色々と探求した結果、それを実現するためにはコントロールできるビジネスを持つことが最良の選択肢だと思いました。それで起業に至っています。まだ実現したいことは沢山あるので道半ばです。