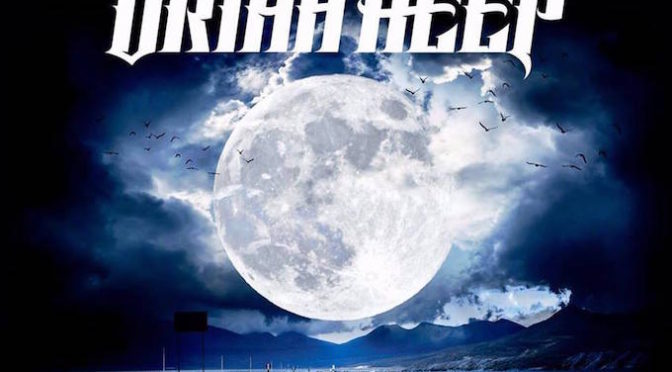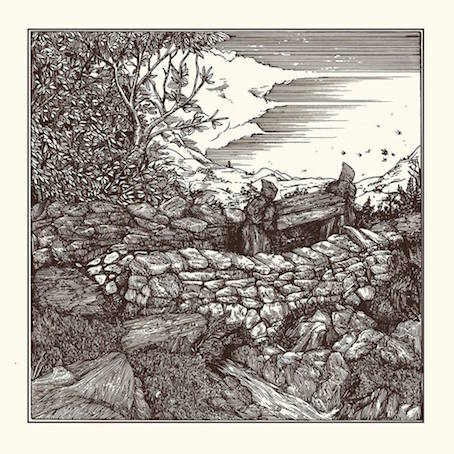EXCLUSIVE: INTERVIEW WITH SEAN TIMMS OF SOUTHERN EMPIRE !!
“When I Was 14, My Father Bought Me a Copy Of “Journey To The Centre Of The Earth” By Rick Wakeman. That Album Changed My Life!”
DISC REVIEW “CIVILISATION”
南半球、オーストラリアの南方アデレードから、プログレッシブな帆を掲げ天海へと漕ぎ出す “南の帝国”。SOUTHERN EMPIRE の紡ぐ物語はあまりに雄弁かつ壮大、圧倒的なパノラマです。
豪州のプログロックにとってアンバサダー的な存在だった UNITOPIA の解散は、旋律の魔法とアートロックの知性を愛するリスナーに茫漠たる喪失感を与えた出来事でした。
後にフロントマン Mark Trueack は元 UNITOPIA とヨーロッパのミュージシャンを集め UNITED PROGRESSIVE FRATERNITY を結成。一方でキーボーディストの Sean Timms はオーストラリアからのみ卓越した人材を選び抜き SOUTHERN EMPIRE を創設したのです。
そして Sean がインタビューで 「別のシンガーを入れた UNITOPIA だと思われないように、Mark のやっている事とは出来るだけ別の事がやりたかったんだ。」と語る通り、SOUTHERN EMPIRE は確かに異色で魅惑のサウンドスケープを深くその帝都に宿します。
30分の大曲を含む全4曲、68分のランニングタイムを携えた最新作 “Civilisation” は一見 “プログマナー”、トラディショナルなプログロックの遺産を存分に受け継いだレトロなレコードにも思えます。
しかし、実際は “プログヘブン” の領域にコンテンポラリーなプロダクション、硬質で鋭利な斬れ味、甘やかでポップなイヤーキャンディーを大胆に織り込みながら、躍動感溢れるハイエンドの造形美を提示したマグナムオパスと言えるのです。
スチームパンクなアートワークは革新を追い求める人類の象徴。ジュール・ヴェルヌの “地球から月へ” を引用したブックレットはイマジネーションへの憧憬。レトロとフューチャー、SFとリアルが入り混じるエピックに、ペリシテの巨人兵器ゴリアテに纏わる “Goliath’s Moon” 以上の幕開けはないでしょう。
ファンクのグルーヴ、モダンでシャープなリフワークに、浮遊する鍵盤の音色、陰影を帯びたロマンチックなボーカルハーモニーが折り重なればそこは異郷のシャングリラ。MOON SAFARI や FROST* にも重なるリリカルでハーモニックなメロディーのオーケストラは、リスナーを誘う優雅なオープニングセレモニーにも思えます。
「このアルバムでは、メンバー全員がライティングとアレンジのプロセスに関わったんだ。その結果は如実に現れているよね。」デビュー作と比較して “Civilisation” には瑞々しく現代的な感性が確かに宿っています。そして、”Goliath’s Moon” をシーンの新たなギターマスター Cam Blokland が作曲し、Sean がアレンジを手がけたという工程こそ、温故知新を具現化したアルバムの肝だと言えるのかも知れませんね。
同様に、ドラマー Brody Green が作曲を行い、Sean が磨き上げた “Cries for the Lonely” もユーティリティーなバンドの本質を明らかにします。NIGHTWISH や劇場音楽にインスピレーションを得た楽曲は確かに絢爛でシアトリカル。SAMURAI OF PROG の Steve Enruh が奏でるヴァイオリン、さらにはフルートの登場も相まって、楽曲はシンフォプログの夢劇場の様相を呈しているのです。
夢劇場と言えば、エレクトロニカやミニムーグ、壮麗なコーラスと共に散りばめられた DREAM THEATER への憧憬は白眉。20分の叙情ストーリーにきっと “A Change of Seasons” の華麗なデザインを思い浮かべるファンも多いでしょう。
プログメタルの大ファンではないと語った Sean 一人では辿り着けなかったであろう多様性の高みへは、Petrucci も舌を巻く鮮烈でロングスプリントな Cam のソロワークがしなやかに連れ去って行くのです。音の選択、配置、ストーリーの描写、グラウンドデザイン、全てにおいて Cam のギターワークはヒーローに相応しい煌めきを灯していますね。
元々は UNITOPIA のために書かれた大作 “The Crossroads” は SOUTHERN EMPIRE との出会いで完璧なるユートピアへと到達したのかも知れませんね。
TOTO のポップセンスに始まり、オリエンタル、フラメンコ、クラッシック、パーカッション、ホルン、ジャジーなサクスフォンにジプシーミュージック。幾重にも折り重なるエクレクティックな音楽の波は、タイトル通りここで交わり、そうしてバンドの大半が備える高い歌唱力を伴ってどこまでも前進を続けて行くのでしょう。
今回弊誌では、バンドのマスターマインド Sean Timms にインタビューを行うことが出来ました。例えば FROST* の “Milliontown”、MOON SAFARI の “Lover’s End” と同等のリスペクトを受けるべき作品だと信じます。
「僕はとても長い楽曲を書く傾向があるんだ。それは僕の歌詞でストーリーを伝えるのが好きだからなんだけどね。」どうぞ!!
SOUTHERN EMPIRE “CIVILISATION” : 10/10
続きを読む NEW DISC REVIEW + INTERVIEW 【SOUTHERN EMPIRE : CIVILISATION】