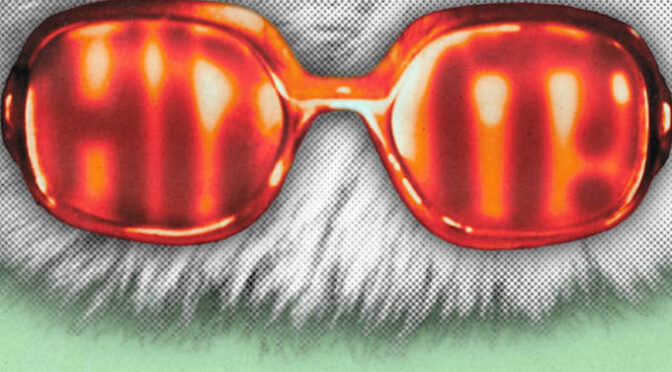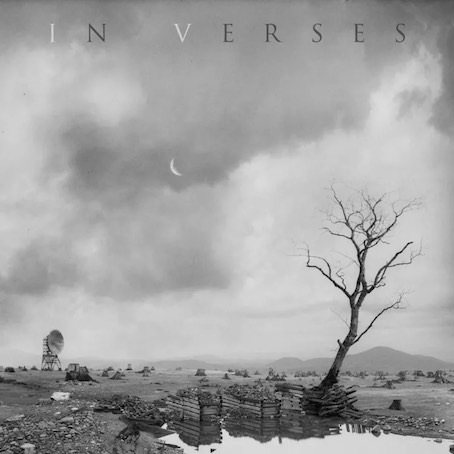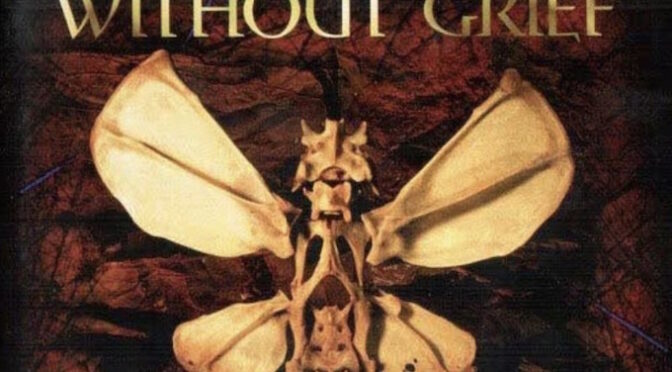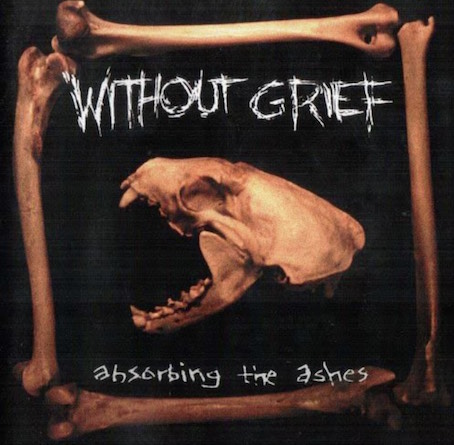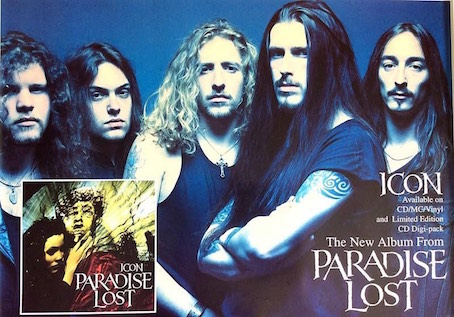EXCLUSIVE: INTERVIEW WITH MARTIN LOPEZ OF SOEN !!
“Progressive music should evolve, not just technically, but emotionally otherwise it stops being progressive and very often complexity can be “in the way” of emotion.”
DISC REVIEW “RELIANCE”
「誰かとの比較は避けられないし、僕たちはそれをネガティブなものとして捉えてはいないよ。”Reliance“ はより直接的で拡大した音楽なので、アリーナ・ロックやメタルとの関連性が自然と強く出てくるよね。だけど、僕たちの意図は特定のバンドに似せようとしたのではなく、明確かつ誠実に音楽を伝えたいというものだった。もし楽曲が人々の心に深く響くなら、それは僕たちにとって大きな喜びだ。だけど、それが目的で曲作りをしているわけではないんだよ」
2010年、かつて OPETH と AMON AMARTH というビッグ・バンドに所属していた名ドラマー Martin Lopez は、自身の新しいバンドを立ち上げました。SOEN と名付けられたこのバンドは、非常に優れたミュージシャン集団 (あの Steve DiGiorgio も在籍) で、Lopez はそのサウンドを “メロディアスでヘヴィ、複雑で、他のどのサウンドとも全く異なる” と表現していました。しかし、そんな彼の意図とは裏腹に、SOEN のサウンドは常に誰かと比較される運命にありました。
初期のアルバム “Cognitive” や “Tellurian” では TOOL と比較されることが多かったものの、SOEN は明らかにクローン以上の存在であり、Lopez の出自である OPETH や KATATONIA のプログ・メタル的な血肉にナイーブで心に迫るメロディを加えて見事な化学反応を起こしていました。近年は初期のアルバムのようなオルタナティブな複雑さ、プログレッシブな紆余曲折は減退しましたが、一方でメタリック & グルーヴィーでありながらアトモスフェリックという SOEN 独自の世界観は伸張。重要なのは、そこにいつも、心を震わせるメロディの泉が存在すること。
そうして、歌の力が戻りつつあるメタル世界で、SOEN は堂々たるプログレッシブ・アリーナ・メタルの実現へと舵を切りました。DISTURBED や NICKELBACK のグルーヴィーでシンガロングを誘うコーラスと、プログレッシブでナイーブな感情の共存。Joel Ekelof の歌声は、脂が乗り切ってまさに今が旬。
「依存は心地よいものだけど、同時に危険なものでもある。このアルバムは、答えを与えることではなく、僕たちが何に、そしてなぜ依存するのかを振り返ることを促しているよ。幸せを探し求めるとき、僕らは依存を恐れながらも受け入れなければならないだろう。ただ、何に頼るのかについては、非常に慎重にならなければならないと思う」
そんな両極を抱きしめたアルバムで SOEN がテーマとしたのは “Reliance” “依存”。SNS の発達により、私たちは見知らぬ誰かと共感しながら、何かの “推し” にかつてより深く依存するようになりました。もちろん、辛い現実を生きていく中で、幸福感や満たされた感覚を得るため好きなものに依存することは、ある意味でライフハックなのかもしれません。しかし、盲目的に “推し” に依存し、”推し” を全肯定することで、自己という最も重要な存在が消えてしまってはいないだろうか? SOEN は盲信的な依存が当たり前となった世界で、依存を恐れ、自分の頭で慎重に考慮することを促しています。
“Primal” では “無意識にスマホをスクロールしている” とか “SNSは暴力的なポルノ” といった表現が使われ、”Drifter” では “アルゴリズムを操る奴らに振り回されるな” といった辛辣な言葉が飛び出します。そもそも、あなたが依存しているのは “推し” なのでしょうか?ひょっとすると、あなたが依存しているのは “推し” ではなく、SNS そのものなのかもしれません。もしそうだとしたら、あなたが孤独を感じ、誰かと少しでも共感したいだけなのだとしたら、SOEN のアリーナ・メタルで共に歌えばいい。もちろん、進化した感情でプログレッシブに思考を巡らせながら。
今回弊誌では、Martin Lopez にインタビューを行うことができました。「音楽のトレンドは移り変わるけど、感情は残り続ける。僕たちが始めた頃は、たしかにテクニックと複雑さが非常に際立っていて、それは刺激的なことだったよね。でも今は、アトモスフィア、ダイナミクス、そして傷つきやすさにもっと居場所があって、僕たちはそれを歓迎しているんだよ。プログレッシブ・ミュージックは、テクニックだけでなく、感情面でも進化するべきなんだ。そうでなければ、複雑さが感情の “邪魔” になってしまう。よくあることだけど、それはもうプログレッシブな音楽とは呼べないからね」 3度目の登場。どうぞ!!
SOEN “RELIANCE” : 10/10
INTERVIEW WITH MARTIN LOPEZ
Q1: Soen was formed in 2010, so we have just passed our 15th anniversary.In the meantime, the band has gained more and more fans and is now one of the standard bearers of prog metal. Do you feel that the band is getting stronger and bigger?
【MARTIN】: Yes, we definitely feel that. What’s most rewarding isn’t just that the audience has grown, but that the connection has deepened. The band feels stronger because we’ve learned to trust our instincts and each other. Growth for us isn’t about numbers, it’s about clarity, confidence, and purpose, and in that sense, Soen feels more solid than ever.
Q1: SOEN の結成は2010年ですから、ちょうど15周年を迎えたところですね。その間、バンドは多くのファンを獲得し、今やプログ・メタルの旗手のひとつとなっています。 バンドはますます強く、大きくなっていると感じていますか?
【MARTIN】: そうだね、確かにそう感じているよ。一番嬉しいのは、観客が増えたことだけでなく、絆が深まったことだ。自分たちの直感とお互いを信じられるようになったおかげで、バンドはより強くなったと感じているんだ。
僕たちにとって成長とは、数字ではなく、明確な信念、自信、そして目的意識を持つことで、その意味で、SOEN はこれまで以上に強固なものになったと感じているんだよ。
Q2: When Soen started, Djent and technique were at their peak, but now I have the impression that more atmospheric bands are being sought after. How do you feel about such changes in the prog world?
【MARTIN】: Trends come and go, but emotion stays. When we started, technique and complexity were very prominent, and that was exciting.
Now there’s more space for atmosphere, dynamics, and vulnerability and we welcome that. Progressive music should evolve, not just technically, but emotionally otherwise it stops being progressive and very often complexity can be “in the way” of emotion.
Q2: SOEN がスタートした頃は、Djentやテクニックが全盛でしたが、今はよりアトモスフェリックなバンドが求められている印象があります。 そうしたプログ世界の変化をどう感じていますか?
【MARTIN】: 音楽のトレンドは移り変わるけど、感情は残り続ける。僕たちが始めた頃は、たしかにテクニックと複雑さが非常に際立っていて、それは刺激的なことだったよね。
でも今は、アトモスフィア、ダイナミクス、そして傷つきやすさにもっと居場所があって、僕たちはそれを歓迎しているんだよ。プログレッシブ・ミュージックは、テクニックだけでなく、感情面でも進化するべきなんだ。そうでなければ、複雑さが感情の “邪魔” になってしまう。よくあることだけど、それはもうプログレッシブな音楽とは呼べないからね。
Q3: The great thing about Soen is that you are always challenging and changing! Your new album “Reliance” feels more like an arena type of metal or rock. How do you feel about comparisons to Disturbed and Nickelback, for example?
【MARTIN】: Comparisons are inevitable, and we don’t see them as negative.
Reliance is more direct and expansive, and that naturally invites references to arena rock and metal. But our intention was never to sound like any particular band, we want to communicate clearly and honestly. If the songs connect with people in a bigger way, that’s something we embrace but it isn’t something that dictates how we write songs.
Q3: SOEN の素晴らしいところは、常に挑戦し、変化し続けていることでしょう! 新しいアルバム “Reliance” は、アリーナ・タイプのメタルやロックに接近した感じがします。 例えば DISTURBED や NICKELBACK と比較されることについてはどう感じますか?
【MARTIN】: 誰かとの比較は避けられないし、僕たちはそれをネガティブなものとして捉えてはいないよ。
“Reliance“ はより直接的で拡大した音楽なので、アリーナ・ロックやメタルとの関連性が自然と強く出てくるよね。だけど、僕たちの意図は特定のバンドに似せようとしたのではなく、明確かつ誠実に音楽を伝えたいというものだった。もし楽曲が人々の心に深く響くなら、それは僕たちにとって大きな喜びだ。だけど、それが目的で曲作りをしているわけではないんだよ 。
Q4: Just before Ozzy passed away, the world was united by the wonderful “Mama, I’m Coming Home”. I feel that the “power of sing,” which had been lost for a long time, has returned to metal. In that sense, I feel that “Reliance,” in which Joel’s song ability is at its best to date, also corresponds to the revival of such “power of sing”, would you agree?
【MARTIN】: Strong melodies and expressive vocals have always been our strongest tool, the hard part is to make aggressive music that is interesting to hear but doesn’t overshadow the vocals and the message behind it. On Reliance Joel’s voice plays a central role in conveying emotion and humanity and with that comes a need for clarity, strength and vulnerability that are very important for our sound.
Q4: オジーが亡くなる直前、あの素晴らしい “Mama, I’m Coming Home” で世界はひとつになりました。 長い間失われていた “歌の力” がメタルに帰ってきたような気がしますね。
そうした意味で、Joel の歌唱力がこれまでで最も発揮されている “Reliance” も、その “歌の力” の復活と呼応しているような気がしますが?
【MARTIN】: 力強いメロディーと表現力豊かなボーカルは、常に僕たち最大の武器なんだ。難しいのは、聴いていて興味深いアグレッシブな音楽を作りつつ、ボーカルとその背後にあるメッセージを覆い隠さないことなんだよね。
“Reliance” では、Joel の声が感情と人間味を伝える上で中心的な役割を果たしている。それに伴い、僕たちのサウンドにとって非常に重要な、明瞭さ、力強さ、そして傷つきやすさが求められているのさ。
Q5: Your drumming is again excellent and you have a personality that is always recognizable as Martin Lopez. Are you still trying new things and striving to get better?
【MARTIN】: Absolutely. Growth never stops. Even if my style is somehow recognizable, I’m always searching for new textures, new approaches, and better ways to serve the song.
Q5: あなたのドラミングは今回も素晴らしく、いつも Martin Lopez とわかる個性がありますね。 今でも新しいことに挑戦し、上達しようと努力していますか?
【MARTIN】: 絶対にね。 成長は決して止められないよ。 自分のスタイルがなんとなくわかっていても、常に新しいテクスチャーや新しいアプローチ、曲に役立つより良い方法を探しているからね。
Q6: “Reliance” is a very striking title. We are now strongly dependent on something through social networking sites and the Internet, or on social networking sites themselves, aren’t we? What message are you sending to this world?
【MARTIN】: Reliance reflects our relationship with the world around us.
Dependence can be comforting, but also dangerous.
The album isn’t about giving answers, but about encouraging reflection on what we rely on, and why.
You have to fear dependence but also embrace it when searching for happiness, you just have to be very careful on what to depend on.
We don’t believe that individuality is a strength in itself, we need to be able to rely on each other to feel whole.
Q6: “Reliance” “依存” というタイトルもとても印象的ですね。 私たちは今、SNSやインターネットを通じて、あるいはSNSそのものでも、何かに強く依存していますよね。 あなたはこの世界にどんなメッセージを送っていますか?
【MARTIN】: 依存は、僕たちを取り巻く世界との関係性を反映しているんだ。
依存は心地よいものだけど、同時に危険なものでもある。
このアルバムは、答えを与えることではなく、僕たちが何に、そしてなぜ依存するのかを振り返ることを促しているよ。
幸せを探し求めるとき、僕らは依存を恐れながらも受け入れなければならないだろう。ただ、何に頼るのかについては、非常に慎重にならなければならないと思う。
僕たちは、ひとりひとりの個性がそれ自体で強みになるとは考えていなくてね。僕たちは、互いに頼ることで初めて、完全な存在だと感じられるんだよ。
Q7: Speaking of social networking sites, instant music clippings and 30-second performance videos are now the norm. The world has become the opposite of progressive music, which requires long, disciplined work and thought, but why do you still continue to do this kind of music?
【MARTIN】: Because depth still matters. Our music asks something of the listener, time, patience, openess and we believe there are still people who want that experience. We need to do anything we can to resist superficiality and remind ourselves that meaning is built slowly, not instantly.
Q7: SNSといえば、インスタントな音楽の切り抜きや30秒の演奏動画が当たり前の時代となり、長い時間をかけて鍛錬し、集中力と思考が不可欠なプログレッシブな音楽とは真逆の世界になってしまいました。それでもなお、こうした音楽を続けているのはなぜですか?
【MARTIN】: 深みは依然として重要だよ。僕たちの音楽はリスナーに時間、忍耐、そして開放性を求めていて、そうした体験を求める人はまだまだいると信じているからね。表面的で薄っぺらな表現に抵抗し、アートの意味は瞬時にではなくゆっくりと築かれるということを改めて認識するために、僕たちはあらゆる努力をする必要があるんだよ。
Q8: The lyrics of the last song, “Vellichoir”, “In the dark we are all the same; in the light we can only be us” are so beautiful and I can relate. In the 20’s the world became a darker place, with wars, divisions, discrimination, and oppression getting worse. What can music and heavy metal do in such a dark world?
【MARTIN】: Music reminds us of our shared humanity. Metal, in particular, has always been a place where darkness is confronted rather than ignored. It offers understanding, and connection and sometimes that’s enough to help people feel less alone in difficult times.
Q8: 最後の曲 “Vellichoir” の歌詞、”In the dark we are all the same; in the light we can only be us” はとても美しく、共感できました。 20年代、世界は暗くなり、戦争、分断、差別、抑圧がひどくなっています。 そんな暗い世界で、音楽やヘヴィ・メタルには何ができるのでしょう?
【MARTIN】: 音楽は僕たちに共通する人間性を思い出させてくれる。特にメタルは、闇を無視するのではなく、それと対峙する場であり続けてきたからね。メタルは理解と繋がりをもたらし、時にはそれが困難な時期、孤独感を和らげるのに十分な力となるんだ。