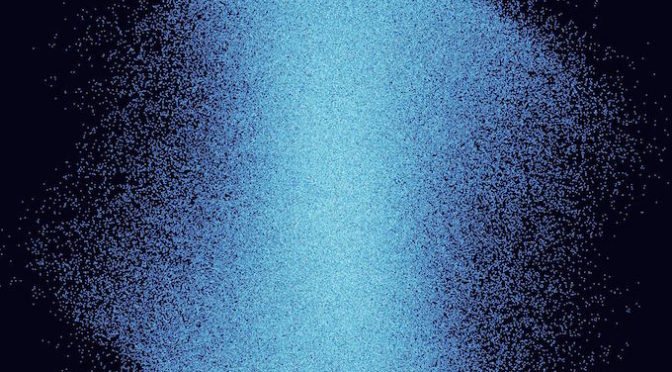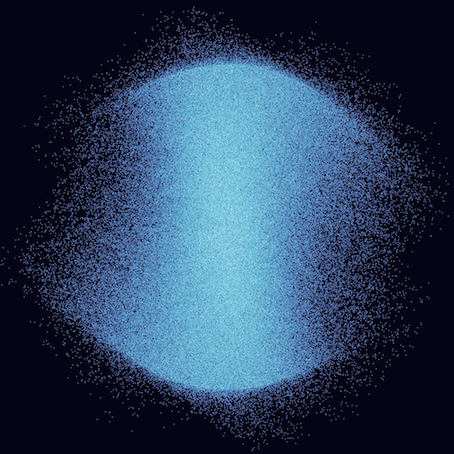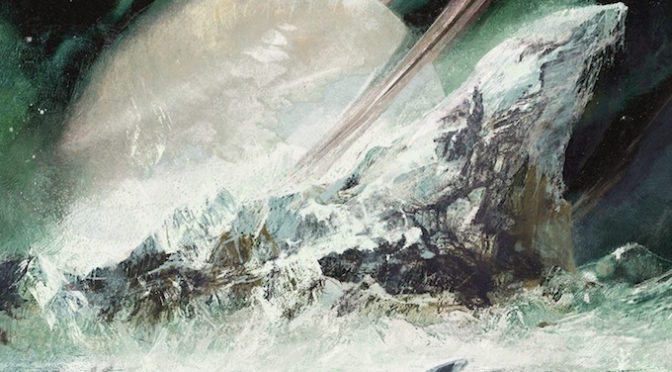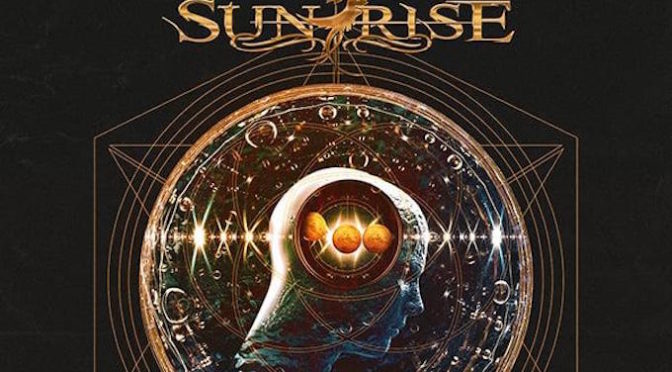COVER STORY: DEAFHEAVEN “INFINITE GRANITE”
“If Sunbather Was Summery High Noon, Then Infinite Granite Is The Early Morning.”
ROADS TO INFINITE
2020年の大半を、George Clarke は夜明けの淡い光を見つめながら過ごしました。本来ならばステージや大自然の中で過ごすはずのエネルギーを蓄えていた DEAFHEAVEN のフロントマンは、ロックダウンでロサンゼルスのアパートの壁に囲まれたまま、不眠症になってしまったのです。しかし、ただ静けさの中で煮詰まるのではなく、その厳しい美しさに魅了され、午前3時から6時の間に執筆活動を行い、夜の深い闇が昼の露に溶けていくのを繰り返し眺めていたのです。
DEAFHEAVEN 5枚目のLP “Infinite Granite” は、そうした深夜のセッションの結果として、地平線上の光の反射のように生まれました。2018年の “Ordinary Corrupt Human Love” ではまだ残していたメタリックな重さの多くを捨てて、シューゲイザーとアヴァンギャルドなポストロック・サウンドへと大胆にコミット。繊細なメロディとアトモスフィアの9トラックを収録しています。では、George にとって “Infinite Granite” とはどういった存在なのでしょう?
「”Sunbather” が夏の正午だったとしたら、”Infinite Granite” は早朝だよ」と彼は、DEAFHEAVEN が2013年に発表した衝撃的なホットピンクの作品と比較します。単純化には注意を払うべきでしょうが、やはり表向きは “黒ずくめ” を何度も塗り替えることには、皮肉や目的が存在しています。今回のTOUCHE AMORE, Nick Steinhardt による抽象的なアートワーク(レコードの最初の60秒をハイテクなグラフィックで視覚化したもの)は、クールなブルーの色調でデザインされています。しかし、そのTシャツのような美的感覚よりもはるかに重要なのは、そこに対応する経験、思考プロセス、深い考察です。
「不眠症だったから、私の宿題の多くは、午前2時から6時の間に行われた。つまり、青い時間帯に多くの曲を書いていたと思う。それもアートワークに影響を与えているよ。全体的に、この落ち着かない時期の影響を受けているようだね」
例えば、タイトルにもなっている “Infinite Granite” “無限の堅牢” は、保留中の人生の静けさや停滞によって “化石化” した気分を表すメタファーです。George が当時を思い返します。
「固い空間に閉じ込められているような感覚があったね。繰り返しや日常の重みを感じていたんだ。”Infinite Granite” という曲は、抽象的な過去が現在の自分にどう影響を与えるかについて歌っている。自分が、部分的には家族の歴史の産物であることを知る。家族の問題はしばしば自分の問題でもあるんだよ。家族の苦難は、必然的に自分の人生でナビゲートしなければならないことにもつながる。それは過去を振り返ることであり、その過去が自分にどのような影響を与えるかを見ることなんだ」
印象主義的な歌詞の表面をなぞると、そこには幸運や運命、家族についての力強い問いかけがありました。
「この作品は、過去を振り返り、その過去が自分にどのような影響を与えるかを理解することが大部分だと感じているよ」
昨年12月に発売されたライヴ・アルバム “10 Years Gone” で節目を迎えた DEAFHEAVEN 10年目の旅。そこで彼らは空虚な時間の中、創造力としての彼らの過去、現在、未来を見つめ直し、それが “Infinite Granite” の印象的なスタイルの変化へとつながっていきました。”Daedalus” や “Language Games” のような初期のカットから、”Ordinary Corrupt Human Love” に収録された11分の “Glint” のようなより実験的な最近の曲まで、8つの傑出した曲を収録。ブラックメタルをベースに、シューゲイザーやポストロック、アンビエント・ミュージック、さらにはオルタナティブ・ロックまでをも取り込んで、DEAFHEAVEN が常にサウンドを前進させてきた10年の終わりに、このアルバムは驚くほど自然な響きを誇っていました。いいかえれば、DEAFHEAVENの物語を自らの言語で語った作品であり、それは彼らが時間をかけて洗練させ、故意に変化させたものなのです。George が振り返ります。
「最も注目したのは、10年間で私たちがどのように変化したかだった。より速く、よりアグレッシブに、よりスマートなダイナミクス、よりスマートなトーンになっていたよ。そして、これらの曲をレコーディングした後、すべての曲に歯ごたえと緊迫感が増していることに気がついたんだ。私たちがどのように成長したのかを見るのはとても興味深いことだったな。ある意味では、新しい DEAFHEAVEN が古い DEAFHEAVEN をカバーしていたというか。若い曲に今の自分たちの姿を重ね合わせていたんだ。例えば、 “Glint” のライブ・バージョンはレコードに収録されているものよりもかなり強化されているよね」
DEAFHEAVEN はブラックメタル純粋主義者の間では常に物議を醸していましたが、2013年の画期的な作品 “Sunbather” 以降、彼らはアンチの数を補うだけの賛同者が広い世界にいることを証明してきました。次に彼らが進む道は?
5枚目のアルバム “Infinite Granite” は、その問いかけに力強く答えます。今回の最も大きな変化は、リードシンガー George Clarke の声でしょう。過去のアルバムでリバーブの中に滲み出た扇情的で血も凍るようなエイリアンの叫び声はほとんどなくなり、代わりに TEARS FOR FEARS にも似たクリーンでメランコリックなボーカルが登場します。あるリスナーにはアリーナ・ロックが聞こえ、あるリスナーにはインディー・ロックが、あるリスナーにはアート・ロックが聞こえるでしょう。 しかし、このような急激な変化にもかかわらず、”Infinite Granite” は紛れもなく DEAFHEAVEN のアルバムです。つまり、広がりがあり、妥協がなく、極端。ギタリストの Kerry McCoy は彼らの過去と現在を対比させます。
「2011年のデビュー作 “Rods To Judah” を書いていた時の子供の俺を思い出すよ。Deathwish のようなレーベルと契約し、本物のブッキングエージェントを持ち、ドアが開くのを見たんだ。それは宝くじに当たったようなものだった。俺は文字通り、マイニングで得た金で暮らしていると思っていたし、今でもそう思っているくらいでね。だけど、俺はあの子供にとても共感しているんだ。あの子に、『大丈夫だよ、全部うまくいくよ。自分でコントロールできないことは心配するな』と言ってあげたいね」
Kerry は、”Ordinary Corrupt Human Love” を制作したあのころのバンドにも共感を示しています。たしかに3年前から変化は起きていましたが、薬物やアルコールへの依存を克服したこと、自分たちのバンドを囲い込むことに夢中になっていた同業者や有識者への “恨み” を晴らしたことは、より広い創造的解放への第一歩に過ぎませんでした。
「あのレコードは、禁酒する前に半分書いて、禁酒した後に半分書いたんだ。あの時期は、俺の脳内化学反応、感情、個人的な人間関係が非常に混乱していてね。個人的にも集団的にも、自分たちのことを理解し、成長し、いくつかの悪魔を正していくうちに、クリエイティブな人間につきものの恐怖心がなくなってきたんだよな。これが今の俺たちの状況で、言い訳をしたり、誰かに何かを証明したりする必要はないと思っている」
昔はもっと波乱万丈だったと George は言います。「私たちはエゴやネガティブな気持ち、自分が一番になりたいという気持ちに駆られていたからね。今では、そんな恐れを知らないことが私たちの原動力になっているんだよ」
“Infinite Granite” の作曲とレコーディングに向けて、バンドの5人のメンバーとコラボレーション・チームは、グループ・チャットの名前をそのまま “Infinite Granite” に変更しました。
Kerry が言うように “完全にロックなレコード” になるという明確なコンセンサスはありませんでしたが、状況はそのように傾いているように見えました。最終的にアルバム中盤のハイライトとなった “Lament For Wasps” の波打つシューゲイザーはテンプレートとなっているでしょうか。”Villain” で実験した “空気のようなファルセット” は、さらに彼らの方向性を強調します。
「いろいろな歌手の歌を聴いていた。力強く歌える方法を探していたんだ。シューゲイザーのライブで問題になるのは、轟音のギターに対抗して、ソフトな声を出すこと。私が好きバンドでも多くは、ライブでそのダイナミックさが必ずしもうまく伝わっていない。ミックスでそのバランスを取るのはとても難しいんだよね。
そこで最初に考えたのは、ギターに対抗できるような強い声が必要だということ。そこで、クラシックの名曲に立ち返り、ニーナ・シモンやチェット・ベイカーなど、個性的で力強い声の持ち主の声を聴くことにしたんだ。それに、TEARS FOR FEARS, DEPECHE MODE といったより力強いシンガーも。最終的にライブで演奏することになったとき、大音量のライブ音楽の中で繊細なボーカルに磨きをかけなければならないような、大きなハードルにはしたくないと思っていたからね。それがモチベーションになったんだ。
ある意味では、”Ordinary Corrupt Human Love ” の “Near” や “Night People” のように、自分ですでにやっていたことでもある。それでも、私のアイデンティティではないような、体外離脱の感覚はあるんだよね。全く新しい筋肉を使い、全く違う脳の部分を使っているような感覚だった。
あまりにも新しいことだから、途中で不安になることもあったよ。ボーカルだけでなく音楽的な面でも、作曲の過程で、ダブル・キックなどを簡単に入れることができたはずなのにとかね。それでも、いつも私の意見は、昔の習慣にとらわれず、進むべき道を進むだった。そして、それは何よりも私のためになったんだ。悲鳴を上げないで、自分のやりたいことをやるんだ。そして、やっているからには、続けること。続けること、そしてその正直さを発揮することがとても重要だった」
この楽曲は、George が禁酒について直接言及している唯一の曲でもあります。 “New Bermuda” の重苦しいトーンが、彼らがロサンゼルスに移った後、バンドを取り巻く幻滅とドラッグの雲を象徴していたことは明らかでした。”Infinite Granite” の角質除去されたサウンドには、感情の浄化が暗示されていますが、それは “Villain” で明確になりました。”Inform my mother’s people / 30 months is war / Dealing with the blood of 30 years well wear “とクラークは歌っています。 行間を読むのは簡単です。George は、30歳になって2年半の禁酒期間を経て、この曲を書いたことを認めています。”Infinite Granite” は、あからさまな断酒の記録ではありませんが、人間関係へのアプローチ、野心の概念、30歳を過ぎてからの個人的な進化についてのバンドの大きなテーマ、その中に断酒も確実に含まれていました。
「私の家系では、アルコール依存症と薬物依存症が何世代にもわたって大きな問題となっていた。ここ数年はそのことをよく調べていたんだよね」
事態が進むにつれ、George は自分のヴォーカルを “音楽的な弱点” と称して、より計算されたものにしたい、より行き当たりばったりではないものにしたいという願望を表明しました。
「私はアグレッシブなボーカルが好きだよ。何年もあのやり方を、楽しみながら進化させてきた。だけど、挑戦したいという気持ちが強かったんだ。これまでの DEAFHEAVEN のような伝統的なボーカル・アプローチでは、今回の曲を向上させることはできないだろうと思った。この方向性を考えると、全体を覆うような激しいボーカルでは限界があるのではないかと言ったんだ。より冒険的なボーカルと音楽をマッチさせる方が野心的だと感じたんだよね」
2018年末にプロデューサー Justin Meldal-Johnsenとの “セレンディピティ” な出会いがあったことで、この方向性はさらに加速しました。Kerry は Justin のカリフォルニア州グレンデールのスタジオで、匿名の他のアーティストにギター・パートを提供するように頼まれていました。そして George は、その年の12月にロサンゼルス・パラディアムで行われた NINE INCH NAILS のライブで Justin とばったり出会いました。DEAFHEAVEN はこれまで Jack Shirley(”Infinite Granite” のエンジニア)としか仕事をしたことがありませんでしたが、Justin のバンドに対する新鮮な熱意を受け、彼らの視野を広げる機会を見逃すことはできなかったのです。Kerry が説明します。
「Jackは、非常に自由な人なんだ。俺たちは彼の意見を聞きたければ聞くけど、俺たちの邪魔をするようなことはしない。彼は、その日のそのバンドの、その曲のタイムカプセルを作ることに重きを置いているからね。Justin は、俺をプロデュースすることに専念していたよ。俺はこれまで、そんなにインプットを受けたことがなかったからね。それがとても役に立ったんだ。とてもクールで満足のいく経験だったな」
実際、DEAFHEAVEN の煌びやかでエモーショナルなテイストは、その領域を誰よりも知っている男によって完全に引き出されています。Justin Meldal-Johnsen は、現在 St.Vincent のベーシスト兼音楽監督を務めており、Beck のツアーバンドにも数十年にわたって参加していました。さらに彼は M83の巨大なエレクトロポップ作品 “Hurry Up, We’re Dreaming” のようなサウンドを求める際に雇われる人物で、そのリストにはエモポップの代表格である TEGAN AND SARA, PARAMORE, JIMMY EAT WORLD までもが含まれているのです。
Justin は当初、DEAFHEAVEN が2019年の7分半の激しいシングル “Black Brick” の延長にあると考えていましたが、実際目の当たりにしたより広い方向性に目を見張りました。
「彼は最初、”Black Brick” みたいにやろう!という感じだったけど結局その後、全く別の感じに仕上がってしまったよね (笑) 。だから彼は必ずしもこの方向性に対して準備ができていなかったにもかかわらず、自分ができる最善の方法でこの音楽を促進してくれたんだ。このレコードを聴いた人たちが、新しいプロデューサーとして入ってきた彼を見て、『ああ、彼が DEAFHEAVEN をこの方向に押しやったんだな』と思うのは間違いないけどね。でも、変な言い方をすれば、それはほとんど逆だったんだよ」
実際、Justin の助けは必要でした。COVID がバンドとプロデューサーのカレンダーを空白にし、数ヶ月に及ぶアルバム制作に入ると、”従来型” の曲作りの難しさが痛感されたのです。Kerry が回顧します。
「俺たちは、これまでのキャリアにおいて、動きのある曲を書いてきたんだ。バース、プレコーラス、コーラスを試すというアイデアは、後ろ向きに見えて奇妙にも俺たちにとってはとても進歩的なものだった。また、ダブルキック、ブラストビート、そして大きなクレッシェンドというような手法に戻ることなく、普段やっていることの重厚さと強さを維持しながら、自分たちらしいサウンドにするという課題もあった。これまでのやり方の代わりに、DINOSAUR Jr. や SONIC YOUTH が楽曲にどうアプローチするかを考えてみたんだよね。今は鍛えるべき筋肉が違うんだ。同じトリックに戻ることなく、普段やっていることの強度を維持するという挑戦だよ」
George にもこだわりがありました。
「今回の作品は、以前の作品に比べて、よりディテールにこだわった、よりテクニカルなものになっているんだよ。いろんな意味で非常に赤裸々なんだ。これまでは、より強力な要素が混ざり合って、ある種の洗礼となっていた。だけどここでは、すべてが表現されているんだ。以前のサウンドに頼らずに、曲の流れやダイナミックさ、ドラマチックさを出すために、どれだけ細かく配慮しなければならなかったか。非常に難しかったよ」
リード・シングル “Great Mass Of Colour” は、そういったディテールの追求を象徴していると George は証言します。重なり合うボーカル・パターンと鏡のようなハーモニーはさながら渦を巻く万華鏡。「I feel them all / Great mass of color / Flooding in my bed / Dissolving into red…」高揚感を増した詩が、明快なコーラスへと展開しそして、堤防が決壊。ブラックメタルのまばらな水しぶきがようやくこぼれ落ちていきます。
「ただ単にメロディックなものを作るだけではないんだよ。大事なのは、記憶に残るものを作ることなんだ」
結果として “Infinite Granite” の楽曲コレクションは、ある部分では研磨され、ある部分では高光沢に溢れ、DEAFHEAVEN の新たな歩みへの第一歩となりました。
アルバムのオープニングを飾る “Shellstar” の鳴り響く馴染みのないアンビエンスは、熱気と怒りに飛び込むのではなく、雲の中を滑るように進んでいきます。George が語る「夏の火の中を崇高に彷徨う/炭、灰、咳、轟音…」というストーリーには、奇妙なメランコリーが漂っています。シングル “In Blur” は、RIDE 1990年の名曲 “Vapour Trail” を下敷きとしたもので、古典的なシューゲイザーの夢見がちな幸福感に翻弄され、「この混沌とした寒さの中で、昼の光はどのように見えるのだろうか」と問いかける、力強く痛烈なレイヤーボーカルをフィーチャーしています。
シンセを駆使したインストゥルメンタル “Neptune Raining Diamonds” は、ブレードランナーのスコアからそのまま切り取ったような186秒。アルバムの中で最も短い曲ですが、レトロフューチャーな眩しさがキラキラと渦巻いています。さらに大作 “Mombasa” (Shiv の母国であるケニア最古の都市にちなんで命名)の8分間は、平穏な美しさから猛烈なカタルシスへと宇宙を駆け抜けるような非日常を投影します。一方で、パンデミックという非日常が及ぼした影響も捨てきれません。George が証言します。
「頭の中にある恐怖や起こっている混乱が、曲作りにもよく影響していたよ。いくつかの曲で聞くことができると思う。特に “The Gnashing” には、ちょっとした奇妙な緊張感があるよね。あの曲のを作っているときに、LAで夜間外出禁止令が出たんだ。フリーウェイがすべてストップしていたのを覚えているよ。LAPD が至る所にいた。ヘリコプターのようなものも。そしてもちろん、BLM と、当時州内で起こっていた火事との間で、LAは日々赤茶色に染まっていて、現在進行中の COVID の状況もあった。これらのことがすべて、この曲に反映されているんだ。仮のタイトルは “End of the World” で、本当に終末論的な感じがしたよね。この曲には、終末論を感じさせる大きなエンディングがあり、全体的にダークでドライな雰囲気がある。あの雰囲気の中で作っていなかったら、必ずしも同じようにはならなかったと思うな」
では、これらの率直に言って、これまでと全く異なるサウンドは、メタルの世界、そしてその場所の牽引者としての立場から身を引く覚悟の意志表示なのでしょうか?George は決して反動ではないと断言しました。
「このアルバムは、非常にドライで、繊細で、エモーショナルな作品で、強さと開放性に焦点を当てている。実にテーマ性の高い作品で、解き明かすべきことがたくさんあるんだよ。私たちのすべてのレコードと同様に、この作品は今の私たちを映し出す鏡であり、人間としての私たちを自然に映し出している。もし何かへの反応だとするならば、それは自分たちの前作への反応だと思うんだ」
たしかに、このアルバムには古の影響が新しいスタイルのフィルターを通して吹き込んでいます。もちろん、ブラックメタルやブラックゲイズの影響はそれほど顕著ではありませんが、ノルウェーの伝説 ULVER の “Kveldssanger” 時代の冷ややかな閃光や、フランスの鬼才 ALCEST が2014年に放った “Shelter” の眩い光も差し込んでいるはずです。それに繊細で豊かなテクスチャーは、MY BLOODY VALENTINE, SWERVEDRIVER, SLOWDIVE といった英国のシューゲイザー・ムーブメントの要素がふんだんに盛り込まれているでしょう。
Kerry は、これらの参照点をさらに拡大して、PINK FLOYD, APHEX TWIN, Brian Eno, THE SMITHS, そして尊敬するスウェーデンのプログレッシブ・バンド、DUNGEN の名を挙げます。一方、 George は RADIOHEAD の重要性を強調し、高い評価を得た2016年のLP “A Moon Shaped Pool” とその3枚目のシングル “Identikit” が特にインスピレーションを与えてくれたと語っています。
実際、DEAFHEAVEN は、”Infinite Granite” を RADIOHEAD が2000年に発表した “Kid A” の自分たちのバージョンだと一貫して発言しています。大胆な音の再出発でありながら、作者のアイデンティティを維持し、拡大しているという共通項をあげながら。George は、「自分たちのやりたいことを堂々と、そして自由にやるという姿勢が大切だ。ヘヴィー・コミュニティでは、BORIS や OPETH のように、自分たちが制限されることはないという理解に基づいて活動しなければならない」と胸を張ります。
では、メタルのエッジを放棄した新たな領域で、DEAFHEAVEN らしさを保つための要素とは何でしょうか?Kerry は熟孝します。
「同じバンドの異なるフレーバーに過ぎないんだ。俺たちの音楽がいつも喚起する核心的な感情のすべてが、新しいフィルターを通して表現されているだけなんだよ。2015年の3枚目のLP “New Bermuda” で、自分たちの音楽にスラッシュやデスメタルの要素を入れることができると気づいたように、今回はこれもできると言っているんだ。それはそれでいいんだよね。これは、俺たちがクリエイティブな筋肉を伸ばせるように壊した、もうひとつの壁なんだよね。人は好きなことを言うものだよ。それは俺たちの仕事ではないんだ。俺たちの仕事は、欲しいものを作ることだけだから…」
George にとって、”Infinite Granite” は、かつてのトレードマークであった爆音のブラックメタルと落ち着いたアンビエンスの摩擦がなくても、気が遠くなるようなエッジを保つことができるという点が重要でした。
「このアルバムは、究極的には私たちを裏返したもの。まだまだ緊張感があるよね。メロディックであっても、かなりの不快感がある。私たちは、その緊張感のある微細な部分に焦点を当てるように努めたんだ。少し地味になったかもしれないけど、面白さが減ったとは思わないよ…」
パンデミックの影響を受けて、George はアメリカを離れ、ニュージーランドで数カ月間の旅行を楽しみました。地球上で最も息を呑むような景色に囲まれ、この島国のCOVID対応のおかげですべてが正常に機能していましたが、それでも彼はツアーに戻ることを夢見ていました。
「Kerry と私は、ライブがなくなったことで、ツアーや世界旅行、人々との出会いなど、このライフスタイルへの愛が深まったと話していたんだ。それは、私たちが失ってしまった、非常にユニークで素晴らしいものなんだ。だから、このアルバムのことを考えるときには、ツアーのことを考えているよ。つまり、可能な限り外に出て演奏し、最も愛している人たちと一緒に、最も愛していることをしながら世界を見て回りたいんだ」
“Infinite Granite” のクリエイティブな “賭け” が功を奏するのか、ファンの中でより凝り固まったメタルヘッズが離れていくならば、DEAFHEAVEN はそれを受け入れることができるでしょうか?George は答えます。
「ファンを失うこと、つまり、得することと失うことの二律背反は、実に面白いものだ。このバンドを愛してやまない私たちのファンが、このアルバムに共感できないのなら、私は理解するよ。彼らに恨みはないし、願わくば我々にも恨みをもたないでもらえれば。私たちには、他にもたくさんの作品がある。ある時期にお互いを見つけることができたのは、幸運で今でも本当に信じられないことなんだよ。そしてすべては進化していく。DEAFHEAVEN では、どの場所からでも乗ったり降りたりすることがでるんだ。この変化は必要だった。もし私たちが、ブラストビート、メジャーキーのコード進行、ディレイのかかったギターでいっぱいのレコードをもう1枚出していたら、人々は私たちに “壊れていないなら、直さないで!”というようなおきまりのレガシーバンドになるよう求めただろうから」
Kerryは誰かのための創作がいかに無意味かを知っています。
「誰かを喜ばせようと考え始めた瞬間に、自分の足を撃つことになる。まあでも、レコードが完成してから6ヶ月間じっくりと考えてみると、どうしてもそういった疑問が出てくるよね。俺たちが出すすべてのレコードは、どこかで怖い思いというかリスクを冒している。だけど、俺たちが音楽制作をしているときは、自分自身にも他の誰にも、「人々がこれをどう思うだろうか」というような疑問を持つことを許さないというルールがあるんだ。”New Bermuda” では、よりヘヴィーな要素を加えていったし、”Ordinary” では、ピアノから始まる曲でアルバムを始めた。毎回、同じルールで制作しているだけなんだ。まあ今回は “掛け金” が多少高かっただけでね。あとはツアーに出て、俺たちを好きな世界中の人たちと話すだけさ。彼らのTシャツを見て、このバンドが好きなキッズたちは、これから飛躍していくだろうと思うんだ」
George はレビューを読むことをやめました。
「”Sunbather” が爆発したとき、あるいはその前に “Roads to Judah” をリリースしたときには、私たちの存在を世界全体が認識していることを初めて垣間見ることができた。それはエキサイティングなことで、特に私たちが22歳、23歳のときには、私たちが作ったものをみんなが気に入ってくれている、クールだな。読んでみようかな?ワオ!ってね。そして、レビュー夢中になったよ。だけど、”Sunbather” が定着した頃には、レビューなんてどちらでも構わないということに気がついたんだよね。というのも、批評家の愛に感謝しているけど、それがずっと続くとは限らないから。あるいは、人間は人間であるとか、彼らは物事に対して様々な意見を持っていて、それが彼らの仕事であるとか、そういったことにね。
特に昔、”‘Sunbather” の時代には、私たちは音楽全体への神からの贈り物だという意見と、何でもありの真新しいものだという意見、その2つの陣営があるように思えた。私たちについて、卑劣で邪悪なことを言っている人もいたよ。私はこの2つの陣営が間違っていることに気づいたんだ。私たちは、音楽界に起こった最悪の出来事ではないけれど、もちろんビートルズでもなんでもない。私たちはただ音楽を作っている人間の集まりで、人々はそれに共感しているんだよね」
岐路において、安全性よりも自己満足を選択することは、いずれにせよ大きな賭けです。DEAFHEAVEN は、黄昏時のシューゲイザーがチャートを独占するはずもないことを十分に理解しており、より激しいメタル・サウンドにしがみついていた方がはるかに安全であることも知っています。ゆえに彼らは、自分たちに忠実でいるために常にリスクを取る価値があると繰り返しています。
いいかえれば彼らは、SLIPKNOT のような “当たり前” の存在となることを危惧していたのです。DEAFHEAVEN 自身は、2019年に BARONESS と共演した際にその危険性を認識していました。サイケ・スラッジの強豪で、確立されたフォーマットに忠実でありながら、常に興味深い方法で進化することに成功している BARONESS。彼らの最新LP “Gold & Grey” は、色分けされたアルバムタイトルを尊重しつつ、新しいギタリストと、TAME IMPALA のミキシングやMGMTのプロデュースを担当した人物を抱え込んでいます。DEAFHEAVEN は、自分たちも同様に長期的に活動する方法を考え始めていたようです。George は、ツアーを通して「やりきった感があった。ツアー中にもう限界だという感覚があったんだ。私は壁にぶつかってしまったようで、この先に私ができることはこのやり方にはもうあまりない」と認めていました。そうして彼らは未開の荒野に再度その身を解き放っていったのです。
「もし俺たちが “エクストリーム・メタル” のバンドであり続けたいと思っていたら、それは難しいことじゃなかった。今後10年間、”Deafheaveny” のレコードを出し続けることで、保証はどんどん増え、フェスのオファーも大きくなっていくだろうから。そうすれば、素敵で小さな “何か” にはなれただろう」
「私たちは、クリエイティブな面に少し興味を持ちすぎているんだ。つまり、他の何よりも自分たちが充実していないと、このプロジェクトは長続きしないんだよね。だから、私たちはまた未開の荒野に身を投じてしまうのさ」
DEAFHEAVEN にはまだまだ可能性が秘められています。
「アルバムには収録されていないけど、ある時期、初期のDJ Shadow や Unkle の最初のレコード、BOARDS OF CANADA のような雰囲気のものを入れようと考えていたことがある。これは、俺がよく聴いていたものでね。バンドの中に PORTISHEAD や MASSIVE ATTACK の影響があるのは確かだと思うけど、俺が興味を持っているもの、Shiv が興味を持っているもの、George が興味を持っているものなど、たくさんあるんだよね。例えば、このアルバムにも初期のWarp レコードや、”OK Computer” の “Airbag”、DJ Shadow のようなものを入れようとしていたんだ。だけど、それは全くフィットしなかったね。結果的にはそれがベストだったと思うけど。とにかく、俺たちにはまだいくつかのレーンが残されていると思うし、そうあってほしいと思う。それこそがクリエイティブな人間の醍醐味だと思うからね」
そう Kerry が目を輝かせれば、George も同意します。
「そうだね、確かにレイドバックしたトリップホップの影響は、私たちもかなり試したけど、今回のアルバムには必ずしも反映されなかった。オーケストラ的な要素を取り入れたり、補助的な楽器を追加したりすることも、まだやったことがないよね。ストリングスにしても、特に理由はないけど入れたことがない。Kerry が言ったように、私たちは常に何かを取り入れたり、試したりすることができる。そして願わくば、私たちが実験を続け、成長し続ければと思うよ」
日本盤は DAYMARE RECORDINGS から発売中!
参考文献: KERRANG!: When The Sun Hits: How Deafheaven stepped out of the shadows to embrace a brave new dawn
THE RINGER:The Sunbathers Turn to the Light: Deafheaven Is Back, and Clearer Than Ever
FADER:Deafheaven on evolution, reinvention, and Infinite Granite
本日日本先行発売!
DEAFHEAVEN “Infinite Granite”
クリーン且つメロディアスなヴォーカル、UK勢を思わせるギターワーク、ロック度を上げたリズム・セクションの力強さ、変化に富んだ楽曲、カラフルでリッチな音の奥深さ。メンバーが「10年の集大成がこの8分間にある」と自負する”Mombasa”が超名曲! pic.twitter.com/Khe8N31Nvx— Daymare Recordings (@daymarerec) August 18, 2021