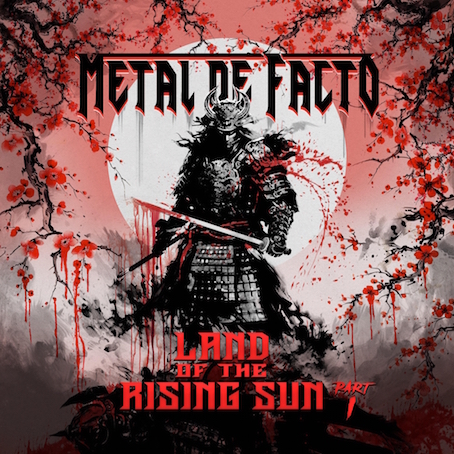EXCLUSIVE: INTERVIEW WITH VILLE VILJANEN OF MORS PRINCIPIUM EST !!
“When we started, we just wanted to make melodic death metal. We did not want to sound exactly like some other band, so maybe that is one reason. But I guess our songwriters just wanted to write songs the way we have done.”
DISC REVIEW “DARKNESS INVISIBLE”
「結成当初は、ただメロディック・デスメタルを作りたかったんだ。ただ、他のバンドと同じようなサウンドにはしたくなかった。それがテクニカルになった理由のひとつかもね。このバンドの歴代のソングライターたちは、そうして僕らがやってきたように、テクニカルな曲を書いていきたかっただけなんだと思う」
メロデス始まりの地、イエテボリから少し離れたフィンランド。彼の地もまた、メロデスを牽引した重要な場所のひとつであるだけでなく、より革命的なメロデスを生み出したと OMNIUM GATHERUM のインタビューにて記しました。AMORPHIS とカレワラの奇跡的な邂逅は、後のフィンランドのメロデス世界に “個性的である” ことを運命づけたとも言えます。CHILDIEN OF BODOM, OMNIUM GATHERUM、そして最近の BRYMIR までフィンランドのメロデスは、それぞれステレオタイプとは異なる並外れた個性を持って戦ってきました。
MORS PRINCIPIUM EST もそんなフィンランドの綺羅星のひとつ。彼らの個性は、激烈なデスメタルに、ハイパー・メロディックでウルトラ・テクニカルな冷気を吹き込むことでした。
「僕にとっては、どのアルバムも特別だよ。 それぞれのアルバムがなければ、僕らはここにいなかったし、”Darkness Invisible” というアルバムもなかっただろうからね。でもそうだね、このアルバムにはファースト・アルバムからの影響もあるけど、新しいアルバムからの影響もあると思う」
古のメタル・ファンにとって、そんなフィンランドの冷気と冷徹の洗礼を存分に浴びたのが、デビュー作 “Inhumanity” であり、名作 “The Unborn”, “Liberation = Termination” だったのです。当時のギター・チームが脱退し、Andy Gillion というメロデス・シュレッド・マシンを得て、MORS PRINCIPIUM EST は荘厳シンフォニックな要素も加えながらさらに飛翔。Gillion を失うも、黄金のギター・チーム、そしてほぼオリジナル・メンバーが復帰して最新作 “Darkness Invisible” が完成を見たのです。そうして、今回のインタビューイ、バンドの首領 Ville Viljanen が語る通り、アルバムは初期と後期の完璧なる融合、MPE 集大成ともいえる傑作に仕上がったのです。
“Of Death” と “Venator”、開幕の二連撃から我々は、Jori Haukio のメカニカルかつ抒情的なシュレッドに “Liberation = Termination” の影を見ます。そうして、牧歌的なインタルードを挟んで押し寄せる、中盤の威風堂々たるドラマティシズムに我々はただ圧倒されるのみ。近年の耽美と荘厳で磨き抜かれた初期の激情と慟哭は、狂おしいまでにフィンランドの風を運び、リスナーに北欧のカタルシスを届けるのです。そう、彼らの個性はもはやフィンランドの秘宝。
今回弊誌では、ボーカリスト Ville Viljanen にインタビューを行うことができました。「メロデスは以前ほど人気がなかったり、他のジャンルほど人気がなかったりするかもしれないのはたしかだ。それでも今でも必要とされているし、求められていると思う。僕たちが演奏を続けているのは、ただメロデスを演奏するのが楽しいからなんだ」 来日も決定!どうぞ!!
MORS PRINCIPIUM EST “DARKNESS INVISIBLE” : 10/10
続きを読む NEW DISC REVIEW + INTERVIEW 【MORS PRINCIPIUM EST : DARKNESS INVISIBLE】JAPAN TOUR 26′