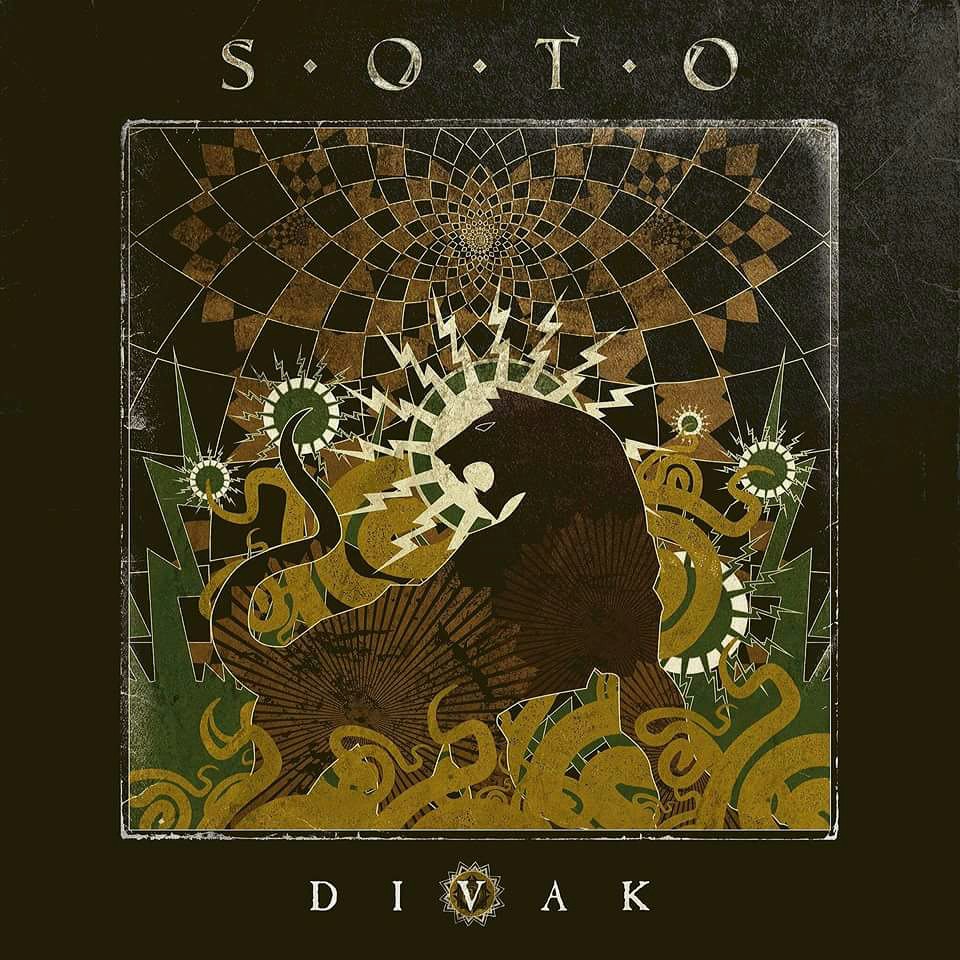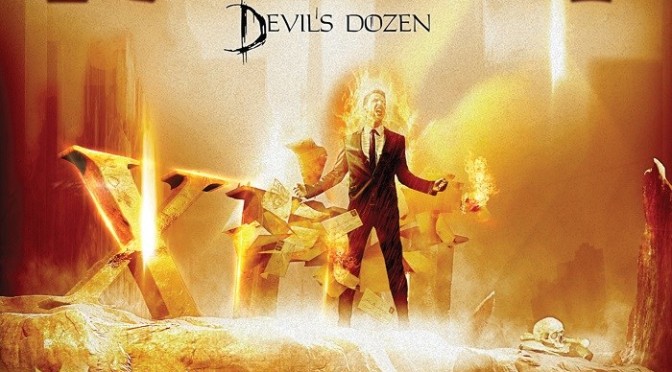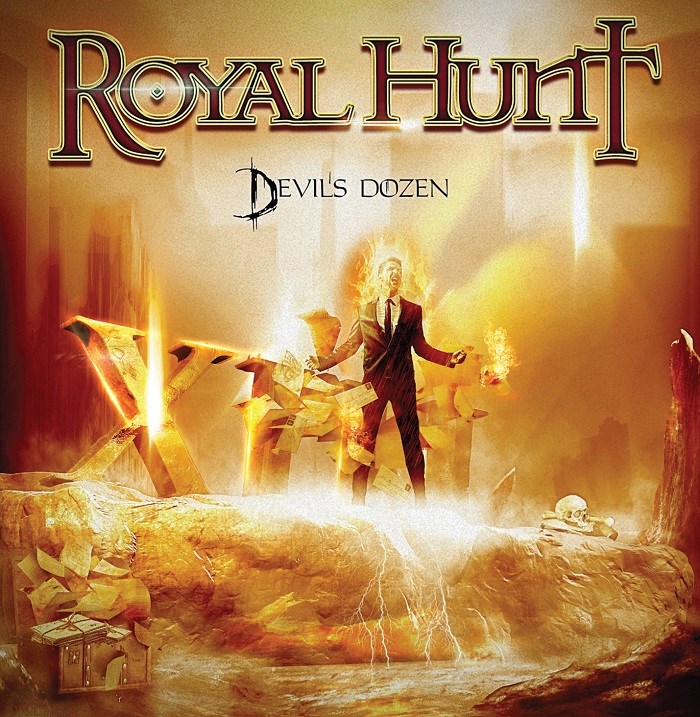EXCLUSIVE: INTERVIEW WITH JEFF SCOTT SOTO !!
Legendary Vocalist, Jeff Scott Soto Talks About Japan Tour With Kuni, Talisman, Yngwie Malmsteen, And More !!
“A GUIDE TO JEFF SCOTT SOTO”
Jeff Scott Soto。Yngwie Malmsteen のバンド RISING FORCE の初代シンガーとして華々しくシーンに登場した唯一無二のボーカリストは、ソロとしては勿論、TALISMAN, JOURNEY, W.E.T. など数多のバンド、プロジェクトでその際立った才能を発揮し続けて来ました。ソウルフルでエモーショナル、”黒い”感覚を保持しながらも、キャッチーな歌メロに絶妙なボーカルハーモニーを乗せる、彼独特の個性は常にハードロックシーンを牽引して来たと言えますね。
同時に、Jeff はオフィシャルメンバーとしてではなく、ゲスト的な立ち位置で素晴らしい作品に貢献し続けた引く手あまたな人物でもあります。Axel Rudi Pell, Alex Masi, Vinnie Vincent, TAKARA などの名作群を懐かしく思うファンも多いでしょう。
80年代に、世界で勝負したマスクマン、日本人ギタリスト Kuni の 2nd アルバム “Lookin’ For Action” も、彼の参加でグレードが上がったアルバムの1枚です。
Billy Sheehan をはじめ、多数の豪華なゲストとともに制作されたデビュー作 “Masque” とは一味違い、固定されたメンバーで勝負した作品で、SLAUGHTER の秀才 Dana Strum プロデュースの下、Jeff のソウルフルな歌唱は勿論、Kuni のツボを得たフレージングの良さ、B’z でもお馴染み Mike Terrana のキレの良いドラムスを味わうことが出来る秀作でしたね。
そして今回、Kuni のデビュー30周年を祝い Loud Park 16 出演が決定、Jeff の参加もアナウンスされました。メンバーは、Kuni, Jeff に加えて GREAT WHITE の Tony Montana, HAREM SCAREM でお馴染み Darren Smith と実に豪華。素晴らしいショーになることでしょう。
今回インタビューを行った Jeff にとっては何と23年振りの来日となります。23年!最後の来日は、1993年の TALISMAN 初来日まで遡らなければなりません。しかし、インタビューで Jeff が語ってくれた通り、TALISMAN の音楽はその長い期間、世代を超えて引き継ぐべきものだと思います。
今は亡き Marcel Jacob というベースの名手にして優れた作曲家が存在したこと、Jeff と Marcel の素晴らしきケミストリー、爽快で、キャッチーで、ファンキーで、複雑なサウンド、その全てが忘れ去られてしまうには惜し過ぎると感じています。Jeff はインタビューで、意外にも Marcel 抜きの TALISMAN の未来に前向きな発言をしてくれました。勿論、ファンにはビッグニュースでしょうし、キッズのためにもぜひ実現してほしいと思います。
また同時に、彼自身の新しいバンド SOTO にも強く力を入れていることが伝わりますね。個人的な感想を述べれば、SOTO の新作 “Divak” はダークでヘヴィー、確かに若干メロディーが弱いものの、楽器陣が想像以上にテクニシャン揃いで、これからの活動に期待が出来そうです。今回の来日が契機となり、TALISMAN や SOTO でも、再度彼の姿を日本で見ることが出来るようになるかも知れませんね!
Jeff は Yngwie との現在の関係についても語ってくれました。メロディックハードの歴史の登場です。どうぞ!!
続きを読む EXCLUSIVE INTERVIEW 【JEFF SCOTT SOTO : TALISMAN, KUNI, SOTO】LOUD PARK 2016 SPECIAL !!