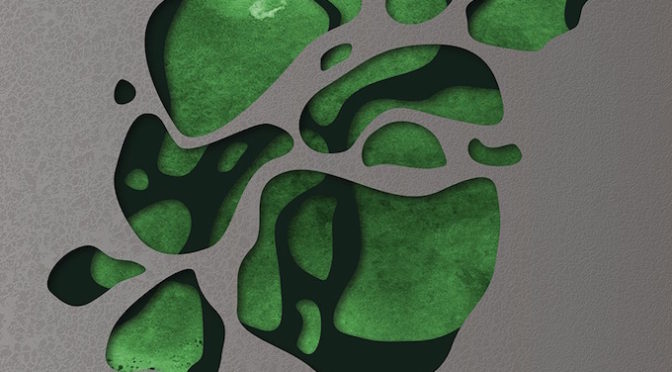EXCLUSIVE: INTERVIEW WITH SARAH LONGFIELD !!
“I’m Just So Happy To See It Getting Normalized. I Remember Starting Out There Were No Women On YouTube Or The Guitar Community, Which Was Always Disheartening.”
DISC REVIEW “DISPARITY”
Fender が行った調査によると、近年新たにギターを始める人の半数が女性であるそうです。その傾向を裏付けるように、Yvette Young, Nita Strauss, Orianthi Panagaris などテクニカルなロックやメタルの世界においてもギターヒロインの存在感、輝きは増す一方だと言えるでしょう。
Sarah Longfield。仄暗く凍える湖と森を抱くアメリカ中西部の最北、ウィスコンシンから登場した25歳の美姫は、さながらギターシーンのジャンヌダルクなのかも知れませんね。
2016年、Guitar World 誌による “世界最高の7弦、8弦ギタープレイヤー15人” の中に選された革新のハイテクニックビューティーは、驚くべきことにチャンネル登録者数20万を超える人気 YouTuber でもあるのです。(Rob Scallon とのコラボレートの数々は秀逸)
「マルチなプラットフォームを築き、ミュージックコミュニティーの様々な側面で名前が売れることは、素晴らしいプロモーションにもなって来たのよ。」と Sarah が語るように、ソロ活動、バンド THE FINE CONSTANT、そして YouTube と新世代らしく現代的なプラットフォームを意欲的に活用することで、彼女は Season of Mist との契約を手にすることになりました。
インタビューで、「私はまずピアノを8歳の時に始めて、それからヴァイオリンを10歳の時に始めたの。遂にギターを手にしたのは12歳の時だったわね。」と語るようにその音楽的素養は実に深くそして多様。弊誌に何度か登場している Yvette Young が似たようなバックグラウンドを持つことも興味深いシンクロニシティーではないでしょうか。
魔女か英雄か。さらにはチェロ、パーカッションまで嗜む才女のエクレクティックな素養とオープンマインドは、メタルの様式、伝統、アグレッションを地図にない未踏の領域へと導くのです。
「最新作は実際、前作とは全く異なるアルバムになったわね。焦点がよりオーガニックなマテリアルにシフトされ、私の持つ様々な影響を探求することが出来るようになったのよ。」 と語る Sarah。つまり、不均衡や差異を意味するタイトルを冠した最新作 “Disparity” は、遂に彼女本来の魅力を余す事なく伝えるマイルストーンに仕上がったと言えるはずです。
人生で初めて手にしたピアノの響きをイントロダクションに、幽玄荘厳、夢見がちでアトモスフェリックな独特の世界はその幕を開けます。”Embracing Solace”。慰めを抱擁する。プログレッシブなデザインからエレクトロニカの実験にジャズの恍惚まで、全てをシームレスに、壮麗優美に、そして時に幽冥に奏でるサウンドスケープは実にユニークかつ濃密。
Kate Bush を想起させる嫋やかな Sarah 自身のボーカルとエモーションを増したギター捌きの相性も極上。自らの音楽旅行を通して経験した光と影はこうして楽曲、作品へと見事に投影されて行きます。
ANIMALS AS LEADERS のショウを見た翌日に書かれたという、ヘヴィーでマスマティカルなデジタルのルーツを探求する “Cataclysm” が Tech-metal、ギターナードの心を激しく打つ一方で、”Departure” のオリエンタルな情緒や “Citrine” のオーガニックなポストロックの音景、”Miro” のアヴァンギャルドなジャズ精神は、二胡やハープ、サクスフォンの導入も相俟って、リスナーをカラフルで刺激的な非日常の絶景へと誘うのです。
今回弊誌では、Sarah Longfield にインタビューを行うことが出来ました。「私は女の子がギターをプレイすることがいたって普通な世の中になってただ本当に嬉しいのよ。」ウィスコンシンの乙女は果たして高潔か異端か。それは歴史が語るでしょう。どうぞ!!
SARAH LONGFIELD “DISPARITY” : 9.9/10
続きを読む NEW DISC REVIEW + INTERVIEW 【SARAH LONGFIELD : DISPARITY】