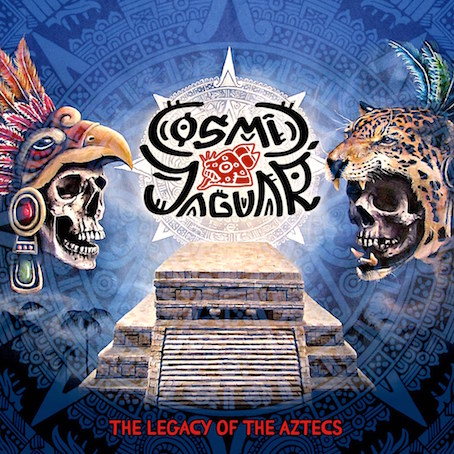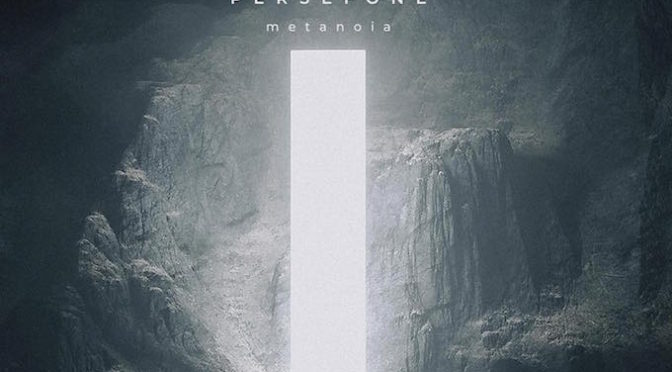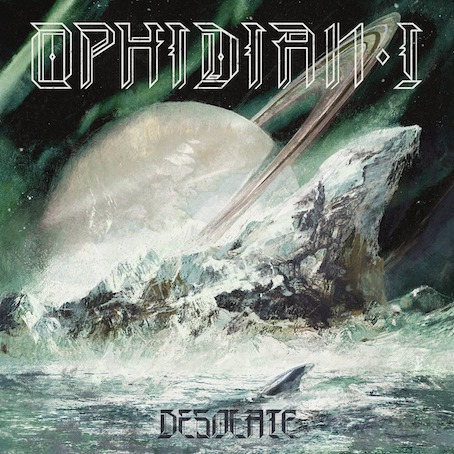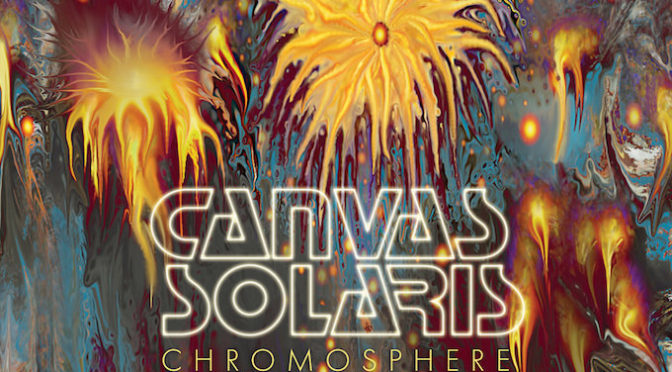COVER STORY : BERRIED ALIVE “BERRIED TRASURE”
“Balenciaga Or Moschino Are Great Examples In Fashion For Being Incredibly Technical Clothing That Doesn’t Take Itself Too Seriously. That’s Really What We Want The Most In Music, To Connect With People.”
BERRIED TREASURE
「Charles Caswell というギタリストがいる。彼は奥さんと BERRIED ALIVE というデュオをやっている。彼は、私が今まで聴いた中で最もクレイジーなギターを弾いている。彼のプレイスタイルは、私がこれまで聴いた中で最も速いプレイヤーなんだ」
ギターレジェンド Joe Satriani がこれほど興奮して紹介するギタリスト。その人物が凡庸なはずはありません。そして当然、世界中が注目します。そのギタリストとは、BERRIED ALIVE というデュオでの活動で知られる Charles Caswell です。
BERRIED ALIVE は、Charles と妻の Kaylie Caswell によるデュオ。彼らのジャンルを説明するのは少し難しいかもしれません。一応、彼らのウェブサイトには、”トラップ、ハードロック、メタル、ヒップホップ、アバンギャルドの要素を取り入れたEDMポップ” のようなものだと書かれています。
Satriani は興味深い比較をしながら、こう付け加えました。
「BERRIED ALIVE の音楽は、Tosin Abasi とかと同じくらい複雑だ。しかし、彼が何を選択し、どのように作曲するのか…それは他の誰とも違っている。人生は挑戦だ。そうして若いギタリストたちは、今この現代を生きることがどういうことなのか、私たちに教えてくれているんだ。美しいことだよ。インスタグラムを見に行って、スマホの前で誰かが僕が弾けないものを弾いているのを見るたびに、”やったー!” って思うんだ。誰かがギターを前に進めているんだからね!」
Satriani の賛辞に、Charles も応えます。
「Joe Satriani は偉大なレジェンドだ。僕が初めてギターを手にして “Surfing With The Alien” を弾いて以来、多大なインスピレーションを受けてきた人物からこんな優しい言葉をかけてもらえるなんて、信じられないほどうれしくて勇気づけられるよ!」
BERRIED ALIVE の芸術的な活動は、2012年に “音楽ベンチャー” という冒険的な形態で始まりました。それ以来、2人はレコードやシングルを精力的にリリースしています。現在までに、BERRIED ALIVE のカタログは、7枚のスタジオ・アルバムと30枚以上のシングルにまで及んでいるのです。その音楽はたしかに、トラップ、ハードロック、メタル、ヒップホップ、アヴァンギャルドの要素を取り入れたEDMポップという表現がぴったりなのかもしれません。バンドの大胆不敵で感染力のある楽曲、まばゆいばかりの音楽性、そしてシアトリカルなセンスは、YouTubeの総再生回数950万回、Spotifyのリスナー数12万人以上という数字に直結し、多くのリスナーを魅了しています。そして、Satriani のみならず、RAGE AGAINST THE MACHINE の Tom Morello, AVENGED SEVENFOLD の Synyster Gates, MOTLEY CRUE の Tommy Lee といったアイコンたちからの喝采までも集めているのです。
「僕たちは普段、いつもギターを弾いているわけでもなく、ただ好きな音を見つけているだけなんだ。ギターで音を模倣する方法を学んだから、音を見つけたら、それがどんな音なのか、たとえクレイジーな音のドラムか何かであっても、それを自分なりに再現することができる。
自分自身や自分たちに対して批判的になるのは好きではないんだ。厳しいやり方は健康的じゃない。僕はギターに3時間、ボーカルに3時間、作曲に2、3時間、マーチャンダイズやソーシャルメディアに2、3時間といった具合に。グッズの注文もすべてこなさなければならない。ギターを弾いているだけじゃなく、何かを作り、リハーサルをし、人々とつながる。運動などで心身の健康に気を配りながらね。1日の中で少しずつでもすべてのことをやっていれば、終わる頃にはかなり満足感があるし、自分を過小評価しなかったように感じる」
重要なのは、彼らがただ驚異的で “リディキュラス” なバンドであるだけでなく、”音楽ベンチャー” という形態をとっている点でしょう。BERRIED ALIVE は、冒険的な音楽と多感覚的なグッズの厳選された世界を構築していて、最近ではビール会社との提携までも行っています。
「空港のレンタカーで、カウンターのお姉さんにおすすめのお店を聞いたんだ。彼女は Heathen Brewing を勧めてくれた。料理も雰囲気もビールも気に入った。数年後、彼らから連絡があり、ビールのコラボをしないかと誘われた。僕たちは彼らの醸造所で会い、数ヶ月かけてすべてのロジスティクスを考え、ビールを造った。かなりクレイジーだったよ!
乳糖を混ぜて、ろ過した後の穀物をすくい取って…僕たちがワインやシャンパンが好きだと知っていたので、自家ぶどう園のぶどうを収穫してくれて、自家栽培のぶどうを使うことができた!醸造所の文化にも本当に感化されたね。みんな協力し合い、助け合うことを厭わないから、僕が音楽の世界で経験してきたことと比べると新鮮だ。Heathen とも将来的にもっとコラボできる可能性がある。そこから生まれたビールの名前が、アルバム “The Mixgrape” にちなんでいるんだ」
マーケティング用語で言えば、BERRIED ALIVE 社は気まぐれでカラフルなライフスタイル・ブランドであり、彼らが提供する商品メニューは拡大し続けているのです。ただし、創業者である Caswell 夫妻は、それほど計算高くはありません。ジャンルにとらわれない音楽、遊び心がありながらも高級感のある服、巧みなマーケティングのアイデアの裏には、自由奔放な芸術的対話がつねにあります。
「僕たちは聴かれて、着られて、berry だけに味あわれるものなんだ (笑) 。すべての感覚にクリエイティブなものを提供したいんだよ!最近、友人が DEFTONES のコンサートに行ったとき、少なくとも10人以上の人が BERRIED ALIVE のグッズを身に着けていて、とても目立つから気づいたと言われてね。たしかに目立つ!僕たちはあまり外に出ないから、反響を知るのはとても楽しいよ」
BERRIED ALIVE の服は明るくポップで遊び心があり、常に人気のあるイチゴと十字架のデザインがトレードマークです。Supreme を彷彿とさせる高級ストリートウェア・ラインとして作られていますが、それは夫妻の甘く歪んだ心と密接に結びついているのです。
2人は、曲作り、服のデザイン、商品ラインにそれぞれ意見を出しながら、流れるようにいつも一緒に創作しています。Charles は、BERRIED ALIVE の楽曲のプロデュース、ミックス、マスタリングを担当し、ブランドとバンドの予算を洋服や没入型ビデオ、将来の作品に充て、Kaylie が歌詞、服のデザイン、ベースラインを担当し、一緒にマーケティング・コンセプトを考えています。実は、そうした阿吽の呼吸には確固たる理由がありました。
BERRIED ALIVE の幻想的な世界のはじまりは、おとぎ話のような出会いにまでさかのぼります。2人が出会ったのは中学1年生のときでしたが、付き合い始めたのは高校に入ってからでした。付き合い始めて早々、Charles は Kaylie がファッションの溢れんばかりの才能と適性を持っていることに気づいたのです。
当時、Charles はバンドやツアーで演奏するテック・メタル・ギターの魔術師 (あの REFLECTIONS にも在籍していた) でしたが、バンドでのドラマや苦労から離れ、孤独なアーティストへと進化していきました。そんな中で、BERRIED ALIVE という音楽団体は当初、Kaylie が提案したサイドプロジェクトのようなものだったのです。
「名前は当時のメタル界にあったダークな名前をもじったダジャレのようなものだったわ。私は芸術としての服がずっと好きだったの。私たちは本当に小さな町の出身で、そこではみんな同じような服を着ていた。そこで私が着ている服について人々が話しているのを耳にすることがあって、それは必ずしも良いことばかりではなかったのよね。でも、服装は自己表現で、人と話す前にその人について知ることができる大事なアイデンティティ。同時に、いつでも脱ぐことができる、表面的なものでもある」
2人の美学はやがて融合し、既存のバンドTシャツを超えたユニークな商品ラインを開発しようと試みます。これが BERRIED ALIVE のアパレル・ラインとなっていきました。彼らがこだわるのは、”深刻になりすぎないこと”。
「僕たちがやっていることはとても深い要素を持っているけど、決して深刻に考えすぎることはない。深刻になりすぎると、どんなメッセージや音楽からも命が吸い取られてしまうと思うからね。それをうまくやっている芸術は他にもあるよ。ドラマを見ても笑える瞬間があるし、漫画を見ても絵が美しいと思う一方で笑ってしまう。
バレンシアガやモスキーノは、ファッションの世界では信じられないほどテクニカルな服でありながら、深刻になりすぎず、時には派手であることに感動するという素晴らしい例だね。派手でありたいときもあれば、ソフトでありたいときもある。それが僕たちが一番望んでいることで、結局は人々とつながりたいんだよ」
そうして今日に至るまで、BERRIED ALIVE は、ビジョンを持ち、それを追求するために努力した2人のマーケティング能力によって、自立したビジネスとなっています。彼らの成功はすべて、直感と芸術的ビジョンに基づくもの。
「レコード・レーベルを持ち、ツアーをするという伝統的な道を歩むことなく、自分たちの夢を叶えることができたのは、大きな成果だと思っているよ。僕たちが一緒にこの仕事をできるのはとても意義深いことだし、フルタイムの仕事になったのはとても特別なこと。とても感謝しているんだ」
実際、Charles がかつてのようにツアーとレコーディングで疲弊するメインストリームの音楽業界にまだいたとしたら、彼らの夢は叶わなかったでしょう。
「あのころ僕はツアー生活をしていて、いつも大事なものから離れていて、自分のベッドで寝たことがなかった。”Melon-choly” は、”スマホを見ながら、君に電話できたらいいなと思う” という一節から始まったんだけど、この曲を書いたとき、その生活の大変な部分をたくさん思い出していたんだ。
今はインターネットがあるから、内向的な人や、何らかの理由で家族と家にいなければならない人でも、アートを作ったり音楽を作ったりできる方法がある。ある意味 DIY でパンクだよね。Kaylie はヴィヴィアン・ウエストウッドが大好きなんだ (笑)。
僕もパンク・ロックがきっかけでギターを弾くようになった。そうやって楽器を愛するようになったし、ルールなんてクソくらえで、みんながやれと言うことの反対をやればいいんだと学んだ。それが BERRIED ALIVE の本質なんだ!僕たちがツアーやライブをやらないことは、ギター界の門番たちを怒らせた。でも僕たちは気にしていないし、それは何の問題にもなっていない」
結局、彼らが求めるのは好きな人たちとつながること。
「ギター世界を敵に回してもかまわないさ。僕らがレコーディングしたものをスピードアップしてるなんていう陰謀論者のいる世界なんだから (笑) 。ボブ・ディランじゃないけど “Go Where They’re Not”。年々、それが身に染みていると思う。僕はただ、歌がうまくなること、より強力な曲を書くこと、そして人々とつながることに集中するようにしている。目標のひとつは、音楽が上手になることとは関係ないレベルで、もっと多くの人とつながろうとすることだ。以前はCNCの機械工で、調剤薬局でも働いていたんだけど音楽とはまったく関係のない、信じられないほどクールな人たちによく会ったよ。音楽の趣味よりも、性格が一致する方が話したいと思うんだよな」
とはいえ、Charles はギターに対する情熱をなくしたわけではありません。
「スタイルは本当に様々。とてもアバンギャルドなんだ。頭の中にアイデアが浮かんだら、それを演奏できるようにするためにまったく新しいテクニックを編み出さなければならないこともある。ある日は超クレイジーなテクニックを駆使した曲を書き、次の日はアコースティックで伝統的な構成のシンガーソングライターの曲を演奏する。完全に自由な表現なんだよ。
ギターや音楽に何か新しいものをもたらすことは、僕にとって本当に重要なことなので、作曲や練習をするときは、今まであまり見たり聴いたりしたことのないようなものになるよう最善を尽くす。そうすることで、より多くの人に聴いてもらえるから。僕は自分の音楽にできる限りの価値を込めたいと思っている。そのためには、楽器をいじったり、練習したり、プロデュース・スキルを磨いたりすることが必要なんだ」
そして、音楽世界を改革し続けることにも熱心です。
「僕たちはエルトン・ジョンが大好きで、マーチャンダイジングをしながらよく聴いているよ。それから SPARKS!僕が彼らにインスパイアされたのは、80年代、もしかしたら70年代後半かもしれないけれど、彼らが自分でレコーディングする方法を学んだからなんだ。当時は前代未聞だった。今では誰でもできる。でも、そんな前例がなかった時代に努力を重ねたことは先進的だし、今もそれを続けているのは超クールだよ!
彼らは自分たちを改革し続けている。何年もかけて、いろんなフェーズやスタイルを作り上げてきた。Jimi Hendrix もそう。彼がギターで話すことに興味を持たせてくれた。それかOzzy Osbourne, PANTERA, BLACK SABBATH でメタルにのめり込んだ。今はあまり音楽を聴いていなくて、オーディオブックや瞑想的なものを聴いている。友人の曲がリリースされたときなどはチェックするけど、ほとんどは頭の中でクレイジーなものを作っているだけだよ!(笑)」
彼らの理想の音楽世界には、エゴも嫉妬も憂鬱もありません。
「僕たちは自分たちが世界最高のギタリストであることを証明したいわけじゃない。もし普通の仕事に戻らなくてはならなくなったとしても、僕らが作る音楽に十二分に満足しているし、お金を稼ぐためにそれを変えようとは思わないから、全然平気だよ。お金儲けのために自分たちの音楽を変えようとは思わない。
自分たちがやっていることにとてもポジティブなメッセージを持つようにしている。そしてみんなにも、自分たちがやっていることが何であれ、自分たちの芸術性や創造性だけで十分だと感じてほしいんだ。メタル世界では、ポジティブであることは一般的ではないけれど、それが僕たちの気持ちなんだよ」
では、BERRIED ALIVE にとっての “成功” とは?
「”ヒーローが友達になったとき、お前は到達したんだ “って父が言っていた。それは究極の成功だ。そもそも自分がやっていることをやりたいと思わせてくれた誰かに認められることがね。
そうしたサポートは、誰かにひどいことを言われたとしても、それを帳消しにしてくれる。最小限のストレスの中で、アートを通して自分たちを維持できることだけが望んでいたことなんだ。誰が見ているかわからないし、誰とつながるかもわからない。数年前には、こんな人生になるとは想像もしていなかったからね!」