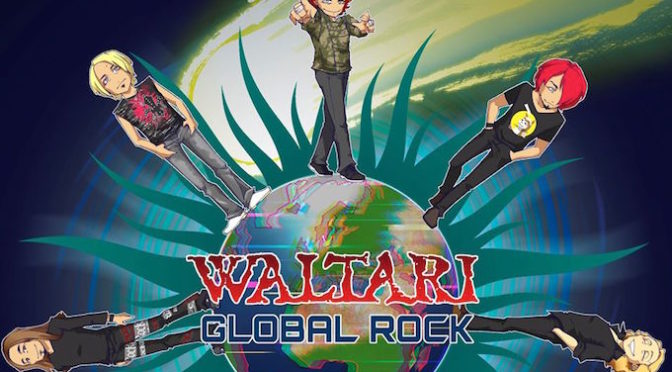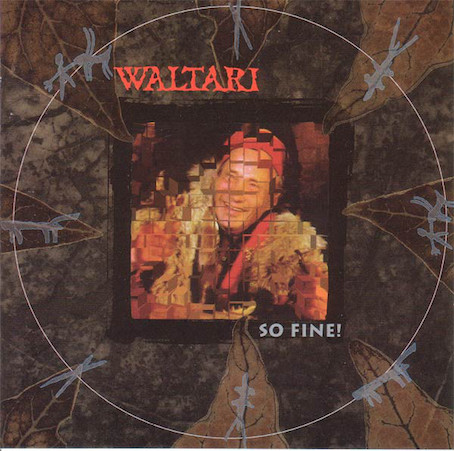EXCLUSIVE: INTERVIEW WITH KÄRTSY HATAKKA OF WALTARI !!
“Let’s Keep The Rock Tradition Alive And Reform It In a Brand New Way Suitable For 2020, And The People Living This Life Here And Now!”
DISC REVIEW “GLOBAL ROCK”
「スカンジナビアのバンドたちは、より幅広いスペクトルの音楽を聴くことで、メタルに “クレイジーさ” を加えていったんだ。そしてしばらくすると、突如として、”ポストファーストメタルタイム” のバンドたちは “ベーシックメタル” のバンドたちを後方に残し、素晴らしく花開いたんだ。」
メタルが多様なスペクトルに枝葉を伸ばし始めた90年代初頭、フィンランドから示現した WALTARI の千変万化でカメレオンの虹彩はまさにポストファーストメタルタイムの象徴でした。
同じアルバムは2枚作らないと語るように、WALTARI はレコードを通じて様々な冒険を行っていきました。”Yeah! Yeah! Die! Die” ではオーケストラとデス/スラッシュメタルの完璧なる邂逅を持たらし、”Space Avenue” ではエレクトロインダストリアルに振り切ったサウンドで周囲を圧倒。素晴らしき “Blood Sample”, “Release Date” といった近年の比較的、普遍なモダンメタルへと接近した作風の中にさえ、煌めくような驚きの瞬間は星の数ほど散りばめられているのですから。
「ロックの伝統を生かしながら、2020年に適した形でリフォームしようじゃないか、だって僕たちは今この時を生きているんだから!それこそがロックに活力を与え、僕たち全員にとって意味のあることなんだ。ロックのアティテュードとは、オープンマインドかつ予測不可能な純粋さだからね!」
あの眩しきメタル革命から30年。WALTARI の首領 Kärtsy Hatakka の主張は今でも一貫しています。端的に言えば温故知新のスピリット。伝統を守りながら時代に即した再構築を促し、自らが先頭に立って “オープンマインドで予測不能な” ロックの純粋なアティテュードを体現しているのです。
「実は、僕たちはいつも自らの音楽がとても “アニメ的” だと感じていたんだよ。だから、日本ツアーの後に Tomo を見つけることができたのはとても素晴らしい出来事だったね。何せ彼女はとても才能があるからね!」
自らの音楽を “アニメ的” と形容したのは、そのやはり予想不可能かつ非現実的な音の葉ゆえでしょうか。最新作 “Global Rock” には、日本のアーティスト Tomo Kataoka の手によるアニメ的なアートワークが採用されています。メンバーが輪になって、「世界各地の人々や伝統と繋がる」その青々としたイメージは、レコードのスピリットを完膚なきまでに反映しているのです。
既存の “ポストロック” のイメージとは遠く離れた、サウンドエフェクトと重低音のメロディックな邂逅、WALTARI 流 “Post Rock” で幕を開けるアルバムは、実際、メタルとロックを基盤にパンク、ファンク、テクノ、ポップ、ヒップホップ、カントリー、エスニックで世界を巡る旅路です。
“Metal Soul” で自らの出自とシュレッドのギター爆撃を敢行したバンドは、コンテンポラリーなヒップホップを抱きしめる “Skyline” や、Post Malone のオマージュと言及する “Boots” で Kärtsy 語るところの “ジェネリックポップ” が大多数のリスナーを惹きつける理由を探求していきます。それはまさしく音故知新。生き残るために再構築し、現代の水で磨きあげたロックのニューチャプター。BRING ME THE HORIZON の “Amo” を愛聴している事実も象徴的ですね。
一方で、FAITH NO MORE のオルタナティブをメタル的に解釈する “The Way” や “No Sacrifice”、カントリーとエクストリームミュージックの不可思議なキメラ “Orleans”、さらに CANNED HEAT のカバーまで、彼らはクロスオーバーの源流としてその誇らしき多様の旗を空高く掲げつつ、勇敢な音のメルティングポットを見せつけていくのです。
「この世界で生き残るためには、僕たち全員が力を合わせなければならないから。」厄災の時代に WALTARI は、奇しくも時空を超えて世界と音楽で繋がりました。
「金銭的には、僕のようなすべてのフリーランサーにとってまさに地獄だよ。何しろ、稼ぎの元であるライブができないんだからね。だけど、自然には祝福されているように感じるね。だから、この危機からポジティブな面を見つけていかなければならないよね。」
音の百鬼夜行にばかり注目が集まりがちな WALTARI ですが、不安や孤独、現代社会に対する嘆きを独自のアイロニーを交えつつ珠玉の旋律へと変換する Kärtsy は旋律と宣律を誰よりも巧みに操るフロントマンです。彼が見つけた道を切り開く方法とは、きっと繋がり進み続けること。今回弊誌では、鬼才に2度目のインタビューを行うことができました。「日本人はロックの再構築を常にかなりよく理解していて、いつもプログレッシブになりたいと考えている。BABYMETAL のような (アイドル的) アクトについてさえね!」どうぞ!!