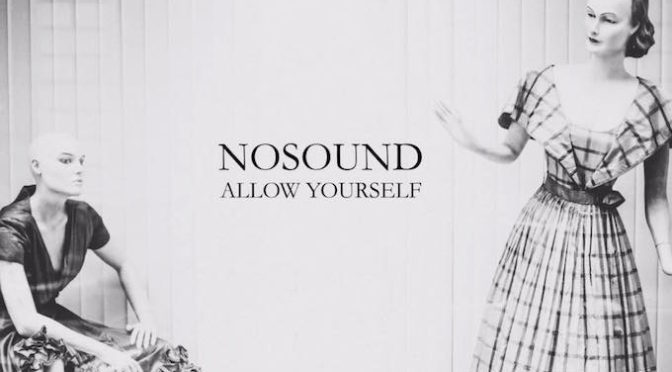EXCLUSIVE: INTERVIEW WITH STEFAN NORGREN OF SEVENTH WONDER !!
“We All Supported Tommy Karevik 100%! Off Course, We All Realized That They’d Come First And That This Would Inevitably Set Us Back Time Wise. But There Was No Way Any Of Us Would Get In The Way Of Such a Great Career Move For Him.”
DISC REVIEW “TIARA”
スウェーデンで毎年行われる “一番大切な冬の行事”、聖ルシア祭。貧しい人々に財産全てを提供した純粋の象徴、光の聖人聖ルチアの姿は、そのスウェーデンに居を置くプログメタルの至心 SEVENTH WONDER と不思議に重なるのかも知れません。
“Waiting in the Wings” でその鵬翼を広げたバンドは、“Mercy Falls” で悲劇的なサスペンスを描き切り、“The Great Escape” では30分のエピックと共に喪失、失楽からの大いなる逃避による微かな希望の灯火を見出して来ました。
「難解なセクションも音楽的に実りがなければ僕にとっては的外れなんだ。だからこそ、メロディーとアトモスフィアが必要なんだけどね。」新加入のドラマーにして現在はバンドのスポークスマン的な役割を務める Stefan Norgren の言葉は真実です。
何より、しばしば DREAM THEATER が引き合いに出されるほどのハイテクニックと緻密なデザインの二重奏を奏でながら、SEVENTH WONDER はスカンジナビアの澄み切った眺望を旋律のクリスタルに封じ込めて来たのですから。そうしてそのパノラマは常に映画のように壮大なストーリーを纏ってリスナーの感情を激しく喚起するのです。
8年という長い月日を経てリリースされた最新作 “Tiara” のストーリーは、もしかするとバンド自体の影法師と言えるのかも知れませんね。滅ぶべき運命にある地球が救いを求め “The Everones” に差し出す純粋無垢の象徴、少女 “Tiara”。そのあらすじに、不世出のボーカル Tommy Karevik の KAMELOT 加入を重ねたファンも多いでしょう。
もちろん、Stefan はインタビューで Tommy の “ダブルワーク” がある程度 Win-Win な状況であることを強調しています。ただし、今でも Roy Khan の亡霊を宿し歌唱をシンフォニックに限定される KAMELOT での活動に、彼本来の姿を知るリスナーの多くが歯痒い思いをしていることも事実です。
実際、”Tiara” での Tommy は不要の責任から解放され自由を謳歌しているようにも思えます。自らに宿る全てのレンジでオクターブの山脈を超え、感情のリミットを解放しながら様々なキャラクターを演じ分けるその絶対的なパフォーマンスはまさに水を得た魚。
よりゴージャスでロックオペラの佇まいを擁する “Tiara”。中でも “Tiara” が別れを告げる “Farewell” 三部作はマスタークラスのバンドと Tommy の開眼が最高レベルでシンクロを果たした絶景と言えるでしょう。
シンセの煌めき、理知的な変拍子、メタルらしいエッジとユニゾンの醍醐味、静と動のダイナミズム、躍動するアコースティック楽器にヴァイオリン、暖かいコーラスの絨毯、Tommy と妹 Jenny との甘やかなデュエット、そして何よりエモーション極まる極上のメロディー。少なくとも、ピュアなプログメタルに求めるものは全てがここに存在します。
同時に、”Arrival” でシンフォニックに幕を開けるアルバムは、”The Everones” のスリリングなボコーダー、”Truth” で見せるベースの妙義とフォルクローレの熱情、“By the Light of the Funeral Pyres” はロックマンの8-bitでしょうか、そしてジェットコースターのエピック “Exhale” までバラエティーに富み、新機軸とチャレンジに満ち溢れています。
「さてその結末は?それはアルバムを聴いて、歌詞を読んで自らで決めて欲しいね…。」では、Tommy と SEVENTH WONDER の物語はどのような結末を迎えるのでしょうか。少なくとも、”Tiara” が DREAM THEATER や SYMPHONY X、そして SHADOW GALLERY を愛し続けて来たここ日本で歓迎されるべき作品であることは確かです。
今回弊誌では、Stefan Norgren にインタビューを行うことが出来ました。「テクニック、メロディー、アトモスフィア…それは僕たちのような音楽を生み出す時、心に留めている素晴らしいキーワードなんだよ。」全てのメタルファンに送る素晴らしき SF 叙事詩。どうぞ!!