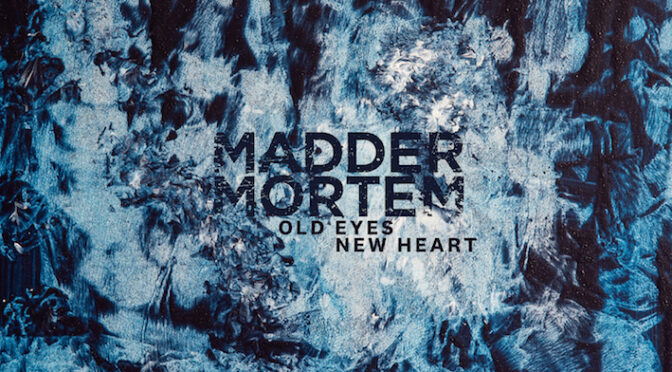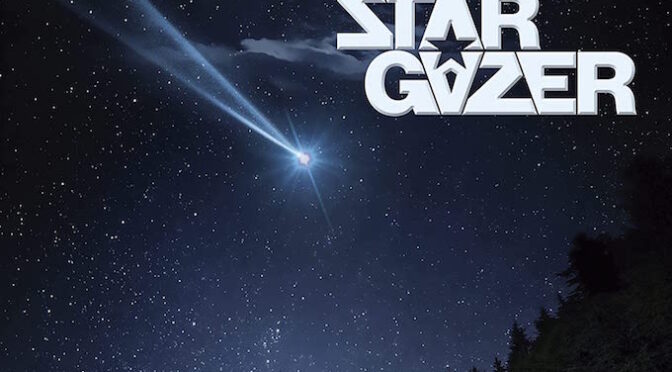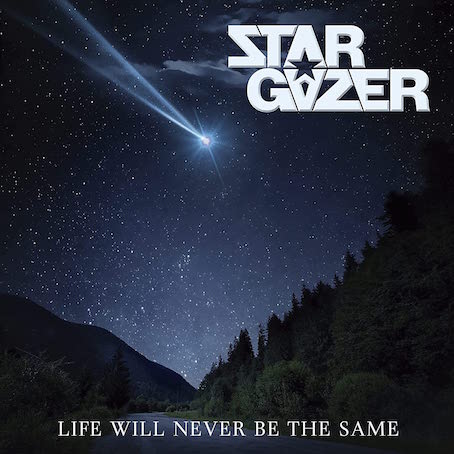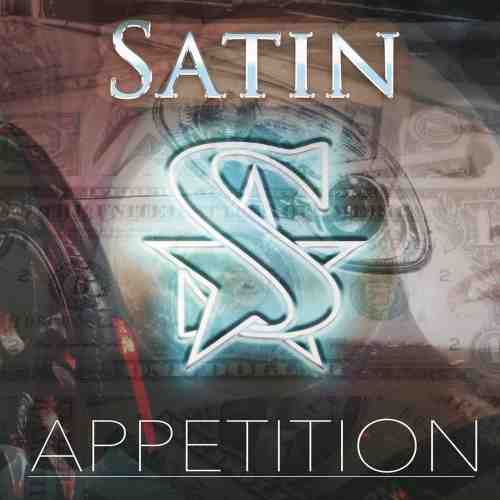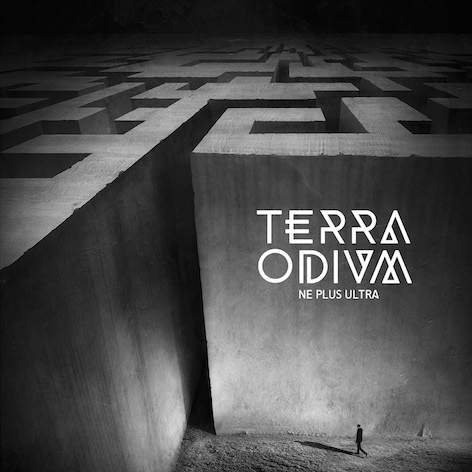EXCLUSIVE: INTERVIEW WITH ANDREAS WETTERGREEN OF THE CHRONICLES OF FATHER ROBIN !!
“We Think It’s Sad If Someone Wants To Live And Express Themselves Only Through «New Formulas» And Dogmatic Only Seek To Do Something That No One Has Done Before. Then You Forget History And The Evolution Of Things, Which In Our Opinion Is At The Core Of Human Existence.”
DISC REVIEW “THE SONGS & TALES OF AIROEA – BOOK Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ“
「最初は若いワインのように最初は有望で実り豊かなバンドだったけど、やがて複雑さを増し、私たち集団の心の奥底にある濁った深みで数年間熟成され、エレジオンの森のオーク樽で熟成されたとき、ついにそのポテンシャルを完全に発揮することになったのさ」
アルバムの制作に長い時間をかけるバンドは少なくありませんが、それでも30年を超える月日を作品に費やすアーティストはほとんど前代未聞でしょう。ノルウェー・プログの粋を集めた THE CHRONICLES OF FATHER ROBIN は、ロビン神父の数奇なる物語に自分たちの人生や経験を重ね合わせ、四半世紀以上かけてついに壮大な3部作を完成させました。
「90年代に親が着ていた70年代の古着に身を包み、髪を伸ばし、1967年から1977年の音楽ばかりを聴いていたんだ。当時のポップ・ミュージックやポップ・カルチャー・シーンにはとても否定的で、RUSH や YES, そして DOORS の音楽は、例えば RED HOT CHILLI PEPPERS や RAGE AGAINST THE MACHINE, NEW KIDS ON THE BLOCK など他のバンドが聴いている音楽よりもずっと聴き応えがあると、パーティーで長い間議論していたほどでね。私たちは、自分たちが他人よりより高い位置にいると確信し、できるだけ多くの “失われた魂” を救おうとしていたんだ。だけどそれからしばらくして、私たちは他人がどう思うかとか、彼らが何に夢中になっているかということに疲れ、ただ自分たちの興味と、ミュージシャンとして、バンドとしての成長にエネルギーを集中させていくことにした」
70年代が終焉を告げて以来、プログレッシブ・ロックはつねに大衆から切り離された場所にありました。だからこそ、プログの世界に立ち入りし者たちはある種の特権意識に目覚め、あまつさえ大衆の啓蒙を望む者まで存在します。90年代のカルチャーに馴染めなかった TCOFR のメンバーたちも当初はカウンター・カルチャーとしてのプログに惹かれていましたが、しかしワインのように熟成され、長い年月を重ねるにつれて、ただ自分たちが夢中になれる音楽を創造する “道” へと進んでいきました。
3部作のコンセプト最初の芽は、民話、神話、幻想文学、サイケデリア、冒険的な音楽に共通の興味を持つ10代の仲間から生まれ、最新の発見を紹介し合ううち、徐々にノルウェーの仲間たちは独自の糸を紡ぎ、パッチワークやレンガのように新たな色彩や経験を積み重ねるようになりました。それは30年もの長きにわたる壮大なブレイン・ストーミング。
「確かに、私たちはプログ・ロックの穴を深く這いずり回ってきたけど、クラシック・ロック、フォーク・ロック、サイケ、ジャズ、クラシック音楽、エスニック、ボサノヴァ、アンビエント・エレクトロニック・ミュージックなどを聴くのをやめたことはない。たとえ自分たちが地球上で最後の人間になったとしても、こうした音楽を演奏するだろう。私たちは、お金や “大衆” からの評価のために音楽をやったことはない。もちろん、レコードをリリースして夢を実現できるだけのお金を稼ぎたいとは思っているけど、どんなジャンルに属するものであれ、音楽を通じて自分たちの考えや感情を顕在化させることが最も重要であり、これからもそうあり続けるだろう。そしてそれこそが、極めてプログレッシブなことだと私たちは考えているんだ」
WOBBLER, WHITE WILLOW, Tusmørke, Jordsjø, IN LINGUA MORTUA, SAMUEL JACKSON 5など、ノルウェーの実験的でプログレッシブなバンドのアーティストが一堂に会した TCOFR は、しかしプログレッシブ・ロックの真髄をその複雑さや華麗なファンタジーではなく、個性や感情を顕在化させることだと言い切ります。
とはいえ、プログの歴史が積み重ねたステレオタイプやクリシェを否定しているわけではありません。学問もアートもすべては積み重ねから生まれるもの。彼らは先人たちが残したプログの書を読み漁り、学び、身につけてそこからさらに自分たちの “クロニクル” を書き加えようとしているのです。
表現力豊かな和声のカデンツ、絶え間なく変化するキーボードの華やかさ、ジャンキーなテンポ、蛇行するギター・セクションの間で、TCOFR の音楽は常に注意力を翻弄し、ドーパミンの過剰分泌を促します。ここにある TCOFR の狂気はまちがいなく、ノルウェーにおける温故知新のプログ・ルネサンスの成果であり、大衆やトレンドから遠すぎる場所にあるがゆえに、大衆やトレンドを巻き込むことを期待させるアートの要塞であり蔵から発掘された奇跡の古酒なのです。
今回弊誌では、WOBBLER でも活躍する Andreas Wettergreen にインタビューを行うことができました。「芸術の発展は、決して1969年の “In The Court of the Crimson King” やバッハのミサ曲ロ短調から始まったわけではない。芸術と芸術を通した人間の表現力は非常に長い間続いており、それは何世紀にもわたって展開し続けている。イタリアの作曲家カルロス・ゲスアルドは、16世紀に複雑で半音階的な難解な合唱作品を作ったが、一方で今日作られるもっとシンプルな合唱作品も美しく興味深いものである。両者は共存し、決して競い合うものではない。
心に響くなら、それはとても良いスタートだ。それが知性も捉えるものであれば、なおさらだ。音楽と芸術はシステムの問題ではなく、感情と気持ちの問題なんだよ。最も重要なことは、良い音楽に限界はないということだ」 ANEKDOTEN, ANGLAGARD に追いつけ、追い越せ。どうぞ!!
THE CHRONICLES OF FATHER ROBIN “THE SONGS AND TALES OF AIROEA” : 10/10
続きを読む NEW DISC REVIEW + INTERVIEW 【THE CHRONICLES OF THE FATHER ROBIN : THE SONGS & TALES OF AIROEA】