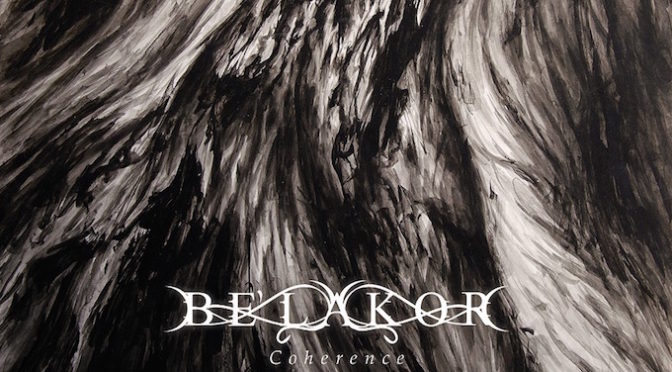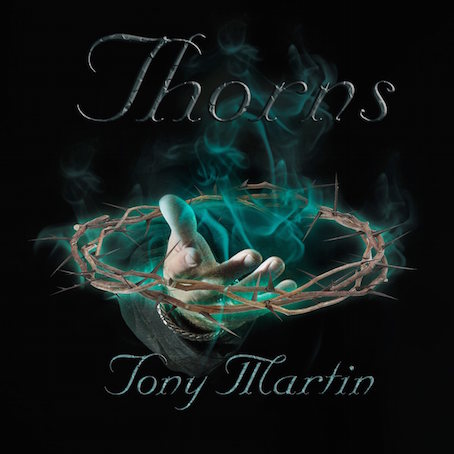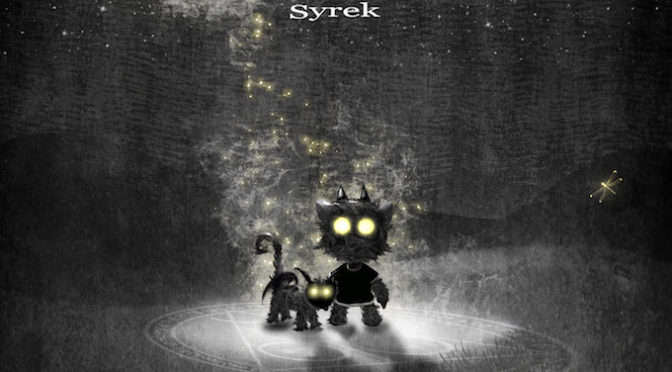EXCLUSIVE: INTERVIEW WITH MANUEL GAGNEUX OF ZEAL & ARDOR !!
ALL PHOTOS BY GEORGE GATSAS
“For The Moment I Just Make Music That I Personally Enjoy. There Was No Intention Of Revitalising a Genre Or The Hubris Of Thinking I Can Rebirth Anything. Only Time Will Tell If It Has Any Impact. Until Then I’ll Just Keep Making Music.”
DISC REVIEW “ZEAL & ARDOR”
「すべてクロスオーバーしているんだ。全く違う分野での経験や視点が、別の分野での新しいアプローチにつながることも多いんだよね。それは私のクリエイティビティにとても役立っているよ」
Manuel Gagneux は、あまり考えることが好きではありません。というより、考えすぎることが嫌いなのです。物事の仕組みに興味を持ち、一時期は物理学を専攻し現在は VR の開発に携わるほど知的な人物であるにもかかわらず。ただし、異なる視点や異なる考え方を受け入れることが創造性をふくらませ、人が “傲慢” になることの抑止力であることを知っています。Manuel はすべてにおいて、傲慢が人類の敵であることを本能的に知っているのです。
「これほどの人気になるとは思ってもみなかったよ。見ていて楽しいバンドと一緒にツアーができたことは、この上ない成果なんだ。すべてが私たちにとって驚きなんだよ」
Manuel は、ZEAL & ARDOR の成功が “滑稽” だと語っています。なぜなら、成功は彼が求めていたものではなかったから。バンドを始めようさえとしたわけでもありません。というのも、このバンドは、ウェブ・フォーラムで、一緒になるはずのないジャンルをミックスするという奇抜なアイデアを募集したのがきっかけだったから。ZEAL & ARDOR は、抑圧された黒人奴隷の歌とブラックメタルを混ぜようという提案から生まれたものです。しかし、それは彼にとって多くの音楽的実験のひとつでした。
「”成功 “が定義される限り、音楽はポピュラリティに過ぎない。そして、人気というのは永久に続くものではないんだ。それが、私がずっと前に理解したこと。だから、私はそれを考えないことにしている。そして、人気はいつ崩れ落ちるかもしれないし、長い時間をかけて消えていくかもしれないことも承知している」
それでも、マニュエルはこの成功にとても感謝をしています。それは、芸術的に解放され、重荷にならないものである限り。MESHUGGAH, OPETH といったビッグネームとの共演や、今年のArcTanGent フェスティバルのトップを飾るなど、もはや Manuel の進撃をとめるものはどこにもないように思えます。
「今のところ、私は個人的に楽しめる音楽を作っているだけなんだよ。ジャンルを活性化させようという意図も、何かを再生させることができるという傲慢さもないんだ。インパクトがあるかどうかは、時間が経ってみないとわからない。それまでは、ただ音楽を作り続けるよ」
1989年、スイスで音楽家の両親のもとに生まれた Manuel の家では、音楽はある種の象徴でした。彼の母親はソウルとジャズのシンガーで父親はパーカッショニスト。「サルサ・パーカッションね。変なポリリズムで、音楽を聴きたくない人には迷惑な話だよ。両親は私にサックスを吹くことを強要したんだ。大嫌いだった。子供の頃の話だけど。 そしてパンクに出会った。想像以上に醜いBCリッチを買って、それから数年間、部屋に閉じこもったんだ」
バーゼルには巨大で活発なパンク・シーンがあることを知った彼は、10代でそこに参加し、メタルやグラインドコアのより過激なサウンドにすぐに耳を傾けるようになりました。子供の頃、Manuelと彼の仲間は毎週末ライブハウスに行き、ドイツのグラインドバンド Japanische Kampfhörspiele のようなショーを見てぶらぶらしていたのです。Manuel が最初のバンドを結成したのはその頃で、ブラックメタル系のバンド名で、”Ateraxie Austere Assumptionのようなもの” でした。
「他のメンバーの一人がその名前に固執していたんだ。ライブは一切やらなかった。基本的には、リハーサル室で一番安いビールを飲んで、クソみたいなマイクで叫んでいただけなんだ。それは素晴らしいことだったけど」
学問的には、Manuel は「全く教育を受けていない」と言います。彼は頭が良く、文学にとても貪欲でしたが、16歳の時に学校を辞めます。ただし、物理を勉強したいという思いがあり、そのために軍隊に入隊し、その軍隊を通じて大学に入るという道を選んだのです。
「軍に入隊した時、自分のやりたいことを言えるようになっていて、それが核防衛研究所で、そこから大学へ行けるかもしれないと思ったんだよな。でも、ただただ拘束され、怪しげなことをやらされるだけ。楽しかったかって?いやいや、ひどいもんだよ。怒鳴られるし。あそこで何をしたかなんて、本当は話すことも許されないんだ。辞めたくて仕方なかったんだよ」
結局、”祖国への別れも告げずに脱走” し、ニューヨークへと Manuel は急行します。ここで、彼は音楽に専念しました。
偶然にも、年配のブルース・ミュージシャンと一緒に暮らすことになり、スイス人の下宿人がミキシングの仕事をする代わりに、彼が所有する家に家賃なしで住めるように計らってくれました。この頃から、彼はインターネットでアイデアを募集するようになったのです。トライバル・メロディック・ハードコア、グレゴリアン・ポストロック、ナッシュヴィル・パワーエレクトロニクス、バロック・ブローステップなど計47枚の作品が作られましたが、その中で定着したのが ZEAL & ARDOR だったのです。
「初めてインタビューを受けることになったんだけど、”なんでこんなことしなきゃいけないんだ “って思ったんだ。とても馬鹿げていたんだけど、その時点では、本当に突飛な提案の嵐の中で、こういうことに無感覚だった。そして、ロードバーンの質問が来る頃には、信じられないという気持ちで、ただただ笑っていた。それが、今も続いているような感じさ。つまり唖然としてる」
セルフタイトルのニューアルバム。その制作状況は、デビュー作”Devil Is Fine” や、その次の”Stranger Fruit” とは少々異なるかもしれません。Manuel は今や有名人であり、車輪はよりしっかりと道を進み、好奇心よりもむしろ期待が大きい状況ですが、ただし彼はそれでもまだ初期のシンプルさからそれほど離れていないのです。つまり、重要なのは閃きとそれに従うこと。
「アルバムは私の愚かなアイデアをただ凝縮したもの。つまり、何かを得て、試してみて、脚光を浴びたらそれを完成させ、そして、あまりいじりすぎないようにするだけさ。クリエイティブな面では、”ああ、これをやったらどうなるんだろう “と考えることに夢中なんだ。こういう風にアレンジしたらどうだろう?とか鍵盤を入れたらどうだろう?とか。夢中になる子供みたいなものさ。そういう喜びはあるよね」
ZEAL & ARDOR は、アフリカ系アメリカ人のスピリチュアル・ミュージックとブラックメタルを融合させるというコンセプトに本質的に忠実でありながら、いまだに挑戦的であると感じられるバンドであることをセルフタイトルで証明します。
インダストリアルなリズム、優しく奏でられるギター、シンセサイザーのサウンドスケープを新たに纏いながら、歴史の暗い回廊に響く血と炎の濃度は不変。彼らの音楽的特異性はクロスオーバーの魅力を発揮しながらも、これまでで最もヘヴィーなサウンドをまざまざと見せつけました。
“Death To The Holy” や “Church Burns” といった曲名は、ブラックメタルの伝統を意識したものですが、奴隷時代の労働歌のようなスタイルも携え、過去の恐怖をより深く再現します。一部で使用されるドイツ語は、ワーグナーのオペラ、その恐ろしい大災害さえ思い起こさせます。
“Emersion” の美しいエレクトロニクスは、ブラックゲイズの猛風によって容赦なく遮られ、一方で “Golden Liar” はメタリックな重さを湿度の高いアトモスフィアに変換する度量を見せます。ブルースと同様にヒップホップを思わせるリズムとリリックが特徴的な “Bow” を聴けば、Run The Jewels のスリーブに似たアートワークにも納得。”A-H-I-L” のドローンがこの野心的なアルバムを曖昧に終わらせるまで、クリエイターは風変わりで鋭いまま凛としてその才を発揮し続けます。
「例えば、”Death To The Holy” の、あの奇妙でうるさい音が、このアルバムから最初に出てきたものの一つだったんだ。この音はとても迷惑で不愉快だから、これを中心に曲を作らないといけないと思ったんだ。それでこうなったんだよ。私がひとつの音を中心に曲を作り、何千人もの人々がその迷惑なものを聴かなければならないということを考えると、笑わずにはいられないよね。そして、それを楽しまずにはいられない。そのクスッと笑える感覚がない曲を頑なに作ろうとすると、十中八九、悪い音になっちゃうんだよな」
これらすべてをまとめているのが、ZEAL & ARDOR に欠かせない2つの要素です。1つ目は、これらの奇妙な枝が広がる音楽の幹で、何にもまして重要なこと。そうでなければ、全体が機能しないもの。
「私にとって、アトモスフィアは最も重要なもの。その雰囲気が半永久的に続いている限り、不快なノイズやジャンルの変更も許容されるんだ。このアルバムでは、カットされたり、合わなかったりした曲をたくさん書いた。何がこのアルバムの一部となり得るか、何が耳障りでなく面白いリスニング体験になるかを選んだんだよ。それがタイトロックなんだ」
このバンドのもうひとつの重要な部分は、物語性です。奴隷制と解放という概念は見た目よりも緩やかですが、それでも ZEAL & ARDOR を生き生きとしたものにするために非常に重要な役割を果たしています。
「”Devil Is Fine” のテーマは “奴隷のような生活” で、Stranger Fruitは “脱出、脱獄” だったんだ。このアルバムは、実際に逃亡生活を送りながら、あるいはある程度自由になりながら、”これからどうすればいいんだ?”と考えるものなんだよ。新しいフロンティアなんだ」
新しいフロンティア。つまり、くだらない古い概念や常識、権威を疑いブラックメタルのように “燃やしてしまう” こと。ただし Manuel はそれを暴力的なやり方ではなく、同調者を増やしながら達成したいと考えています。破壊というよりも創造で。
「古い権威を燃やす。その意図は大いにあったね。だけどね、ここでも私は、それでオーソリティの見解や権力者のやり方が変わることはないと自覚しているんだよ。だから何かを変えたいというよりは、むしろこれは私自身と、すでに私に同意している人たちの、過去に決別を告げる “宣言” なんだよね」
ZEAL & ARDOR がより直接的で完全に明確な態度を示したのは、2020年にリリースした “Wake Of A Nation EP” の時だけでした。警察官によるジョージ・フロイド殺害事件後の反人種差別デモをきっかけに書かれ、リリースされたこの作品のアートワークは、2本の警棒でできた逆十字であり、6曲は意図的に “ここ数ヶ月で私の仲間に起こったことに対する反応” でした。
「まさにあの事件が原点だった。当時はアメリカにいる家族のことがとても心配で、基本的には自分へのセラピーとしてあの EP を書いたんだ。あのような不確かな時代にいることは本当に恐ろしいことで、他の方法で対応する方法を知らなかったんだ」
ただし、便乗や売名とは程遠い、静かな抵抗でしたが。
「BLM 運動の理念は正しくて当然だと思うよ。どこでもそうだけど、一番悪い人が一番うるさいことが多いよね。私も職業柄、よく叫ぶ人という皮肉があるんだけど (笑)」
Manuel の音楽に対する動機は今も純粋で、他人が喜ぶものを作れば嘘くさくなる。まずは自分が楽しみ、満足するものを作るという方針はいささかもブレることはありません。だからこそ、メタルのリスナーだけでなく、様々なジャンルの信奉者がこの音楽に惹かれるのでしょう。多様性を掲げた多様な音楽で、人々はさらに予想外のこと、驚きを期待するようになりました。そんな上がりきったハードルの上を飛び越えていくのが ZEAL & ARDOR のやり方です。地に足をつけ、傲慢とは程遠い謙虚で寛容なやり方で。
「音楽を作ることは、私にとってとても地に足がついた経験なんだよ。派手なことは何もないし、気張ってもいない。ただ幸運なことに、それに対して人々が感情移入してくれることはあるんだよね。だけど、彼らの経験は私とは異なるもので、異なるけれどそれは両方とも同じように意味があることなんだよね。それが私の音楽が潜在的にできることのすべて。私が世界を変えられると言うのは傲慢で、率直に言って事実ではないよ」
参考文献: KERRANG!:Zeal & Ardor: “I just want to take people by surprise”
ZEAL & ARDOR “ZEAL & ARDOR” : 10/10
続きを読む NEW DISC REVIEW + INTERVIEW 【ZEAL & ARDOR : ZEAL & ARDOR】