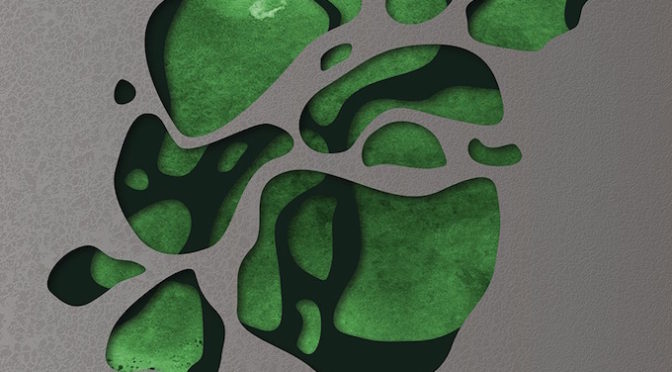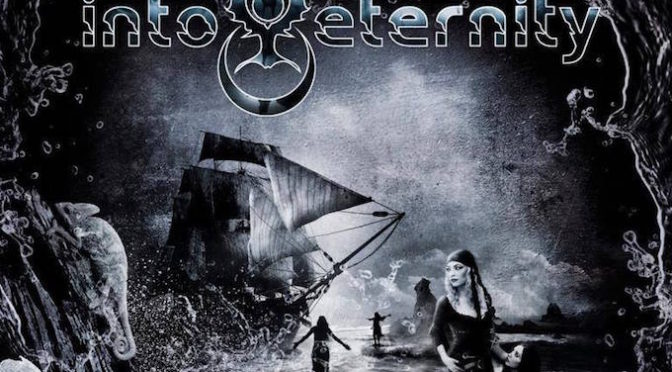EXCLUSIVE: INTERVIEW WITH ANTHONY LUCERO OF CULT LEADER !!
“I Do Feel The Weeping Skull Represnts The Concept Of The Album. Musically And Lyrically We Want The Band To Be An Expression Of The Negativity In Our Lives.”
DISC REVIEW “A PATIENT MAN”
ソルトレイクに兆すエクストリームミュージックの胡乱なニューリーダー。異端の唱道者 CULT LEADER が掲げる教義は、陶酔を誘う魔性のカオスとノワールです。
グラインドコアとスラッジの蜜月を象徴したバンド GAZA の解散は、アンダーグラウンドの世界にとって二重の意味でショッキングな出来事でした。鋭利で野放図なその独創性が途切れることはもちろん、当時のボーカリストが起こしたスキャンダルもまた、リスナーの大きな落胆を誘ったことは確かでしょう。
しかし障害の根源を断ち切り、ベーシスト Anthony をボーカルに据えて再始動を果たした CULT LEADER のある種麻薬的で、妖気振りまく夜叉の佇まいは、GAZA の悲劇を振り払って余る程に鮮烈かつ混沌です。
もちろん、2014年のデビュー EP “Nothing for Us Here” 以来、CULT LEADER はメタリックでブルータルなハードコアの鼓動に、プログレッシブやドゥーム/スラッジの息吹と悲哀の情操を投影し、カオティックで多様な宇宙を創造して来ました。
実際、インタビューで Anthony も 「もし僕たちがある特定のジャンルに限定されてしまったら、もはやバンドとして機能しないとさえ思うんだ。それほど僕たちの音楽性は多岐に富んでいるんだよ。」 と語っています。
ただし、それでも黒の指導者が提示する新たなバイブル “A Patient Man” は、敬虔な信者にこれまで以上の圧倒的驚愕とカタルシスをもたらす大いなる預言書、もしくは洗礼だと言えるでしょう。
CONVERGE と Chelsea Wolfe, Nick Cave の薄幸なる婚姻。涙するスカルをアートワークにあしらったこの作品を、端的に表せばこういった表現になるでしょうか。
言い換えれば、ランニングタイムのおよそ半分はグラインドとハードコアのカオス。一方で残りの半分はバリトンボイスで紡がれるデリケートなノワールへと捧げられているのです。
ブラストビートに導かれ、ポリリズミックなメロディーと無節操なブレイクダウンが花開くオープナー “I Am Healed” や、不協和のシャワーとスラッジのスロウバーンがしのぎを削る “Isolation in the Land of Milk and Honey” が慣れ親しんだ CULT LEADER の経典だとすれば、連続する “To: Achlys”, “World of Joy” の2曲はさながら新経典でしょうか。
Nick Cave, Chelsea Wolfe, DEAD CAN DANCE のプリミティブでノワールな世界観。NEUROSIS の放射線状にも位置する13分間の穏やかなフューネラルは、哀しみと闇、美しき孤独と終焉を反映しながら、ダークアメリカーナにフォークやゴスまで内包し作品に傑出したデュエル、コントラストをもたらしました。
「音楽的にも詩的にも、僕たちはこのバンドを人生におけるネガティブな部分の代弁者としたいんだよ。」と Anthony が語るように、黒雲の途切れないアルバムにおいて、ただ “テンション” という素材を主軸としてこれほどの落差、ダイナミズムを創出するレコードは極めて稀だと言えるでしょう。
「頼むから俺を癒してくれ。」Anthony の咆哮、絶唱はリアルな苦痛、苦悶を掻き立てるマスターの所業。一方で、「愛に満ちた光が世界中の人間に注いでも、俺の下には来ないだろう。」と孤独を綴るその声は、全てを受け入れ語りかけるような慰めと寂寞のトーンでした。
孤高の唱道者は墓標の上で踊る。もしかすると、彼らの新たな教義は、THOU や CONVERGE の最新作とも根底ではシンクロしているのかも知れません。Kurt Ballou のプロダクション、リリースは Deathwish Inc. から。
今回弊誌では、Anthony Lucero にインタビューを行うことが出来ました。「自分たちのコンフォートゾーンの外へと冒険することを、僕たちはいつも心掛けているんだよ。」どうぞ!!
CULT LEADER “A PATIENT MAN” : 10/10
続きを読む NEW DISC REVIEW + INTERVIEW 【CULT LEADER : A PATIENT MAN】