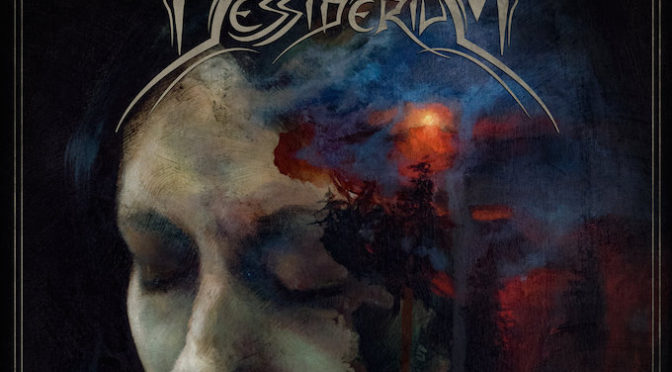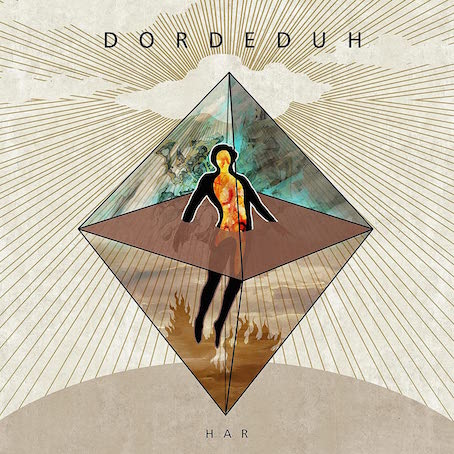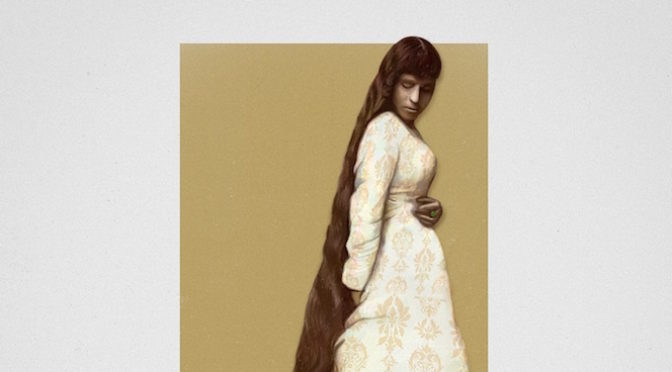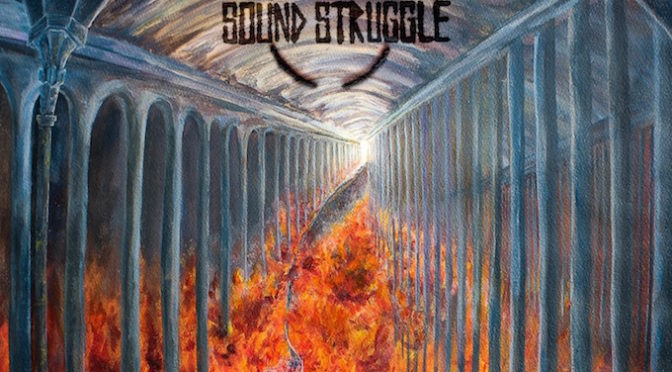EXCLUSIVE: INTERVIEW WITH ALEX HADDAD OF DESSIDERIUM !!
“Video Game Soundtracks Have To Be Addictive To Be Good. You Have To Be Able To Listen To Them For Hours On End And Still Enjoy It, And That’s Something I Strive For In My Own Music As Well”
DISC REVIEW “ARIA”
「あの頃の僕は全然正しい道を歩んでいなかったんだよね。自分の好きなことを追求しないことで、鬱屈とした感情を抱え、何かから逃れようと必死になっていた時期だった。それで、自分の夢に深く執着するようになったんだ。日記に記録したり、一日中夢のことを考えたりして夢はどんどん鮮明になり、離れられなくなっていったんだ」
DESSIDERIUM は、ロサンゼルスのサンタモニカの山で生まれ、アリゾナの砂漠と太陽の下で活動を続けている Alex Haddadの音楽夢日記。自らを熱狂的な音楽オタクと称する Alex は、生き甲斐である音楽を追求できずに悩み、そして自身の夢に囚われていきました。それは彼にとってある種の逃避だったのかもしれませんね。
“妄想は自己犠牲を招き、その苦しみは、外側の世界に自分の内なる感情を反映させたいという願いから、慰めを傷つきながら求めるようになる”。壮大なエクストリーム・プログ絵巻”Aria” のテーマは、アルバムの中で最もシネマティックな “Cosmic Limbs” なは反映されています。バンド名 DESSIDERIUM とは、ラテン語で “失われたものへの熱烈な欲望や憧れ” と訳される “Desiderium” が元になっています。そして彼は今、夢の中から自身の夢を取り戻しました。
「JRPG は長い間、僕の生活の一部だった。日本のロールプレイング・ゲームから得られる経験は、他の種類のゲームから得られるものとは全く別のものなんだよ。普段はゲームを楽しむためにプレイしているんだけど、JRPG はストーリー、雰囲気、アート、キャラクターとの関係、そしてもちろん音楽が好きでプレイしている。ビデオゲームという枠を超えているんだ。別世界へのバケーションのようなもので、そこまで没頭していれば、もちろん僕の書く音楽にも影響を与えているに決まっているよね」
日本のロールプレイング・ゲームの熱狂的な信者である Alex にとって、ゲーム音楽には何時間聴いても飽きない中毒性が必須です。彼の愛するゼノギアス、ファイナル・ファンタジー、ドラゴンクエストにクロノ・トリガーはそんな中毒性のある美しくも知的な音楽に満ち溢れていました。
DESSIDERIUM の音楽にも、当然その中毒性は深く刻まれています。そして彼の目指した夢の形は、狭い箱にとらわれず、ビデオゲームの作曲家、映画音楽、プログロックにインスパイアされた幻想と荘厳を、メタルのエナジーと神秘で表現して具現化されたのです。メランコリーと憧憬を伴った、まだ見ぬ時への期待と淡いノスタルジアを感じさせる蒼き夢。
「OPETH は、僕が最も影響を受けたバンドだろうな。OPETH を知ってから2年ほどは、彼らしか聴かない時期があったくらいでね。彼らの初期の作品は非常に悲劇的でロマンチックで、若くて繊細だった僕の心に深く響いたんだよ」
オープニングの “White Morning in a World She Knows” のアコースティックな憂鬱とメランコリックな美声の間には、明らかに OPETH の作品でも最も “孤独” で Alex 最愛の “My Arms, Your Hearse” の影を感じます。しかし、そこから色彩豊かなシンフォニック・プログレへと展開し、後に KRALLICE ライクなリフが黒々とした “複雑な雑音” を奏でると DESSIDERIUM の真の才能が開花していきます。さながら WILDERUN のように、DESSIDERIUM は OPETH との親和性をより高い次元、強烈な野心、多様なメタルの高みに到達するためのプラットフォームとして使用しているのです。
“Aria” が現代の多くの” プログデス” 作品と異なるのは、”The Persection Complex” が象徴するように、そのユニークで楽観的なトーンにあるとも言えます。Alex は、暗さや痛みの即効薬であるマイナースケールをあまり使用せず、より伝統的なメロディーのパレットを多様に選り分けて描いていきます。
パワー・メタル的な “ハッピー” なサウンドとまでは必ずしも言えないでしょうが、醸し出すドラゴンと魔法のファンタジックな冒険譚、その雰囲気は、ほとんどのエクストリーム・メタルバンドが触れることのできない未知の領域なのですから。そうして陰と陽のえも言われぬ対比の美学がリスナーを夢の世界に誘うのです。
今回弊誌では、Alex Haddad にインタビューを行うことができました。「スーパー・ドンキーコングを差したゲームボーイ・カラーを持ち歩き、ヘッドフォンをつないでゲームの一時停止を押すと、ゲームをプレイしなくてもサウンドトラックが流れ続けたのを鮮明に覚えているよ。僕はヒップホップのアルバムを聴いているようなふりをして、実はゲームの音楽に合わせて架空のラッパーが詩を歌うことを想像していた」もし、OPETH と YES と WINTERSUN が日本のロールプレイング・ゲームのサウンドトラックを作ったら。G(ame) 線上のアリア。そんな If の世界を実現するプロジェクト。どうぞ!!