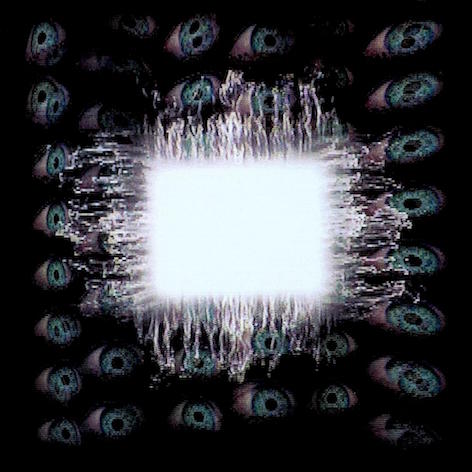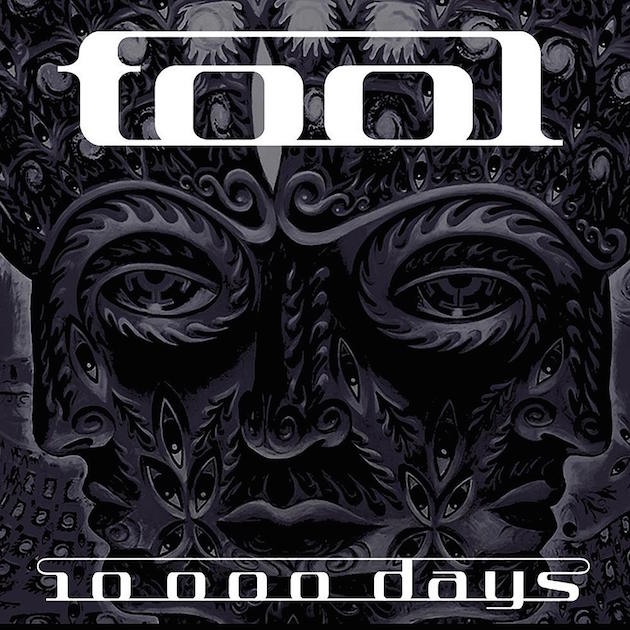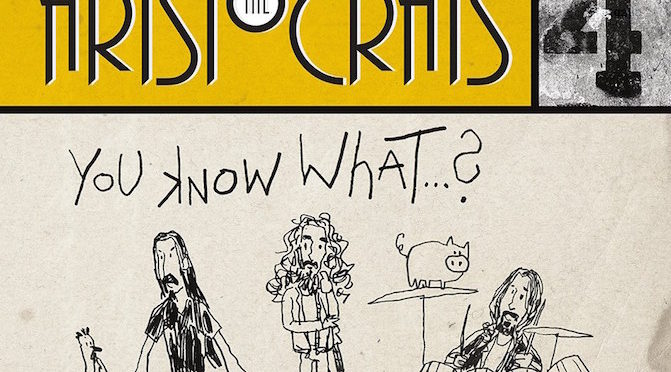COVER STORY: OPETH “IN CAUDA VENENUM”
“The Last Death Metal I Bought Because I Was Interested Was “Domination” by Morbid Angel. That’s 1995, a Long Time Ago Now. I’m Not Saying It’s Just Been Bad Releases Since Then, Of Course Not, But That’s The Last Time I Felt Like I Wanted To Hear What’s New.”
THE STORY BEHIND “IN CAUDA VENENUM”
1995年 “Orchid” で闇の蘭を咲かせた “月の都” は、デス/ブラックメタルを縦糸にプログロックを横糸に織り上げる華麗なタペストリーを創造し続け、尊き北欧の激情とメランコリーをロック史へと刻んでいます。昨今、デス/ブラックメタルへの傾倒は確かに薄れましたが一方でクラッシックロック、フォーク、サイケデリックとそのテリトリーは拡大を遂げ “In Cauda Venenum” は魅力的な音楽の交差点にも思えます。
マスターマインド Mikael Akerfeldt はスウェーデン語と英語の二ヶ国語でこの新たなタペストリーを織り上げる決定を下します。OPETH がスウェーデン語でレコーディングを行ったのは、ROXETTE のシンガー Marie Fredrikkson のカバー “Den Standiga Resan” 以来。
そのアイデアは、Mikael が娘を学校に送った時に降りて来たようです。「別にクールな理由がある訳じゃないんだ。ただやりたいからやっただけさ。いつも俺は、アルバムごとに新たなアイデアを試そうとしているからね。そしてたまたま今回はそれがスウェーデン語だった訳さ。」
ただし音楽を先に生み出し、後に歌詞をつけるのが Mikael のライティングスタイルです。普段は50分ほどのマテリアルで “打ち止め” する Mikael ですが、”In Cauda Venenum” のライティングプロセスでは溢れ出るアイデアは留まるところを知りませんでした。
「この作品ではこれまで以上に書いて書いて書きまくった。それで3曲もボーナストラックがつくことになったんだ。」
スウェーデン語のアイデアは、当初メンバーたちの同意を得られなかったと Mikael は語っています。ただし、何曲かのデモを聴かせるとその考えは180度変わりました。
「奇抜なアイデアと思われたくはなかったんだ。いつも通りやりたかったからね。ただ別の言語を使っているというだけでね。」
スウェーデン語バージョンと英語バージョンの違いは Mikael の歌唱のみ。「言葉がわからないからアルバムをスキップしてしまうのでは」という不安から英語でも吹き込むことを決めた Mikael ですが、彼のクリーンボイスはビロードの揺らぎで溶け出し、スウェーデン語の違和感を感じさせることはありません。むしろ際立つのは言葉に宿るシルクの美しさ。
実際、その不安はすっかり杞憂に終わりました。Billbord のハードロックアルバムチャート3位、ロックアルバム9位の健闘ぶりはそのアイデアの魅力を素直に伝えています。
どちらかと言えば Mikael はスウェーデン語のバージョンを推奨しているようです。
「スウェーデン語がオリジナルで最初に出てきたものだから、やはりイノセントだし少しだけ良いように思えるよ。まあ選ぶのはリスナーだけどね。」
故にアルバムタイトル “In Cauda Venenum” はどちらの言語にもフィットするようラテン語の中から選ばれました。「尾には毒を持つ」ローマ人がサソリの例えで使用したフレーズは、フレンドリーでも最後に棘を放つ人物のメタファー、さらには “想像もつかない驚きを最後に与える” 例えとして用いられるようになりました。
Travis Smith が描いたアートワークもその危機感を反映します。窓辺に映るはメンバーそれぞれのシルエット。ヴィクトリア建築の家屋は悪魔の舌の上に聳えます。「悪魔に飲み込まれるんだ。最後には不快な驚きを与えるためにね。」
ではアルバムに特定のコンセプトは存在するのでしょうか?
「イエスと言うべきなんだろうがノーだ (笑)。コンセプトアルバムとして書いた訳じゃない。ただ、”Dark Side of the Moon” みたいなアルバムだと思うんだ。あの作品を聴いてもコンセプトは分からないけど、循環する密接なテーマは感じられる。KING DIAMOND みたいに明確なコンセプト作じゃないけどね。だから俺は言ってみれば現代の “リアル” をテーマにしたんだと思う。」
2016年にリリースした “Sorceress” との違いについて、Mikael は前作はより “イージー” なアルバムだったと語ります。
「”Sorceress” はストレートなロックのパートがいくつか存在するね。構成もそこまで入念に練った訳じゃないし、ストリングスもあまり入ってはいないからね。」
一方で “In Cauda Venenum” は 「吸収することが難しく、”精神分裂病” のアルバム」 だと表現します。その根幹には、深く感情へと訴えかける遂に花開いた第2期 OPETH のユニークな多様性があるはずです。
さらにギタープレイヤー Fredrik Åkesson もここ10年で最も “練られた” アルバムだと強調します。
「”Watershed” 以来初めてレコーディングに入る前にバンドでリハーサルを行ったんだ。僕はいつもそうしようと主張してきたんだけどね。おかげで、スタジオに入る頃には楽曲が肉体に深く浸透していたんだ。そうして、可能な限りエピックなアルバムを製作するって目標を達成することができたのさ。」
そして Mikael からのプレッシャーに苦笑します。
「僕はギタリストにとって “トーン” が重要だと思っている。理論を知り尽くしたジャズプレイヤーでもない限り、トーンを自分の顔に出来るからね。”Lovelorn Crime” では Mikael から君が死ぬ時みんなが思い出すようなギターソロにしてくれって言われたよ。(苦笑)」
では Fredrik は現在の OPETH の音楽性をどう思っているのでしょうか?
「もし “Blackwater Park” のような作品を別のバージョンで繰り返しリリースすれば停滞するし退屈だろう。ただあの頃の楽曲をライブでプレイするのは間違いなく今でも楽しいよ。Mikael のグロウルは今が最高の状態でとても邪悪だ。だからまたいつかレコードに収録だってするかも知れないよ。」
Mikael が OPETH を政治的な乗り物に利用することはありません。それでも、スウェーデンの “偽善に満ちた” 社会民主労働党と右派政党の連立、現代の “リアル” を黙って見過ごすことは出来ませんでした。
「”Hjartat Vet Vad Handen Gor/Heart in Hand” はそうした矛盾やダブルスタンダードについて書いた。俺の社会民主的な考え方を誰かに押し付ける気はないんだけどね。アイツらと同じになってしまうから。だけど奴らの偽善だけは暴いておきたかった。」
Mikael にとってそれ以上に重要なことは、涙を誘うほどにリスナーの感情を揺さぶる音楽そのものでしょう。
「もっとリスナーの琴線にふれたかったんだ。究極的にはそれこそが俺の愛する音楽だからね。ただ暴れたりビールを飲んだり以外の何かを喚起する音楽さ。つまり、このアルバムをリスナーの人生における重要な出来事のサウンドトラックにしたかったんだ。上手くいったかは分からないけどね。」
もちろん、Mikael は2011年の “ウルトラ-プログレッシブ” な “Heritage” 以降、ファンが “OPETH は今でもメタルか?” 論争を繰り広げていることに気づいています。
「それについて話す前に定義しておくことがある。彼らの言う “メタル” って何なんだい?彼らは俺と同世代?若いの?年上なの?俺の “メタル” って何なんだよ?」
そうして様々なファンと話をするうち、Mikael は一つの結論へと達します。「みんなが考えている”メタル” と俺の “メタル” は決して相容れない。」
“Heritage” の顔面リンゴが象徴するように、マッチョなメタルのイメージに疲れ果てたとも。
「アー写をマッチョでシリアスに撮るのもバカらしくなってね。”Watershed” から自分たちを美化するのはやめたんだ。あのアルバムの裏面には俺たち全員の顔をミックスした醜い男が写っているだろ?彼は “Jorge” って言うんだ。」
では、なぜ Mikael はデスメタルから距離を置いたのでしょう?
「最後に買ったデスメタルのレコードは、1995年 MORBID ANGEL の “Domination” だ。以来良いデスメタルレコードがないとは全然思わないけど、俺が新作を聴きたいと思ったのはあれが最後だったんだ。MORBID ANGEL はデスメタルの先頭を走っていた。David Vincent にあなたがいなければバンドをやってなかったと伝えたくらいにね。だからデスメタルは俺にとって間違いなく重要だ。
ただ、”Watershed” でやり切ってしまったんだ。あれ以上良いものは作れない。スクリームボーカルも古い物以外聴かないしね。」
とはいえ、Mikael も音楽ファンが特定のジャンルに所属することを重要視する習性は理解しています。それは何より、過去の自分が生粋のメタルヘッドだったから。数十年の時を経て、彼のアティテュードを変えた大きな要因の一つは確かに年齢でした。そうして、よりエクレクティックに “ジャンルレス” なバンドへと進化を遂げた OPETH。
「もう俺たちがどこかのジャンルに所属しているとは思っていないよ。俺らのファン、特に若いファンの多くはメタルヘッドでいたいと思っていると感じるね。だから俺は自問自答を始めるんだ。俺にとってメタルでいることは重要か?いやそうじゃないってね。だけどまあ、まだケツの青いキッズから KILLSWITCH ENGAGE の新作は聴いた?あれこそが真のメタルだ。あんたはそうじゃないなんて教えられたくはないんだけどね。」
常にポジティブに思える Mikael ですが、OPETH の成功にあぐらをかいているわけではありません。この10年、彼は全てのアルバムでこれが最後の作品かもしれないと思いながら臨んできました。
「俺にとってこの考え方は良いんだよ。怠惰にならず、過去の焼き直しにも用心するからね。」
Mikael はファンのヤキモキした気持ちさえ楽しんでいるフシがあります。
「リスナーが決して確信できないところが気に入っている。いつも期待するものや望むものを届けようとしていると安心して欲しくないんだよ。彼らが完璧にクソだと思うものをリリースするかもしれないけど、俺らはいつも “これが俺たちのやりたいこと” ってアティテュードでやるからね。君がもしデスメタルのファンで、”Blackwater Park” みたいなアルバムを望んでもそれは叶わないよ。だって俺らはもうあの場所に興味がないし、もっとチャレンジングな地点にいるからね。」
続きを読む COVER STORY + NEW DISC REVIEW 【OPETH : IN CAUDA VENENUM】