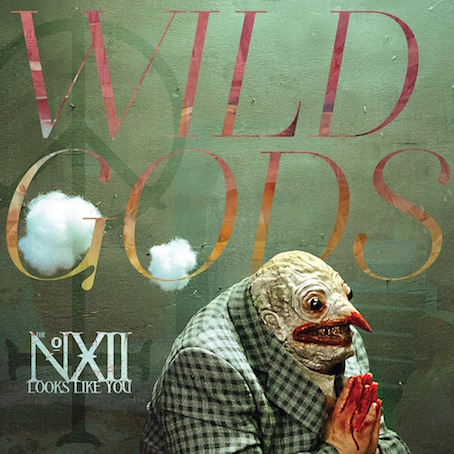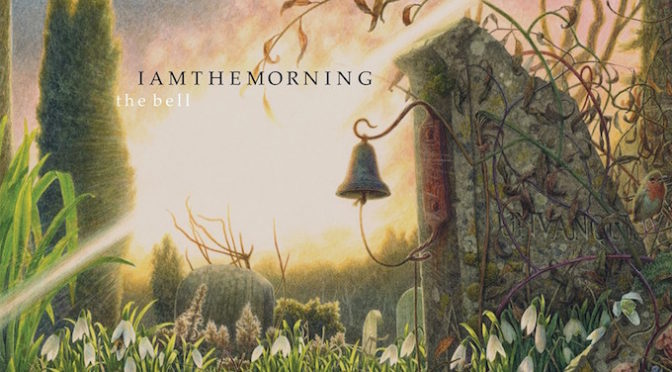COVER STORY : JINJER “MACRO”
“I Was Too Young To Remember Life In Soviet Union, But The Spirit Of Soviet Union Is Still Here. I’m Living In An Apartment Built Maybe 40 Years Ago, And My Parents Live In Such An Apartment, As Well. All Our Shops And Supermarkets Are Situated In Buildings Built Then. So It Is Still Sike Soviet Union. And There Are a Lot Of People Who Still Have Soviet Union In Their Heads And Their Minds.”
HOW JINJER SINGER TATIANA CROSSES MUSICAL, LYRICAL, AND UKRANIAN BORDER
「時に穏やかで平穏。だけど時に人々は何かが起こるのをただ待っている。今現在、少なくとも爆撃はされていないわ。それは良い事ね。」
JINJER のボーカリスト Tatiana Shmailyuk はウクライナのドネツクにある故郷ゴルロフカについてそう話します。彼女とバンドメイト、ベーシストの Eugene Abdiukhanov、ギタリスト Roman Ibramkhalilov、そしてドラマー Vladislav Ulasevich が最初にドネツクから逃れたのは2014年のことでした。それから程なくして、ウクライナの内戦を装った現在も続くウクライナとロシアの衝突、クリミア危機が勃発したのです。
「良い時期に脱出したと思うわ。だって数ヶ月後には国境地域を跨ぐことさえ本当に不可能となっていたんだから。」
戦場から逃れる中で、JINJER は東部から西部へと800マイルを移動してポーランドとの国境に近いリヴィウに立ち寄りました。
「だけどすぐに退屈してしまったわ。旅行者のための街だったから。家も借りたんだけど、水道、電気、暖房設備に問題があって住むことは難しかった。だからもっと文明化された場所へ移ることにしたの。」そうして Tatiana 達はウクライナの首都キエフへと移り住んだのです。
では、ウクライナの風土や国民性は JINJER にどういった特徴をもたらしているのでしょうか?
「JINJER は優しさと弱さが等しい土地から生まれたの。ウクライナは経済的には厳しい国よ。特に90年代前半、私たちの親の世代は大変だった。父と母は最低の賃金を得るためでさえ一生懸命働かなければならなかったの。兄と私を養うために。学校や家の近くにもいつも犯罪があったしね。そこから私たちは人生の教訓を多く学んだわ。
だからウクライナ人は精神的にタフなのよ。例えば少々痛くても、医者には行かないわよ。最後まで我慢する。 だからショウもキャンセルなんてしないわ。ジュネーブの灼熱で喉が腫れ上がっても、私はセットを完遂したわ。根性ね。」
ただし、素顔の Tatiana はシャイな一人の女性です。「みんな私を鉄の女か何かだと思っているようだけど、私だって人生全てを恐れているわ。だから演じているようなものよ。みんなと同じようにセンシティブで傷つきやすいの。いつもスクリームしている訳じゃないしね。まあ毎晩叫んでいるけど、朝は叫ばないわ (笑)。」
Tatiana は JINJER を始めるずっと以前から歌い、そしてその咆哮を響かせていました。
「母に言わせれば、とても幼い頃からスクリームしていたそうよ。叫びすぎておなかにヘルニアができたくらいにね。」
稀に叫んでいない時には、ラジオで聴いたロシアやウクライナのポップソングを歌っていました。1989年のヒットソング “Lambada” も彼女のお気に入りです。「ポルトガル語は分からないけど、シンガロングしていれば楽しいわよね。」
シリアスにボーカルへ取り組み始めたのは8歳の時。レッスンを受け、コンサートホールで合唱隊としてコンサートを行いましたが、ダンスの振り付けに悩まされてしまいます。
「二度とやらないわ!ダンスを誰かとシンクロさせるなんて苦行。一人でなら全てをコントロール出来るんだけどね。」
しかしすぐに兄によってロシアンメタルの世界へと誘われ人生が変わりました。中でも、ロシアの IRON MAIDEN と称される ARIA の存在は別格。
「ドネツク、特に私の故郷ゴルロフカの人間は音楽的なのよ。メタルが大好きだしね。偉大なバンドも沢山あったわ。兄もミュージシャンでダークなドゥームバンドでギターを弾いていたの。」
1991年、ソヴィエト連邦が崩壊すると変化は猛烈な勢いで押し寄せました。MTVはウクライナにも NIRVANA や OFFSPRING のウイルスを運びます。
「NIRVANA を聴いてすぐにロシアのロックを忘れたわ (笑)。MTV は最高だった。すぐに OFFSPRING にハマったわ。私たちの街で私は一番の OFFSPRING ファンに違いなかったの。父がテレビの音をカセットに録音する方法を教えてくれてね。友人やクラスメイトとテープの交換を始めたのよ。そうしてリスナーとして音楽体験を共有していたのね。」
OTEP の Otep Shamaya は Tatiana の感性に衝撃を与えました。「この男の人は最高にクールね!って言ったら友人が女の子よって。OMGって感じよ!こんな女の子は初めてだったわ。そうやって私も彼女みたいに衝撃を与えたいって思うようになったの。
私も9歳からずっと男物の服を着ているわ。それって結局、性別で世の男性を虜にしたくないからなんでしょうね。それよりも中身や心で惹きつけたいのよ。去年ツアーで会えたんだけど、酔っ払っていてずっと彼女を賞賛していたことしか覚えていないの。」
2009年、キエフに訪れた SOULFLY が初めてのメタルコンサート。「めったにない機会だったのに、彼氏が誰かと喧嘩をはじめて途中でセキュリティーに追い出されたのよ。その夜はずっと彼を責め続けたわ。」
近年、ツアーで家を開けることも多い Tatiana ですが、それでも継続中の紛争は彼女をウクライナから完全に切り離すことはありませんでした。ただしソヴィエトのアティテュードに魅力を感じることはありません。ソ連が崩壊した時 Tatiana はわずか4歳でしたが、それでも強硬な共産主義の残影は彼女を未だに訶みます。
「ソビエト連邦での生活を思い出すには幼すぎたけど、それでもソ連の精神はまだここにあるの。私はおそらく40年前に建てられたアパートに住んでいて、両親も同様にそんな感じのアパートに住んでいるわ。お店だってスーパーマーケットだって当時建てられたもの。だからここは今でもまるでソ連よ。それにまだ多くの人々が頭や心にソ連を宿しているの。
古い人間をマトリョーシカって呼んでるわ。私の容姿はバスの中でもジロジロ見られるし。ウクライナでは男性でもタトゥーは受け入れられていないの。まだ U.S.S.R の考え方でいるから、異なる人間が気にくわないのよ。そういった年配の人たちはテレビばかり見ているけど、そこに現実は映っていないわ。タトゥー?あなた60歳になったらどうするの?って感じよ。」
青春期を東欧の貧困家庭で過ごした Tatiana の人間に対するダークな見方は、彼女の故郷に限りません。「私は人類が好きじゃないの (笑)。進化で何かがおかしくなったのよ。今では神様や自然を蔑ろにしている。それが私の内なる怒りを呼び起こすのよ。」
母なる自然への愛情は Tatiana をヴィーガンに変えようとしています。「私はまだビーガンになろうとしているところなの。子供の頃あまり裕福じゃない家庭で育ったから、肉を食べる余裕があまりなくてね。だから最近肉をやめて、肉が大好きだって気づいたの。肉の匂いがすると、気が狂いそうよ。でも動物の苦しみや環境を思うとね…。」
幸いなことに、Tatiana はヴィーガンへの願望と肉食への渇望を両立させる解決策を持っています。「人間の肉を食べることが許されるならそうするわ (笑)。そんなに食に貪欲なら、お互いを食べてみない?」
DISC REVIEW “MACRO”
Facebook に次いで世界で2番目に人気のあるソーシャルメディアプラットフォーム YouTube。JINJER が公開した “Pisces” のライブビデオはすでに2800万回の視聴数を誇ります。
当然そこには、ウクライナという出自、さらにジキルとハイドを行き来する女性ボーカル Tatiana の希少性、話題性が要因の一つとして存在するはずです。
ただし、JINJER の音楽がオンラインによくある、短命のインスタントなエンターテインメントでないこともまた事実でしょう。ベーシスト Eugene にとっては音楽が全てです。
「ウクライナ出身だから政治性を求められるのも分かるんだけど、僕らの音楽にかんしては何物にも左右されないんだ。仮にロシア出身だろうと、イタリア出身だろうと同じだよ。音楽と僕たち。全てはそれだけさ。」
つまり、JINJER は同時代の若者に表層から衝撃を与えつつ、実のところその裏側では幾度ものリスニング体験に耐えうる好奇心と思考の奥深きトンネルを掘り進めているのです。
実際、Tatiana は JINJER がスポットライトを燦々とその身に浴びるような集団ではないと語ります。
「有名になりたいって訳じゃないの。今でも私は車ももっていないし築40年のアパートに住んでいるわ。だから第2の “Pisces” を作ろうなんて思わない。JINJER は大人気になるようなバンドじゃないわ。」
とは言え、PROTEST THE HERO の精子と KILLSWITCH ENGAGE の卵子が受精し生まれたようにも思える2012年の “Inhale, Don’t Breath” から JINJER は異次元の進化を遂げています。比較するべきはもはやメタル世界最大の恐竜 GOJIRA でしょうか。それとも MESHUGGAH?
テクニカルなグルーヴメタルに Nu-metal と djent の DNA を配合し、R&B からジャズ、レゲエ、ウクライナの伝統音楽まで多様な音の葉を吸収した JINJER のユニークな個性は全てを変えた “King of Everything” から本格化へ転じたと言えるでしょう。
2019年に届けられた EP “Micro” とフルアルバム “Macro” は双子のような存在で、創造性のオーバーフローの結果でした。
「もともとフルアルバムの予定はなかったんだ。”Micro” は次の作品までの繋ぎって感じだったんだけど、完成が近づくともっともっと楽曲を書きたくなってね。クリエイティブなエナジーが溢れていたんだ。」
無慈悲なデスメタルから東欧のメランコリー、そしてレゲエの躍動までを描く“Judgement (& Punishment)” はJINJER の持つプログのダイナミズムを代弁する楽曲でしょう。
「僕たちの音楽に境界は存在しない。いいかい?ここにあるのは、多様性、多様性、そして多様性だ。」そう Eugene が語れば Tatiana は 「JINJER に加わる前、私はレゲエ、スカ、ファンクをプレイするバンドにいたの。だからレゲエの大ファンなのよ。頭はドレッドにしていたし、ラスタファリに全て捧げていたわ。葉っぱはやらないけど。苦手なの。JINJER は以前 “Who Is Gonna Be the One” でもレゲエを取り入れたのよ。レゲエをメタルにもっともっと挿入したいわ。クールだから。」と幅広い音楽の嗜好を明かします。
判決を下し罰するというタイトルは SNS に闊歩する魑魅魍魎を揶揄しています。「気に入らなければ放って置けばいい。私ならそうするわ。なぜ一々批判的なコメントを残すのかしら?それって例えばスーパーに行って質の悪いバナナを見る度、おいクソバナナ!お前が大嫌いだ!さっさと木に戻りやがれ!って叫び始めるようなものでしょ?(笑) 私は他にやるべきことが沢山あるの。そんなことに割くエナジーはないわ。」
“On The Top” は2020年代の幕開けを告げる新たなプログアンセム。SOULFLY を想わせるトライバルパーカッシブと djent の小気味よいスタッカートシンコペートは Tatiana のフレキシブルな歌呪術へと怪しく絡みつき融けあいます。
「ラットレースのラットを演じてるって感じることはある?世界はどんどんそのスピードを増し、誰もが成功と呼ばれるあやふやなものに夢中よね。”On The Top” で訴えたのは、名声や成功に伴う孤独と満たされない心。”トップ” に到達するため犠牲にするものは多いわ。その梯子は本当に登る価値があるの?犠牲を払うのは自分自信なんだから。」
ウクライナの陰影を抱きしめたコケティッシュな “Retrospective”、ポルトガルのライター José Saramago の著作にインスピレーションを受け、死を地球を闊歩するクリーチャーになぞらえた “Pausing Death”、大胆にも聖書を再創造したと語る “Noah” など、Tatiana の扱う題材は多岐に富み、世界をマクロ、そしてミクロ、両方の視点から観察して切り取るのです。
「ウクライナでは決してメタルは歓迎されていないの。にもかかわらず素晴らしいバンドは沢山存在するわ。ただ、チャンスを把み国境を超えることは本当に難しいの。」
アイコニックな女性をフロントに抱き、多様性を音楽のアイデンティティーとして奉納し、ウクライナという第三世界から登場した JINJER は、実はその存在自体が越境、拡散するモダンメタルの理念を体現しています。音楽、リリックのボーダーはもちろん、メタファーではなく実際に険しい国境を超えた勇者 JINJER の冒険はまだ始まったばかりです。
参考文献: FROM WARZONES TO MOSH PITS: THE EVOLUTION OF JINJER’S TATIANA SHMAILYUK: REVOLVERMAG
Ukrainian Metal Band Jinjer Delivers on Its Promise With New Album ‘Macro’